前回の記事はこちら「医療的ケア児の入院で感じた、病院のあたたかい配慮と在宅へのつながり【実体験】」
私と娘は2か所の大学病院に通っています。
どちらも専門的な診療科がそろっているので、
医療面でもとても安心して通える病院です。

家から少し離れたところにA小児専門病院があるのですが、
「A病院だったら、もっと子ども向けの工夫がされているのかな?」と思うこともあります。
もし小児専門病院に通われている方がいたら、
コメントでどんな工夫があるのか教えてもらえるとうれしいです!
今回も、元看護師でもある私が、実際に付き添い入院をして驚いたことを5つご紹介します。
病院によって特徴があるので、
「うちの病院はこうだったよ」という違いを感じてみるのもいいかもしれません。
1)乳幼児用ベッドが高くて大変…でも安全のため
乳幼児用のベッドの特徴は、
大人用ベッドと比較して高さがあり、
ベッドを囲うように高い柵があることです。
・治療・処置のしやすさ
・こどもが柵を乗り越えないように
ベッドも柵もしっかりと高く作られています。
ただ、付き添ってお世話をしていると、
上がったり下りたりがとても大変です。
特に、急いでミルクを作ったり、ケアの物品をとるときなど、
足腰への負担が大きいなと感じました。
急いで降りるときは、ついバランスを崩しそうになります。

同じ重症心身障がいの子を持つ友人は、転落の可能性が低いと考え、
看護師さんに大人用ベッドに変更してもらえるか相談したそうです。
OKだったと聞いて、私も今後辛かったら相談してみたいと思います。
ただ、私の娘はまだ寝返りをしませんが、
今後寝返りをするようになったら、転落の危険が出てくるかもしれません。
ちなみに、認知症のある大人の方など、非常に転落のリスクが高い方には、
あえてベッドを使わずに「畳に敷布団」を敷いて過ごしてもらうこともあります。
転倒を完全に防ぐのは難しいからこそ、
「転んでも大けがをしにくい環境」を整えることが大切です。

対象年齢は0~5歳未満ですが、
身長が80~90cmを超えると、
ベッド柵を乗り越えるリスクが高まります。
そのため、実際は2~3歳以降は注意が必要とされ、
状況によっては他の種類のベッドに変更するケースもあります。
転落・事故防止のためにも、
親が部屋を離れる際は、ベッド柵をしっかり上げるよう指導されることが一般的です。
※ベッドの選択・乳幼児用ベッドの仕組み | 看護roo![カンゴルー]
↑看護師さん向けの用のサイトですが、詳しく乳幼児用ベッドについて書かれています。
※参考:小児用ベッドからの転落に関連した事例
↑医療者向けサイトです。
2)ミルク用のお湯がある
病棟には、電子レンジ・洗濯機・乾燥室・シャワー室など
付き添いする保護者も生活しやすい環境が整えられています。
中でも、ミルク用の70度のお湯が出る専用のポットが設置されていた時は
助かりました。
ミルクを作るときに、簡単に必要なお湯が使えるのは嬉しいです。

医療的ケアが必要な子どもによっては、
2歳を過ぎても、栄養剤ではなくミルクを飲んでいる方もいるそうです。
私の娘も経管栄養でミルクを注入しています。
我が家にとっても粉ミルクは、きっとこれからも
長くお世話になるんだろうなと感じています。
3)プレイルームがある!でも利用にはルールも
おもちゃや絵本があるプレイルームが設けられている病棟もあり、
親や保育士さんと楽しそうに遊んでいる様子も見られました。
ただ、感染対策のため、赤ちゃんでもマスク着用が必須だったため、
私の娘は利用できませんでした。
おもちゃを口に入れないようにするなど決まりがいくつかあり、
感染予防にも配慮されていました。
4)親向けのお弁当や給食の販売がある
病院によっては、お弁当屋さんが病棟や病室に来て、
付き添いの親向けにお弁当を販売してくれたり、
病院の給食を頼めるところもあります。
毎日コンビニや売店に行く余裕がないときも、
病室まで届けてくれるサービスがあると、とても助かります。
私の場合は、娘やケアが落ち着いているときでしか
ご飯を食べられないため、
コンビニで買った手軽に食べられるごはんを冷蔵庫に沢山いれて、
好きなタイミングで食べていました。
でもたまに飽きてしまうので、
そういうときはこのサービスを利用していました。

「今日のごはん、どうしよう…」というストレスが軽減される取り組みは
嬉しいですよね。
5)親同士が仲良くなれる
私の初めての入院は、大学病院の産科でした。
あのときは、「ママ友ができるのかな」と少しワクワクしていました。
でも、みなさんそれぞれに事情を抱えているため、
患者さん同士は、会釈する程度。
会話は、医療スタッフや面会の方だけでした。
大部屋のカーテンは誰も開けている方はいなくて、
産科のオルゴールのBGMだけが静かに流れる環境でした。
またNICUでも会釈程度でした。
一方、小児科では、日中はにぎやかな声や泣き声なども聞こえてきます。
長期入院になると、顔なじみの親御さんも増え、
ミルクのお湯をもらいに行ったときなどに、
「同じくらいの年齢ですね」なんて声をかけ合うこともあります。
他の患者さんも、笑顔でおしゃべりするような場面が見られることもありました。
おわりに
冒頭でご紹介した小児専門「A病院」では、
最近、赤字経営やスタッフ不足により、一部の取り組みが縮小しているという話も耳にします。
物価や人件費の上昇、医療スタッフの不足など、
地域の医療を取り巻く環境は厳しさを増していて、
「これから、子どもたちの医療はどうなるんだろう?」と不安に感じることもあります。
★この記事が参考になったらクリックお願いします。応援していただけると嬉しいです
にほんブログ村
しかし、遠隔診療やAIの技術も進んできていて、これからの医療の変化にも期待が高まります。
子どもたちやご家族が、今後もより安心して医療を受けられる未来になるといいですね。

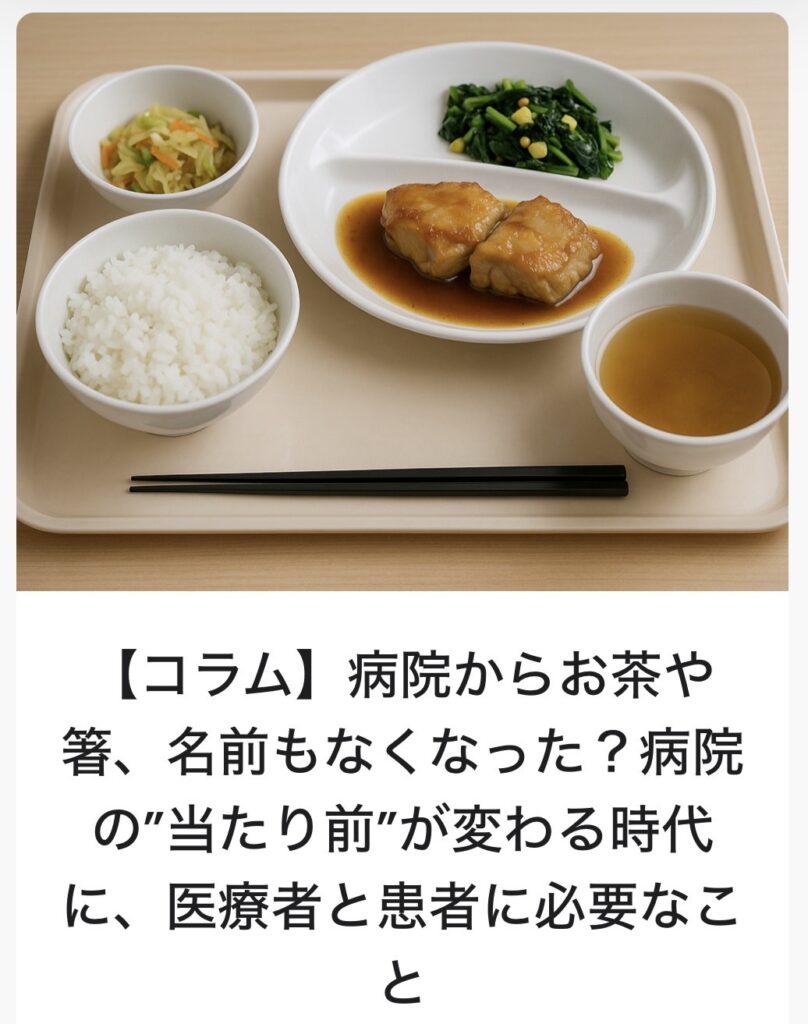
No responses yet