みなさんは、「先のこと」をどこまで知りたいと思いますか?
病気がこの先どう進行するのか、
どんな症状が出るのか、
どんな選択肢があるのか──

私は、職業柄もあり、
できる限りすべてを知りたいタイプです。
知っておけば、すぐに異変に気づけて、対策もできるし、
心構えもできる。
そのときが来たときに、
最善の選択をする準備ができると思っているからです。
でも、私の夫は違います。
「知るのが怖い」と言います。
「必要がなければ、知らなくてもいい」とも。
同じ病気の子のドキュメンタリーがちょうど
TVで放送されていても見ませんし、
SNSで情報をチェックすることもありません。
けれど不思議なことに──
実際に子どもの状態変化が起きたとき、
夫は私よりも冷静に、そして的確に情報を集め始めます。
“その時その時で、必要なことに集中して過ごしたい”、
という夫なりの向き合い方なのだと思います。
医療の現場でも、
たとえば、「癌であったら、知りたくない」と、
患者さん自身が言うこともありますし、
逆にご家族から「本人には病名を伝えないでほしい」
「自分も知りたくない」と、
希望されることもあります。
今回は、そんな「知ること」「知らないこと」について、
医療的ケア児の親である私の視点から掘り下げてみたいと思います。
目次
1.知ることのメリット
病気が進行するとどんな症状が出るのか、
どんな選択肢があるのかをあらかじめ知っておくことで、
私たちは心の準備や治療の選択、生活の調整がしやすくなります。

たとえば、私の子どもは風邪でも重症化しやすいので、
発熱や感冒症状があれば、
すぐに入院準備をして病院に向かいます。
医療的ケア児の親としては、
・必要となる制度や支援を見直し、
・訪問看護の時間の変更や回数を増やしたり、
・医療機器の導入についても、
前もって相談することもできます。
「そのとき」になってから考えるのではなく、
「そのとき」に向けて動いておくことで、
子どもにとっても自分たちにとっても、
より良い選択ができるという安心感があります。
ただ、知りすぎることが必ずしも、心を軽くするとは限りません。

私は、子どもが少しでもむせると
「誤嚥性肺炎になるのでは」と冷や冷やします。
ミルクの投与スピードが早すぎるのでは?
姿勢が悪いのでは?
栄養剤を変えたほうがいいのか?
またむせたら命にかかわるのではないかーー
毎回のケアに怯えてしまう自分がいます。
咳が出るたびに胸が痛み、保守的になってしまうこともありました。
でも、そんな中で気づいたこともあります。
子どもには、私の想像を超えた
”子ども自身の力と無限大の可能性”がある。
情報を集めることはとても大切です。
けれど、ネットや本で得た知識がすべての子どもに
当てはまるわけではありません。
また、AIや見た情報が間違ったことを言っていたら、
私はその“間違い”を信じてしまうかもしれない。
それが娘の命に関わることだったらと思うと、とても怖いです。
「自分の子どもにとって何が合っているのか」は、
医療者と娘、家族と相談しながら判断する必要があります。
ときには、思い込みや不安が、
子どもの可能性を狭めてしまうこともあるのだと、学びました。
★こちらもご覧ください★
2.知らないことのメリット
一方で、先のことを知らないからこそ、
”今”に集中できるというメリットもあります。
私の夫のように、将来起こるかもしれない症状や予後のことを想像すると、
怖くなったり、必要以上に不安になってしまうこともあります。
知らないことで、不安を最小限に抑え、
毎日を平穏に過ごせる人もいるのです。
私の尊敬する医師が、このようなことを言っていました。
「病気は、いつ・どんなことが起きるか分かりません。
あまり先のことばかり考えて不安になりすぎるよりも、
“今”を大切にして楽しみながら、
何かあったときには信頼できる医師と、
その時に一番いい選択をすればいいと思います」

以前、私は調べすぎて不安で
いっぱいになっていた時期がありました。
夫や医師の言うように、
「先のことを考えすぎない」ことは、
自分の心を守るためには大切なことなのかもしれません。
娘の寿命は、私より短いかもしれません。
でも、だからこそネガティブに過ごすより
一日一日、
一緒に楽しく過ごす時間を大切にしたいです。

医療現場では、患者本人・家族が「詳しく知りたくない」
「余命や進行については詳しく聞きたくない」と希望することがあります。
3.患者本人が“知りたくない”と望む理由
患者本人が「自分は知りたくない」と望むことがあります。
患者が知ることで精神的なショックを受けたり、
治療や生きる希望を見いだせなくなったり、
人生の残り時間に縛られてしまうことを避けたい
という気持ちから来ていることが多いです。
4.家族が“知らせたくない”と考える理由
また、家族が「本人に知らせたくない」と望むことも少なくありません。
その理由はさまざまですが、
「本人が傷ついてほしくない」という想いがあります。
現実を知ることで、本人が落ち込んだり、
希望を失ってしまう。
知って悲しむよりも、残された時間を
平穏に過ごしてほしいと願うあまり、
あえて本人に知らせないという選択をするのです。
「嘘ではないけれど、本当のことも言わない」――
その判断は、家族にとっても大きな負担であり、
時に「これでよかったのか」と苦しみながらの決断でもあります。
5.「知らない権利」とは?

私は、産科に入院中、「お腹の赤ちゃんに心臓の病気があるかもしれない」と産科医から告げられました。
そのため、「専門医に”胎児心エコースクリーニング”を受けましょう」と勧められました。
その際の同意書には、
以下の4つの選択肢が記されていました。
1.検査をして、すべてを知りたい
2.検査をして、一部だけを知りたい
3.検査をして、結果は知りたくない
4.検査はしない
「知りたくない」と希望する方もいて、
その背景には、
異常が見つかった場合に、妊婦や家族が強い不安・葛藤を
抱えてしまう可能性があるからだそうです。
現代医療ではインフォームド・コンセント(説明と同意)が基本ですが、
「知りたくない」と希望した場合、
医療者はどこまで説明すべきか、慎重に判断しなければなりません。
医師の職業倫理指針 第3版でもこのように記されています。
「例外的に、真の病名や病状をありのまま告げることが
患者に対して過大な精神的打撃を与えるなど、
その後の治療の妨げになる正当な理由があるときは、
真実を告げないことも許される。
この場合、担当の医師は他の医師等の意見を聞くなどして、
慎重に判断すべきである。
本人へ告知をしないときには、
しかるべき家族等に正しい病名や病状を知らせておくことが重要である。
また、告知をする場合でも、
家族と共に、説明をする必要がある場合も多い。
医師、本人、家族が協力して病気に立ち向かうことが
必要な場合などには、病名・病状の説明がその第一歩になるからである。
ただし、患者本人が家族に対して病名や病状を知らせることを
望まないときには、それに従うべきである。
家族が患者本人に本当の病名や病状を知らせてほしくないと言ったときには、
真実を告げることが患者本人のためにならないと考えられる場合を除き、
医師は家族に対して、
患者への説明の必要性を認めるように説得することも重要である。
なお、このような経過および事情は、
後日のため記録にとどめておくべきである。」
(日本医師会『医師の職業倫理指針』より)
引用:医師の職業倫理指針[第3版]
医療の現場でも、「知る権利」と同時に「知らない権利」も認められており、
それを尊重する姿勢が求められています。
家族が代わりに説明を受け、
本人には病名や予後の見通しを明かさずに治療やケアを進めるケースもあります。

たとえば、がんなどの病名をあえて伏せて
「慢性的な体調不良」と説明したり、
「検査の一環」として治療を行うこともあります。
ただ、未告知の場合、医療者にとって、
・患者・家族と積極的に深く関わることができない
・患者の残りの人生の過ごし方の選択肢が狭まる
・真実が伝えられないことで、逆に不安や恐怖を強める可能性がある
──そのバランスに、医療者は常に悩みながらも丁寧に対応する必要があります。
6.患者・家族があとから知ってしまったときの対応
本人や家族に病名を伝えない方針で進めていたとしても、
何かの拍子に患者や家族がその事実に気づいてしまうことがあります。
たとえば、医療者の会話、看護記録、
インターネット情報などから「重大な病気なのではないか」
と感じるケースです。そのようなとき、
患者や家族の不安やショックは非常に大きく、信頼関係を失ってしまうこともあります。
その際には、まず本人の気持ちを受け止めることが大切です。
「本当のことが知りたい」
といった感情があれば、誠実に向き合い、
必要に応じて医師や心理職などの専門家が同席して説明を行うこともあります。
一度にすべてを伝えるのではなく、
段階的に説明していくこともひとつの方法です。
大切なのは、本人のペースを尊重しながら、
信頼関係を再構築していくことです。
7.子どもへの伝え方
小児や発達段階にある子どもに病名や病状をどう伝えるかは、
とても繊細なテーマです。
伝えるべきか、いつ・どのように伝えるべきかは、
年齢、理解力、性格、家庭環境などによって異なります。
小さな子どもには、「お腹の中にバイキンがいて、お薬で治すよ」
といった表現を使うこともあれば、
大きな子どもには「検査で分かったことを一緒に考えていこう」
と対話を重視することもあります。
医療チームと連携しながら、
保護者が「どんな言葉で伝えるか」「どこまで説明するか」を
一緒に考えて方針を統一していくことが大切です。

子どもに病名や経過を直接伝えない場合でも、
子どもは自分の体の変化や周囲の雰囲気を敏感に感じ取っています。
だからこそ、「本人の安心感を保つ」「嘘をつかない」
ことを意識した、誠実な説明が必要です。
8.終わりに:今を大切に生きるために
私は「できる限り、すべてを知っておきたい」と思うタイプです。
でも、知ることが不安を増やし、
必要以上に先のことを考えてしまうこともありました。
一方で、何も知らないからこそ、
落ち着いて目の前のことに向き合える人もいます。
「知ること」も「知らないこと」も、どちらが正しいということはありません。
その人にとって、どんな向き合い方が一番心地よく、”自分らしく生きられるのか”。
それを尊重することが大切だと、
今は思っています。
子どもと、家族と過ごせるこの一瞬一瞬を、
これからも大事にしていきたいです。
★この記事が参考になったらクリックお願いします。応援していただけると嬉しいです
にほんブログ村
★こちらもご覧ください★

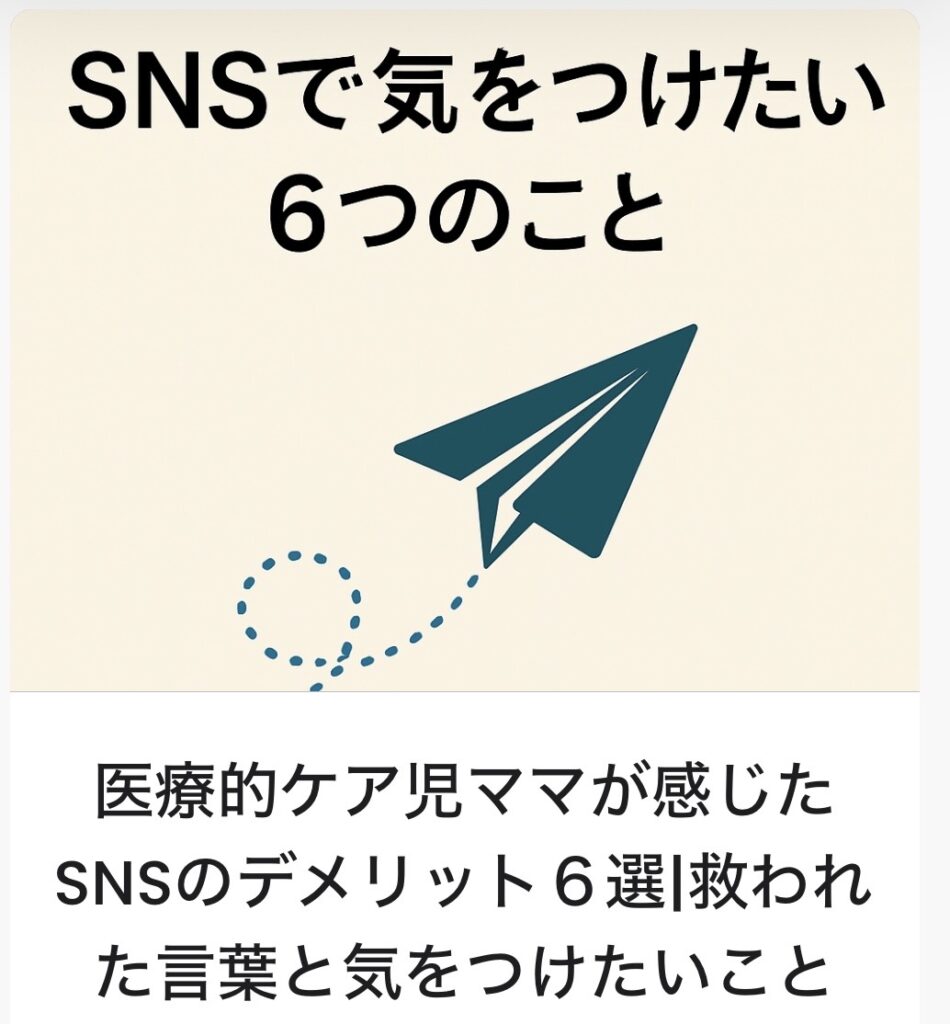
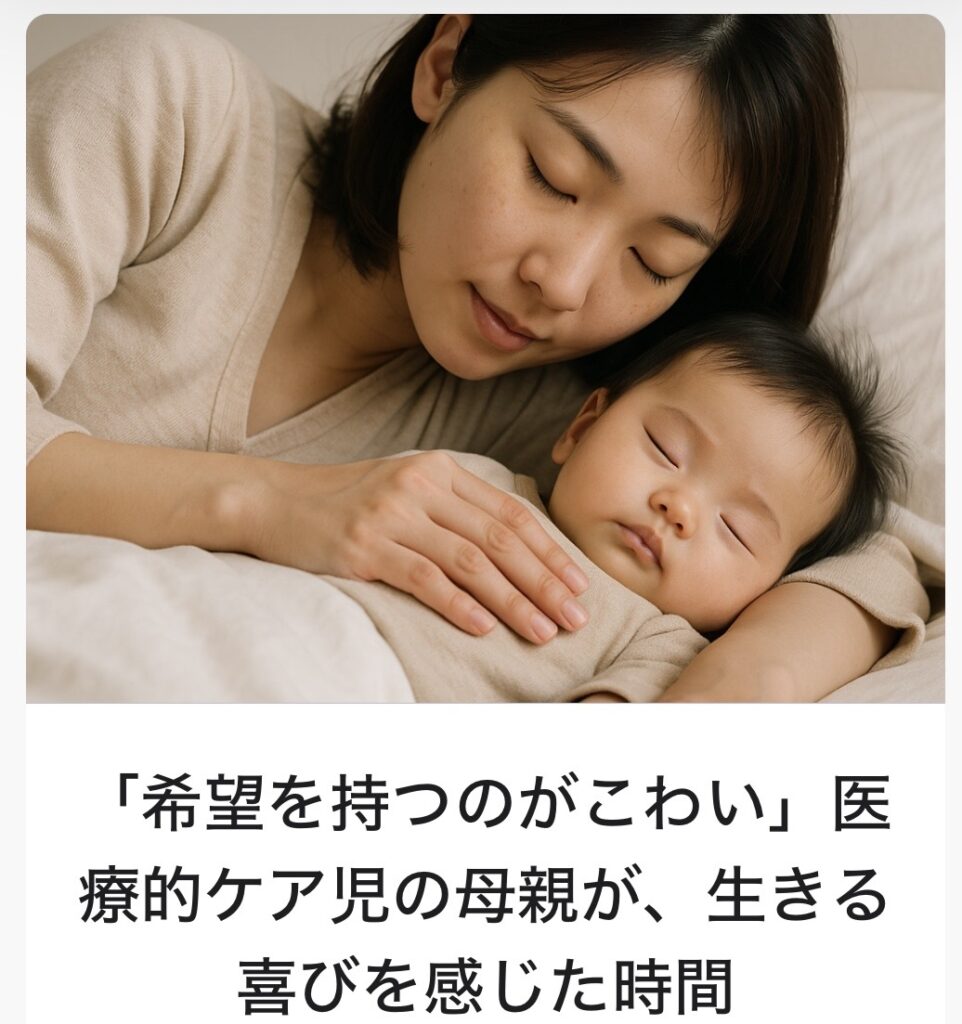
No responses yet