子どもの処置、そばにいたい? それとも待っていたい?
みなさんは、子どもが採血や医療処置を受けるとき、
そばにいたいと思いますか?
それとも、つらい姿を見るのが苦しくて、
待っていたいと思いますか?
あるいは、病院側の方針で、
同席するかどうか決められている場合もあるかもしれません。
私の娘は、ふたつの病院に通っています。
大きな大学病院では、「お母さんは外でお待ちください」と案内されます。
一方、地域に根ざしたもう一つの病院では、
「一緒に処置室へどうぞ」と言われます。

私は看護師としての経験があるため、
つい処置の様子をじっと見てしまいます。
採血の部位を一緒に確認したり、
処置に自然と参加してしまうことも。
失敗してしまったときはつい「あっ」と表情に出てしまい、
医師や看護師に成功してほしい気持ちで、
プレッシャーをかけているかもしれません。
何より、娘が泣いて私を見つめるたび、
胸が締めつけられるような気持ちになります。
「がんばってくれてありがとう」と応援しながら、
自分の中ではいつも複雑な感情が渦巻いています。
目次
1.親の付き添いには、2つの考え方がある
処置や採血など、痛みをともなう場面で親が同席することについては、主に2つの考え方があるそうです。
① 親は同席しない方がいい
理由として、
・親がそばにいるのに助けてくれない状況が、
子どもに“見捨てられた”という不信感を与える可能性がある。
・親が付き添うかどうか判断を迷うことで処置の開始が遅れ、
子どもの不安が長引いてしまう。
・医療スタッフ側にとっても、
親の目の前で子どもを抑える場面を見られたくない、
・採血や処置に対するプレッシャーがかかる。
・親が医療スタッフを見て「乱暴に感じた」「怖かった」と感じ、
信頼関係に影響を与える。
そのため、親は同席せず、医療スタッフが必要に応じて子どもの体をしっかり支え、
短時間で終える方が子どもにとって負担が少ないという考え方です。

しかし、
・子どもは、親がいない不安や恐怖を感じ、
・親も、子どもの泣き声をきいて何もしてあげられない辛さ、
・状況が分からず不安になる欠点もあります。
② 親は同席する方がいい
理由として、
・親と一緒にいると子どもが安心でき、怖さが和らぐ。
・親が処置の大変さを実感できる
採血や点滴が簡単ではないこと、子どもが頑張っていることを感じる。
・医療スタッフとの信頼関係が築ける
丁寧な対応を目の当たりにし、安心や信頼につながる。
・親が子どもを支えることで、スタッフの人数を減らせ、待ち時間の減少につながる。
近年では**「子どもの気持ちに寄り添う」ことが重視されるようになり、
親の同席が推奨される場面も増えているそうです。**
背景には「子どもの権利条約」もあり、
子どもの意見を尊重したり、安心できる環境を整えることが求められています。
参考:子どもの権利条約 | 日本ユニセフ協会
岡本医師のご経験によると、約8割のお母さんが点滴をとるとき
「子どものそばにいたい」と希望しているそうです。
参考:子どもの採血時に親を引き離す4つの理由とその反論。 | 笑顔が好き。
子どもの気持ちを大切にするプレパレーション 札幌病院小児科 | 公益社団法人 北海道勤労者医療協会 -Hokkaido Kin-ikyo-

子どもが、少しでも安心できる処置の時間にするために、
プレパレーション(事前の声掛けや説明、工夫)が、
注目されています。
2.プレパレーションの大切さ
① プレパレーションとは?
医療処置の前に、
子どもの発達段階に応じて説明・準備を行い、不安や恐怖を減らし、
心の準備を整える支援のこと。
目的は:
・「これから何が起こるのか」を理解できるようにすること
・自分の体に起きることに備える“心の準備”を手助けすること
・安心して処置に臨めるようにサポートすること

子どもも、大人も、何をされるか分からないと恐怖ですよね
②年齢によって異なる「プレパレーション」
| 年齢 | プレパレーションの方法例 |
|---|---|
| 0~2歳 | おもちゃや人形で気をそらす 親のスキンシップ・声かけが中心 |
| 3~5歳 | 人形を使って遊びながら 「注射ごっこ」などを通じて理解を促す |
| 6~9歳 | 絵本や写真、言葉での簡単な説明。 「終わったら〇〇しようね」と希望を持たせる |
| 10歳以上 | より具体的な説明が可能。 本人の意思を尊重し、不安に寄り添う声かけが有効 |

小児科のスタッフさんは、「聴診器やボールペンにマスコットをつける」
「キャラクターのエプロンを身に着ける」など、いつも
子どもの不安を和らげる工夫をたくさんされています!
③プレパレーションの例
実際の現場では、どのような声掛けがされているのでしょうか。
🔍【聴診・診察のとき】
- 「くまさんの聴診器で“もしもし”するよ」
- 「お腹に“こんにちは”ってしてもいいかな?」
- 「聴診器、あったかいから安心してね」
- 「くまさんが元気かなって、ちょっとだけ聞かせてね」
💉【採血・注射のとき】
- 「ちっくん、がんばれるようにアンパンマンが応援してるよ」
- 「魔法のテープ貼るね、これが“ちっくん準備OK”のしるし」
- 「お薬が中に入って、元気パワーになるよ」
- 「5秒だけがんばろう!いーち、にーい、さーん…」
👃【鼻吸引・鼻チューブのとき】
- 「鼻のおそうじタイムだよ~、ちょっとくすぐったいかも」
- 「ゾウさんのお鼻みたいに、ビューッと空気とばすよ」
- 「おはなにシャワーするよ〜」
🎵【気をそらす声かけ】
- 「〇〇ちゃんのお歌きかせて〜」
- 「今日の朝ごはん何だった?教えてー」
- 「好きなジュース、なーんだ?」
- 「終わったらシールあげるね!」
🧸【ごっこ遊びに取り入れて】
- 「ぬいぐるみにもやってみようか、ちっくんの練習ね」
- 「アンパンマンにもお薬あげよっか、元気になるかな?」
- 「今日は〇〇ちゃんが先生ね。ママに“もしもし”してあげて」
④親ができる関わり
プレパレーションは医療者だけでなく、親だからこそできる関わり方もたくさんあります。
たとえばこんなことができます:
- 💬 やさしい言葉で説明する
「先生がちょっとチクっとするお薬をするけど、お母さんここにいるからね」 - 🧸 お気に入りのおもちゃや毛布を持っていく
それだけで子どもの“いつも通り”の気持ちが保てます - ✋ 手を握る、背中をさするなど触れ合う
スキンシップは何よりの安心材料になります - 🎵 歌をうたいながらトントン。数を数えたり気をそらす声かけ
「いーち、にーい…あとちょっとで終わるね」とリズムをつけるのも◎
そして、何よりも「大丈夫だよ、終わったらぎゅーしようね」と、
安心できる約束や、終わったあとの楽しみを伝えてあげるのも効果的です。
👶 乳児の処置には「しょ糖」で痛みを和らげる工夫も
乳児の処置の際に「しょ糖(甘い液体)」を口に含ませることで、
痛みをやわらげる効果があることがわかっています。
これは医学的にも研究されていて、甘みが赤ちゃんの脳内に“快”の刺激を与えることで、
痛みの感覚がやわらぐと考えられています。
たとえば処置の直前に、スプーンやスポイトでほんの少し甘い液体
(しょ糖水)を赤ちゃんのお口に含ませると、
- 泣きが少なくなる
- 処置後の落ち着きが早くなる
という報告があります。
3.おわりに
もし病院でプレパレーションがない場合でも、
遠慮なく親がやってあげたいことを、相談してみてもいいかもしれません。
母乳を飲ませながら処置を受ける「授乳中プレパレーション」という方法もあるそうです。
処置はどうしても子どもにとって怖い時間かもしれません。
私もまだまだ手探りですが、付き添うときも、そうじゃないときも、
「ずっとそばにいるよ。」「一緒にがんばろう」と伝え
自分ができる行動をしながら、
これからも娘とともに治療を続けていきます。
★この記事が参考になったらクリックお願いします。応援していただけると嬉しいです
にほんブログ村
★こちらもご覧ください★

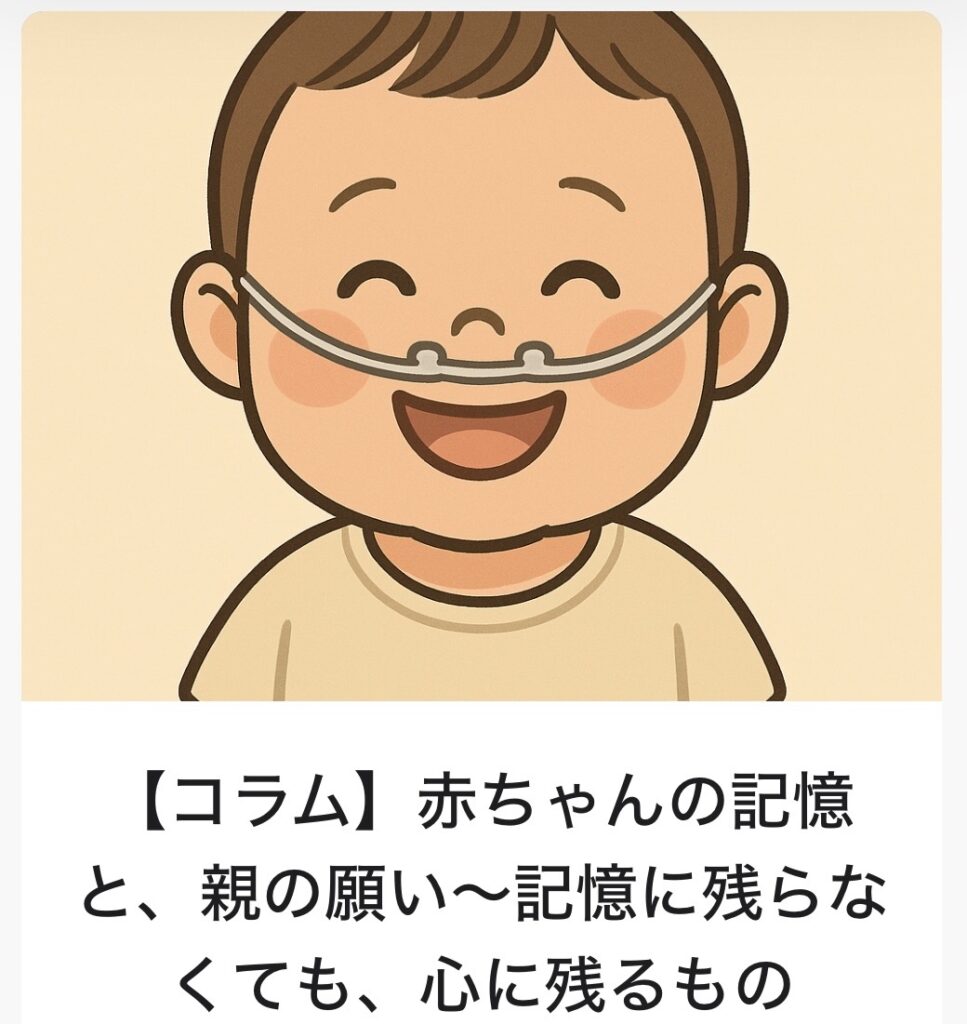
No responses yet