【コラム】「昔は当たり前だったのに…」変わりゆく病院のサービス事情5選
時代とともに、病院のあり方や入院中のサービスも少しずつ変わってきました。
「えっ、これって自分でやるの?」と驚いたり、
「昔はこうだったのにな」と感じることも。
今回は、私が実際に入院して驚いた、
昔と今の病院の違いを5つご紹介します。
みなさんの病院ではどうですか?
目次
1)お箸やお茶は自分で用意
私が2020年頃に働いていた病院では、
給食時にお箸・スプーン・フォーク、お茶も提供されていました。
ところが、昨年産科に入院した際には、
どれも用意されておらずびっくり!

「自分で準備するの?なんだかちょっと寂しいな…」
と感じたのを覚えています。
またちょうどその頃、「牛乳パックのストロー」が廃止に。
「コップに移すか、直接飲んでください」
という貼り紙がされていました。
■廃止された背景にはこんな理由が…
- 安全面:異物混入のリスク(虫・ホコリなど)
※2020年前後(新型コロナウイルス流行時期)以降はお茶に蓋をつける対策が広がりました。 - 衛生面:長時間放置による細菌の繁殖リスク
- コスト削減:物価高騰により、食器・ストローなど備品、洗浄費用の見直し
- 職員の業務軽減:配茶の準備・管理の負担軽減 など…

配茶に関しては、2010年代から少しずつ「配茶ポットの廃止」「紙パック茶の導入」といった
衛生面・コスト面・業務軽減の取り組みや見直しが始まっていたそうです。
廃止となる代わり、病院によっては以下のような工夫もされています:
- 入院セットに箸・スプーン・フォーク・コップ・飲料水を含める
- 給茶機や自動販売機の設置
- 飲料プラン(有料オプション)を導入
とはいえ、一人で用意・片付けができない患者さんもいますので、
看護師や看護助手さんに遠慮なくお願いしましょう。
2)体温・血圧は自分で測る
朝になると、「体温を測ってください」と放送が流れ、
歩ける方はナースステーション近くの自動血圧計や体重計で、
自分で測定するスタイルでした。
測定後は、その数値を看護師さんに伝え、
基準値から外れていたり、いつもと違う変化がある場合には、
看護師さんが再度測定してくれます。
3)給食は自分で取りに行く
歩ける人は配膳車まで行き、
食事を自分で受け取りに行くスタイルでした。
看護師として以前は配膳するのが当たり前だったので、
これにもびっくり!
ただ②③ともに、患者さんが主体的に医療者と関われることが
あるのはいいなと思いました。
ベッドから離れることで気分転換にもなりますし、
私が看護師として働いている時に
患者さんはよく「忙しそうだから何か協力したい」
「自分でできるのに」と言ってくださる方もいました。
また、入院中はストレスや環境の変化でせん妄が起こりやすく
「これは何ご飯?朝ごはん?」と戸惑う高齢者の方もいます。
病棟生活に参加することで、記憶にも残りやすく、
いい取り組みだと思いました。
もちろん、配膳間違いや、
転倒リスクがある方はほかの患者さんとの接触や事故も
起こりうるため注意が必要です。
4)名札は「名字のみ」
最近では、医療スタッフの名札にフルネームではなく
「名字のみ」を表示する病院が増えてきました。
これは、個人情報保護の観点からの配慮です。
スタッフだけでなく、患者さん自身も、特別な事情があれば
「仮名」や「イニシャル(Aさんなど)」を使うことも可能です。
また、病室前のネームプレートに名前を表示しないという対応も、
病院によっては選べます。
名前を知られたくない理由は人それぞれ。
一人ひとりの気持ちや事情に寄り添える仕組みが、
少しずつ広がっていると感じます
5)電話でフルネームは名乗らない
私が働いていた病院では、
以前は電話がかかってきたら
「〇〇病院、看護師の〇〇です」と言っていました。
しかし、いたずら電話が増えたことから、
今は「〇〇病院、看護師です」となりました。
背景にある「病院をとりまく現状」
こうした変化の背景には、
病院を取り巻く厳しい現実もあります。
● 経営の厳しさ
- コロナ以降、外来・入院数が減少
(2025年時点でも、コロナ前の水準には戻っていません。) - 薬価マイナス改定
(国の医療費抑制策として、薬の公定価格が引き下げられ、
病院・薬局の収益は圧迫されています) - 特に中小病院では赤字や閉院も増加
(患者数の減少とコスト増加のダブルパンチで、
閉院や縮小を余儀なくされる例が増えています。) - 物価・光熱費・人件費の上昇が直撃
● 医師・看護師の人手不足
- 長時間労働、夜勤・オンコールの負担増
- 特に地方は深刻
- 医療スタッフの離職率も高く、現場は疲弊
- 働き方改革
(2024年度から医師にも労働時間の上限が設けられました)
● カスタマーハラスメント(カスハラ)問題
- 無理な要求や暴言、SNS拡散への不安
- 職員が「言い返せない」立場につけ込むケースも
● ICT導入のプレッシャー
- 電子カルテやAI化が進む一方、習熟の負担も
- デジタル化しても、「人の手によるケア」は必要不可欠
● 患者ニーズの変化
- 病院を“サービス業”と捉える声も増加
- 丁寧な接遇や対応が求められる時代に
- SNSで口コミが広がる
おわりに
私は以前4人部屋に入院したことがあります。
その際、歩けない同室の患者さんに「私がご飯持ってきてあげるよ!」
と隣のベッドの患者さんが声をかけていました。

医療者の立場としては、
他の患者さんの食事を看護師に知らせずに配膳するのは、
実は危険な場合もあります。
たとえば、食前に血糖測定やインスリンの投与が必要な人もいます。
検査のために「今は食事を待ってください」と言われている可能性などもあります。
それでも、あの温かい気遣いや声掛けは、
素敵だなと心が温まりました。
医療の現場は、時代とともに効率化・システム化が進んでいます。
でも、病院には日々、
さまざまな事情を抱えた方がいます。
だからこそ、周囲の人の
ちょっとした気づきや手助け、
優しい言葉の一つ一つが、本当に大切だと感じます。
近年では、患者さんと医療者が「対等な関係」
で向き合う時代になってきました。
それぞれの立場には、それぞれの背景や思いがあります。
時には「カスハラ(カスタマーハラスメント)」という言葉が聞かれることもありますが、
決して対立ではなく、
協力し合い、分かり合える関係性を。ーー
それが、これからの医療現場にますます求められていくのではないかと
感じています。
時折、お茶や箸の持参がないからと、
飲水を控えたり、給食を手で食べようとする患者さんもいるそうです。
コロナ禍をきっかけに、
人と距離をとることが当たり前となり、
パーソナルスペースを大切にする風潮が強まりました。
そんな現代では、
「他者との関わりをためらってしまう」こともあるかもしれません。
けれど、助けを求めている人はすぐ近くにいて、
あなたの小さなサポ―トが、
誰かにとっては非常に大きな支えになることもあるのです。
★この記事が参考になったらクリックお願いします。応援していただけると嬉しいです
にほんブログ村
★こちらもご覧ください★

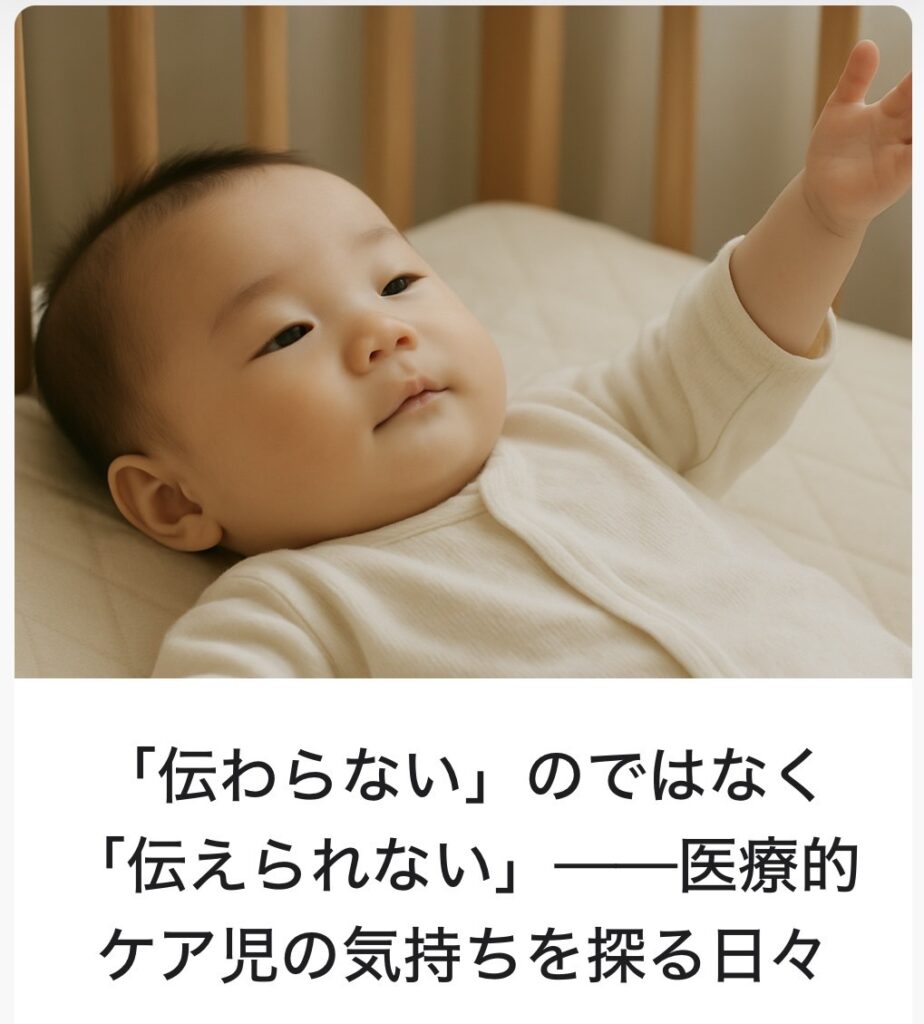
No responses yet