このブログを読んでくださっている方の中には、
医療的ケア児を妊娠中の方、お子さんがNICU・小児科で頑張っている方、在宅の準備をされている方、
すでにご自宅で医療的ケアを行いながら育児をされている方、
医療や福祉に携わる方、ご家族やきょうだい、親族、そして支援に関心のある方——
さまざまな立場の方がいらっしゃると思います。
医療的ケア児と生きていく中で、私は何度も葛藤や不安に襲われました。
けれど、同じ医療的ケア児のご家族や娘をサポートしてくれる方々からのアドバイス、
毎日の小さな工夫、試行錯誤が、私たちらしい生き方の支えになっています。
「医療的ケア児だから無理かも」と言われることもありますが、
私たちは、少しずつ**“わが家らしい暮らし”**を築いています。
このサイトでは、そんな葛藤や不安と向き合いながら、
自分たちの暮らしを模索するためのヒントと工夫をまとめています。
目次
1.このブログについて
どんな人が書いているの?
医療的ケアが必要な娘と夫と暮らしている、元看護師の30代前半ママです。
現在は会社員として働いていますが(育休中)、娘の妊娠・出産をきっかけに、
再び医療と“初めての育児”に向き合う日々が始まりました。

看護師として働いていたため、医療は身近なものでした。
でも、まさか自分の子どもが医療を必要とするとは思わず、
正直ショックを受けました。
医療的ケアも落ち着いてできると思っていたのに、
「親」として向き合ったときは、今でも戸惑いや不安の連続です。
元看護師の私ですら毎日バタバタしているのに、
医療に初めて触れるご家族が処置を身につけながら育児をしている姿には、
心から尊敬の気持ちが湧いてきます。
このブログでは、
看護師としての視点と、
ひとりの母親としての視点を行き来しながら、
多くの人との出会いと日々の経験を通じて、
医療的ケア児とともに歩む中で、辛い経験は避けられません。
それでも、どんな人でも夢や希望をあきらめず、少しずつ心穏やかに、
**“わが家らしい暮らし”**に近づいていけますよう、心から願っています。
ブログを始めた想い
娘の妊娠・出産、NICU、退院後の在宅生活。
突然の病状悪化により繰り返す入退院。――
私は何度も困難に出会い、戸惑い、悩み、立ち止まりました。
大きな壁を前に、もう乗り越えられないと諦めそうになったこともあります。
看護師として、子どもの病状を予測できるからこそ、
「もう終わりが見えているのかも…」という怖さを抱くこともありました。また、初めての慣れないケアや育児で、余裕のない日々。
それでも、小さなぬくもりに触れるたび、
**「この子を産んでよかった。私たちでこの子を守るんだ!」**と思うようになりました
前向きな思いもある一方で、
ネット上では必要な情報がなかなか見つからず、
同じ立場の声も届かず、孤独を感じることが多々ありました。
前向きな言葉をもらっても素直に受け取れず、
ときには無神経な一言に深く傷つくこともありました。
そんな時、“医療的ケアの先輩”たちが手を差し伸べてくれました。
- 同じ立場だからこそ分かり合える不安や小さな喜びと工夫
- 専門職だからこそ伝えられる核心をついたアドバイス
ネガティブな思いから抜け出し、
**「こうありたい私たちの暮らし」**を思い描きながら、
日々の中で小さな希望の芽を育てることができました。
子どもの病状、経済的な不安、仕事の両立、きょうだいのこと…。
きっと、みなさんにもそれぞれの悩みがあると思います。
だからこそ――
「つらかったとき、励ましてもらった私が、今度は誰かの力になれたら」
「教えてもらった工夫や経験を、次へつなぎたい」
そんな想いから、このブログをはじめました
2.医療的ケア児とは?
医療的ケア児ってどんな子?
医療的ケア児とは、日常的に医療的なサポートが必要な子どもたちのことを指します。
たとえば、こんなケアがあります。
・人工呼吸器の管理
・気管切開
・経管栄養(胃ろう・鼻チューブ)
・インスリン注射 など
病名や背景、状態は一人ひとり異なります。
・元気に歩いたり走ったりできる子もいれば
・誰かの手を借りて姿勢を保つ子もいます。
2021年の厚生労働省の調査によると、
全国に約2万人以上の医療的ケア児がいるとされています。
でも、在宅で生活している家庭が多いため、
普段の暮らしの中で出会うことは少ないかもしれません。
私も当初は、「この地域に、医療的ケア児はあまりいないのかな」と思っていました。
しかし、病院でたくさんのご家族に出会い、
それぞれが悩みや希望を抱えながら日々を乗り越えていることを知り、
とても励まされました。
特にNICUで隣のベッドだったご家族と、外来で再会したとき。
お互い”親・子ども”としての成長を喜び合い、
あの日の不安な気持ちが「今ここまできたんだね」という喜びに変わった瞬間でした。
このブログでは、目には見えないけどみんな頑張っている。
「辛いのは私たちだけではない。家族で、みんなで、がんばろう」
そう思ったあの日の気持ちを大切に、
医療的ケア児とともに生きる毎日のことを、少しずつ綴っていきたいと思います。
わが子との出会いから現在
◇はじまりは、ひとつのエコー検査から
私は、ずっと順調な妊婦健診を受けていました。
けれどある日、エコーで
「赤ちゃんの右の腎臓に嚢胞があるかもしれません」
と伝えられ、大学病院での精密検査をすすめられました。
そこで言われたのは、衝撃的なひと言。
「赤ちゃんの大きさが、100人いたら3番目に小さいくらいです」
体が小さいと、お腹の中で急に命を落とすこともあるそうで、
そのまま管理入院が決まりました。
・赤ちゃんの状態によっては、緊急帝王切開になる可能性もある
・モニターで様子を見ながらの入院生活になる
そう説明を受け、私は妊娠30週で大学病院に入院することに。
でも当時の私たち夫婦にはまだ実感がなく、
「先生、ちょっと大袈裟すぎない?」
とさえ思っていたのです。
◇18トリソミーとの診断、そして出産へ
妊娠33週で羊水検査を行い、娘は18トリソミーと診断されました。
「生まれても、生きられるかわからない」——
妊娠中、私はその現実を受け止めきれず、毎日胎動があるかを確認しながら、
不安と悲しみで涙する日々を過ごしていました。そんな私のそばに、夫はいつもいてくれました。
心のどこかで、「もしかして診断は間違いなのでは」と思いながら迎えた出産。
大きな産声を上げて生まれた娘の姿を見て、
私は「かわいい!!本当に18トリソミーなの!?」と疑問に思いながら
抱きしめました。
◇“かわいい”と抱きしめた瞬間から、現実との向き合いが始まった
抱きしめた後、泣き声が聞こえなくなり、
SPO2(酸素飽和度)のアラーム音が鳴り響きました。
点滴や呼吸器、モニターが次々と装着され、
医師や看護師たちが慌ただしく動く姿に、
「やはり18トリソミーなのだ」という現実を、
強く実感することになりました。
NICUに入った娘の状態は良くなったり悪くなったり。
母子同室の方と赤ちゃんの姿を見るたびに涙が止まらず、
看護師さんや助産師さんにたくさん話を聞いてもらいました。
感情の波に揺られながら、私だけ先に退院して、
その後は毎日昼と夜の2回、面会に通いました。
医師は「できる限り良い状態のうちに、おうちで思い出を作りましょう」
と早期退院を勧めてくれました。
不安と希望を抱きながら、1か月の入院を経て、
私たちは自宅での生活を始めることになったのです。
◇在宅での暮らしと、支えてくれる人たち
NICUを退院し、現在は在宅での生活を送っています。
大学病院への通院は月に1〜2回、
多いときには月4回にのぼることもあります。
また、状態が急に変化することもあり、
1〜2か月に1回は入院することもあります。
娘の病状は日々変化しますが、安全に在宅生活が送れるよう、
たくさんの方々に支えていただいています。
それぞれがわが家に足を運び、
娘の暮らしを支えてくれる大切な存在です。
◇現在の医療的ケアについて
娘に必要な医療的ケアは多岐にわたります。
そして症状によって、日々必要なケアは異なります。
- 腹部ケア(浣腸・導気)
- 呼吸管理(経鼻酸素・人工呼吸器:トリロジーエボ・吸入・吸引)
- 栄養管理(経管栄養を口から入れています)
それぞれのケアは、最初はとても不安でした。
健康な子どもと比べてしまい、
「かわいそう」「どうして私の娘が…」「娘は生まれたことを幸せに思っているのだろうか」と、
やるせない気持ちになることもありました。
「腹部ケアをしてもお腹が張っている」
「呼吸器をつけるのを嫌がる」など、うまくいかないことも多く、
日々試行錯誤の連続です。
そんなときは、医療スタッフや、同じ悩みを経験をしたご家族の
“医療的ケアの先輩”に相談しています。
少しずつ、私たちなりのやり方を見つけていきました。
chatgptやネットでも日々情報収集をしています。
気づけば、医療的ケアは“辛い・かわいそうなこと”ではなく、
娘が少しでも心地よく生きるための「大切な役割」になっていきました。
3.読者の皆様へのお願い
◆あくまで個人の経験に基づく内容です
◆誤りや情報の古さが含まれる可能性もあります
◆制度には地域差があるため、専門職の方とご相談ください
◆ご家庭やお子さんの状況によっては、当てはまらない場合もあります
※このブログに書かれている内容は、個人の経験に基づいています。
できるだけ正確な情報を心がけていますが、誤りや情報の古さが含まれる可能性もあります。
ご理解のほどお願いいたします。
制度や支援には地域差があり、また、お子さんの状態やご家庭の状況によっては、
合わない場合もあるかもしれません。
医療機関や専門職の方とご相談のうえご判断ください。
どうか「ひとつの体験談」として、無理のない範囲で参考にしていただけたら嬉しいです。
4.おわりに
医療的ケア児との生活は、
「我慢ばかり」「制限の多い生活」——
そんなイメージがありますが、
今できることを見つけ、小さな夢や“やってみたい”を叶えられるように。
私たちらしく、日々を重ねながら、少しずつ前に進んでいきたいと思います。
「わが子と過ごす毎日を、大切に生きる」という意味では、他のご家庭となんら変わらないのかもしれません。
この記事が参考になったらクリックお願いします。応援していただけると嬉しいです。
にほんブログ村
★わたしの家族のインタビューはこちら★

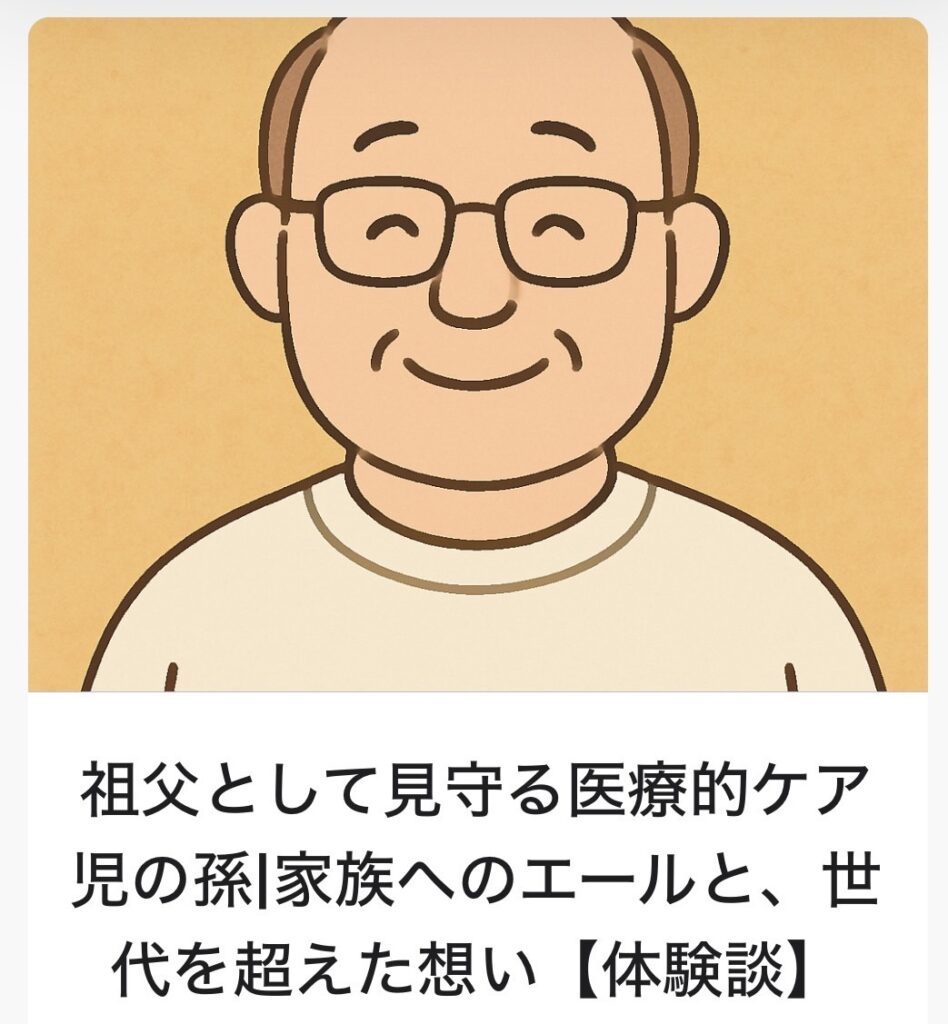
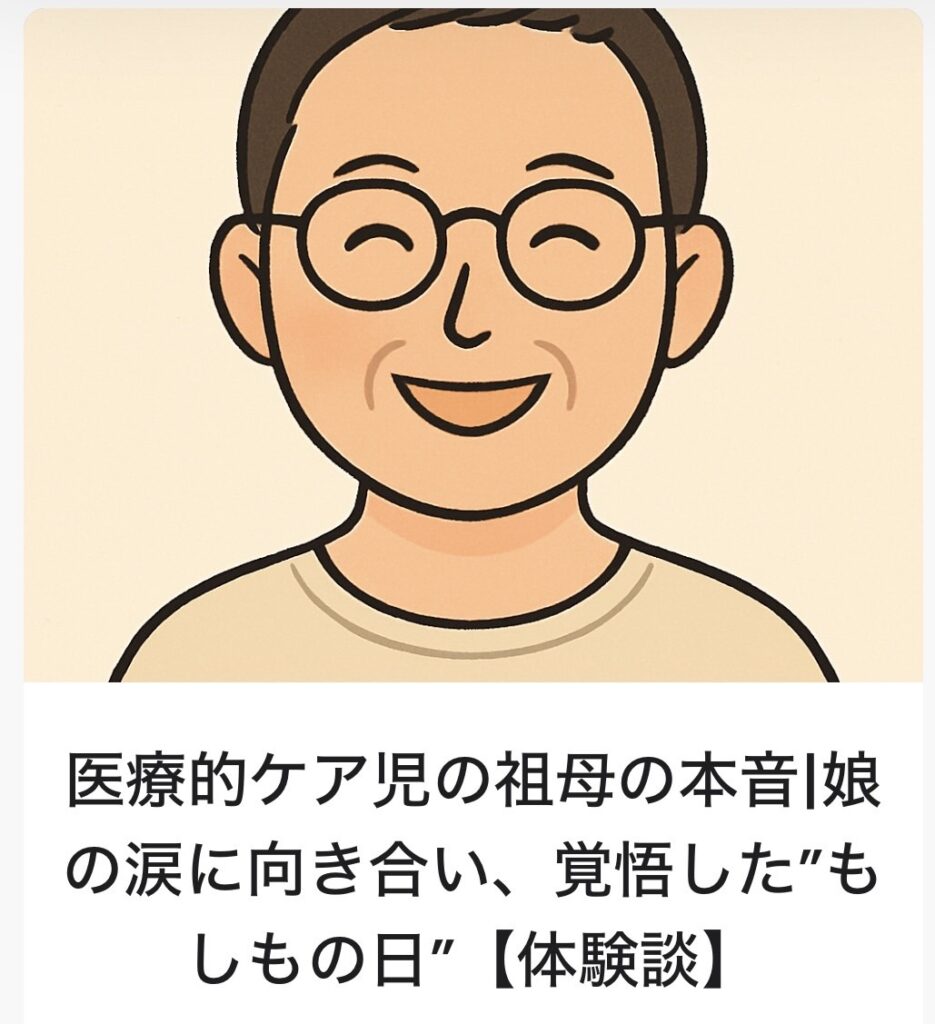

No responses yet