以前、あるSNSでこんな投稿を見かけました。

「訪問看護師が家の中をじろじろ見て嫌だった」
この投稿に対して、看護師と名乗る方がこう返していました。

「利用者の家や生活状況を知ることは、
看護師にとって大切なポイントです。」
たしかに、それも一理あります。
生活の中にあるリスクや、支援のヒントを見つけることは、訪問看護の大切な視点です。
たとえば、安全面の確認のため💡

地震のときに赤ちゃんのそばにタンスが倒れてこないか、
熱いお湯の入ったポットは手の届く場所にないか、
ハサミや刃物などの危険物が近くに置かれていないか…など
また、お掃除の状況から心の余裕や忙しさを確認するため💡

部屋が乱雑だったりゴミがたまっているような場合は、
「今はご両親がとても疲れているのかな」
「生活がまわらないほど大変な状況なのかも」と感じることもあります。
随時、必要なサービスも案内します。
逆に、乱雑な環境が整うようになってきたら
「生活リズムが整ってきたのかもしれない」
「今は穏やかに過ごせているのかな」と、少し安心することもあります。
そのほかにも、「きれい好きなご家族だな」「こういうところはこだわりがあるのかな」とご家庭の雰囲気を感じ取ったり、「ここに酸素を配置したらケアもスムーズになるんじゃないかな」など、アドバイスにつながることがあります。

しかし、だからといって「じろじろ見る」ことはよくありませんし、
利用者さんを不快にさせるような行動は、
どんな理由があっても避けるべきです。
実際、医療的ケア児を育てている友人たちに聞いてみると、
「訪問看護師さんとすれ違うことはある」「合わないと感じたことがある」と多くの声がありました。私自身もそうでした。
今回は、訪問看護師と合わなかった私の経験も交えながら、「訪問看護師の苦悩」に触れつつ対応策について考えたいと思います。
目次
私は訪問看護師さんと合わなくて事業所を変えた
現在、我が家では2つ目の訪問看護ステーションを利用しています。
最初に紹介されたのは、NICUに入院していたころ、
退院支援の担当者が「小児もたくさん診ているから安心」とすすめてくれたところでした。

大学病院の看護師さんのように知識が豊富で沢山のアドバイスをいただけると
期待していました。
でも、実際には私の子どもと同じ病気の子を診たことがないと言われ、
病状についての質問にも答えてもらえず…。
どちらかというと“介護”や“ケア”に特化している印象でした。
我が家では、沐浴や日々のケアは夫婦で行っていたので、
お願いしたいのは「病状の観察」でした。
退院したばかりで未熟児ということもあり、
少しの変化にも早く気づけるようにと思って依頼したのです。
でも実際の訪問では、私との雑談が中心で、
期待していた内容とは違いました。
そのため、申し訳ない思いはありましたが、契約を解除して
自分で評判を調べた次のステーションと契約しました。
新しい事業所でも、すれ違いはある
2つ目の訪問看護師さんは、子どもに絵本を読んだり、
歌をうたったり、明るい雰囲気で接してくれる方でした。
でも、病状の変化をしっかり見てくれているかというと、少し不安がありました。
あるとき、思い切って「もっと病状のことをみてほしい」
と伝えてみたんです。すると、それ以降は、
「今日はいつもより呼吸が楽そうですね!」
と、声に出して状態を伝えてくれるようになりました。
誠実に対応してくださり、信頼関係も深まっていきました。勇気をもって伝えてよかったと思います。
訪問看護師さんの抱える苦悩
訪問看護師さんは、ただケアを届けるだけでなく、
「その人・家族の暮らし」の中で、寄り添いながら看護をする必要があります。
特に小児・医療的ケア児の在宅支援では、
専門性と柔軟性、そして家族とも深い関係性が求められます。
けれど、その現場には、
外からはなかなか見えない苦労やプレッシャーもたくさんあるのです。
■ 幅広い年齢と疾患
0歳の赤ちゃんから18歳の思春期まで、子どもたちはそれぞれ違うリズムで生きています。
赤ちゃん、児童発達支援に行っている子、学校に通っている子――
本当に様々です。
バイタルサインや発達、ライフスタイルも一人一人違い、好きなこと、嫌いなこと。
症状の現れ方や対応方法もそれぞれです。
■家庭ごとのケアを覚える必要がある
医療的ケア児の場合、同じ病名でも必要なケアはひとりひとり異なります。また、
- 吸引や呼吸器の設定
- 胃ろうの管理や注入時間
- 胃管の入れ方、テープ固定の方法など、
家族が普段ケアをしている方法を理解し実施する力が求められます。
また、物品の洗浄方法や洗う場所(洗面台・キッチン)、洗うタイミングも
家庭によって異なるため、覚える必要があります。

おむつやおしり拭き、ガーゼなど家族が購入しているものを
訪問看護師さんは使用するため
”無駄遣い”がないように注意してケアをしているそうです。
■ 専門性と広範な知識へのプレッシャー
早期退院が進むなかで、訪問看護師は急性期後の医療にも対応しなければならないことが増えています。
呼吸器管理、けいれん時の対応、経管栄養、皮膚トラブル…。
専門的かつ幅広い知識が求められます。
ですが、職場によっては教育体制が不十分で、
「学ぶ時間がない」「相談できる人がいない」と悩む方もいます。
また、一人で訪問する場合は、緊急性を判断する責任や相談できない孤独感を抱く場合もあります。
■身体的負担
特に一人での訪問の場合、介助や処置が多いと身体的な負担が大きくなります。
時間に追われながらのケアや、次の訪問先に急ぐ移動も、体力的にも精神的にもストレスになります。
■ 時間の制限
訪問看護には“訪問時間”という制約があります。
1件にかけられる時間は決まっていて、遅れると次の訪問に影響が出ます。

「今すぐに来てほしい」と言われても、人手や交通、天候などの影響で厳しい場合があります。
また、ご家族にとっては「もっと話したい」「もっと丁寧に見てほしい」という気持ちがあり、「時間なので失礼します」と言うのは心苦しい場面もあります。
時間にしばられながらも、関係をこわさないように気を配る──そんな繊細なバランスが、訪問看護には求められています。
■ 多職種との情報共有の難しさ
病状の変化や処置の確認など、主治医との連携は重要ですが、実際には電話のみの対応になることも多く、医師と十分にコミュニケーションが取れない現実があります。
- 手術や緊急対応などで返答がすぐ返ってこない
- 情報がうまく伝わらない
こうしたコミュニケーションの難しさが、判断を迷わせたり、ストレスにつながったりすることもあります。

また、訪問看護師がしばしば感じるのが、
「病院と同じケアをしてほしい」という家族の期待とギャップです。
「病院はこうしてくれていた」と言われても、在宅では物品や時間、人手など限りがあります。
また、病院のときとケアの状況が変わっていることがあり、
比べられてしまうプレッシャーは大きく、
病院から訪問看護師に十分な情報提供がされていないこともあります。
■ 生活環境に適応する大変さ
- 家の中が寒すぎる/暑すぎる
- ケアをする場所が狭く姿勢が苦しい
- 家族が疲れ果てていて、対応が難しい
こうした“家の中の困難”にも寄り添いながら、
「その人らしい暮らし」を支えるのが訪問看護師の役割です。

病院とは違い、おうちにある物品を使ってケアをするので
試行錯誤が必要になります。
また、病院だと看護師ができる検査も家ではできません。限られた環境で看護を行う大変さ
があります。
■ 看護以外の大変さ
ケアだけでなく、書類業務、記録、スケジュール調整、他職種との連携…と、
看護業務以外の負担も決して小さくありません。
それに加えて、24時間対応をしている訪問看護ステーションの看護師さんは急な呼び出しもあり、
家庭との両立にも悩む方が多く、
子育て中の看護師さんは特に、送迎や家事とのバランスに苦労しています。
■ 訪問そのものが拒否されることもある
また、患者さんやご家族の精神状態が不安定なときには、訪問看護そのものを拒否されることもあります。
- 「今日は来ないでほしい」
- 「もう見られたくない」
- 「他人に入ってこられるのがつらい」
そんなふうに言われてしまうと、看護師側もどうすべきか悩みます。
無理に入ることはできない。でも、支援を途絶えさせることもできない。

特に、医療的ケア児を育てている家庭では、
子どもも親も精神的な余裕が日によって大きく揺れることもあり、
「昨日は平気だったのに、今日は無理」という状況も少なくありません。
訪問看護師さんは、そうした“こころの揺れ”にも寄り添い「どうして拒否したのか」考えながら、慎重に、丁寧に関わっています。
■治療や状態への考え・価値観の違い
訪問看護の現場では、ときに家族と看護師、
他の医療職種との間で価値観や考えの違いが浮き彫りになることがあります。
◎家族と看護師間では、たとえば
子どもの体調が悪化したとき、
看護師としては「安全のために、入院して管理した方がいい」と考えることがあります。
けれど、家族は「できるかぎり家で過ごしたい」と希望する場合があります。
家族にとっては「自宅での生活の思い」があるからこそ、医療的な判断とぶつかることがあります。
◎看護師と他の医療職種との間では、たとえば
患者さんが苦しんでいることを報告しても、医師から「とりあえず様子を見よう」と言われたり、
眠気の副作用が強くでることを気にして、医師が痛み止めを増やしてくれない、など…
沢山の職種が関り、みんな”子どものため”を思っているため、支援の方向性がまとまらないことがあります。
大切なこと──“伝えること”と“わかろうとすること”
訪問看護師さんが抱える苦労は、身体・環境的なものだけでなく、人との関係性や、価値観の違いから生まれるものもとても多いと感じます。
沢山の人が関わっているため、情報共有や支援の方向性がまとまっていないと、訪問看護師さんにも葛藤がうまれます。
そしてそれは、私たち家族も同じです。子どもも親も、毎日必死で生活しています。

また、看護師さんに悪気があるわけではありませんが、
家族の希望と違う関わり方だと、訪問そのものがストレスになってしまうこともあるのです。
一方で、看護師さんもスケジュールを組んで、一日に何件も訪問をこなしています。すべての家庭の希望通りに動くことが難しい現実も、よくわかります。
⸻
だからこそ、大切なのは、
“お互いに気持ちを伝えること”、そして“わかり合おうとすること”。
「私たち家族はできるだけ、病院じゃなくて家で過ごしたい」
「この時間に来てもらえるのは嬉しいけど、もう少し遅い方が助かるかも…」
そんなふうに、少しずつでも言葉にしていくことが、信頼関係の第一歩になるはずです。
⸻
それでも、どうしてもストレスに感じることが続くなら──
無理をする必要はありません。
訪問看護ステーションの中で担当を変えてもらうこともできますし、
ステーション自体を変更したり、複数契約をして“自分たちに合う人”を見つけるのも一つの方法です。
「誰かと相性が合わないこと」は、決して悪いことではありません。
少しずつ、「この人とならやっていけそう」と思える関係性を見つけていけたら──
それが、子どもにとっても家族にとっても、一番の安心につながるのではないでしょうか。
おわりに──その訪問の裏側では
訪問看護師をしている友人が、ある冬の日にこんな話をしてくれました。
「雪の日は、まず家の前を雪かきしてからじゃないと車を停められなくて…。でも、訪問時間に遅れないようにって必死なんだよね」
「それでも、病院じゃなくて家で自由に過ごしているのを見ると、やっぱりこの仕事はやりがいがあるなって思う」
この言葉が、ずっと心に残っています。
訪問看護は、様々な困難さがあるお仕事ですが、それでも、
目の前にいる子どもやご家族の“いつもの暮らし”を守るために、時間通り、力強く関わってくれます。
ときにすれ違うこともある。遠慮もある。
理解し合えず、もどかしい気持ちになることもある。

でも、だからこそ、
「この看護師さんと一緒に歩んでいきたい」と思える関係性を少しずつ築いていけたら──
それは、子どもにとっても、家族にとっても、かけがえのない支えになるのだと思います。
★この記事が参考になったらクリックお願いします。応援していただけると嬉しいです
にほんブログ村
★こちらもご覧ください★

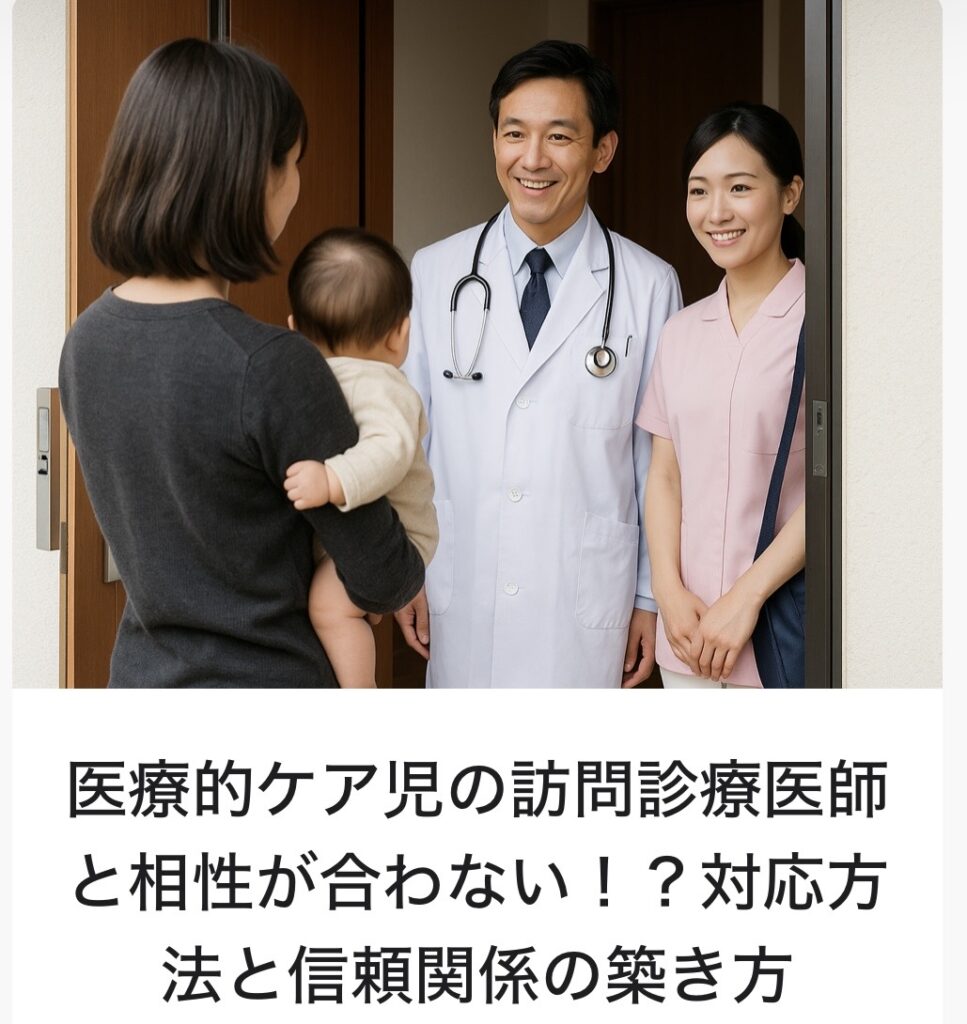
No responses yet