もうすぐお盆。あなたの大切な人は、どこで旅立たれましたか?
目次

お盆とは、亡くなったご先祖様の霊が、あの世からこの世に帰ってくるとされる期間に、家族でお迎えし、おもてなしをする日本の風習です。
地域によっては**7月盆(7月13〜16日)**のところもありますが、ほとんどの地域では**8月盆(8月13〜16日)**が主流です。
| 日付 | 一般的な行事内容 |
|---|---|
| 8月13日 | 迎え盆(ご先祖様をお迎えする) |
| 8月14日〜15日 | お盆の本番(法要やお墓参りなど) |
| 8月16日 | 送り盆(ご先祖様をお見送りする) |
| 行事 | 内容 |
|---|---|
| 迎え火(むかえび) | 8月13日ごろ、玄関先などで火を焚いてご先祖様をお迎えする |
| お墓参り | 墓石をきれいに掃除して、お花やお線香を供える |
| 仏壇のお供え | 精進料理(肉や魚を使わない料理)、果物などを供える |
| 盆踊り | 地域の祭り。ご先祖様の供養と、みんなの健康を願って踊る |
| 送り火(おくりび) | 8月16日ごろ、再び火を焚いて、ご先祖様をあの世へお見送りする |
※地域や家庭によって異なります。
お盆は、ご先祖様を偲び、命のつながりに思いをはせる時期。
みなさまのご先祖様はどこで旅立たれましたか?病院、 施設、ご自宅など。。
今回は、看護師として私が経験してきた「ターミナルケア(終末期ケア)」について、
病院・施設・在宅それぞれの特徴や流れをご紹介します。
1.病院での看取り──安心はあるけれど、慌ただしさも
病院では、状態が悪化したときに
「どこまで治療を行うか(DNARかフルコードか)」を家族と話し合います。
★フルコードについては、こちらもご覧ください★
DNAR(蘇生措置拒否)となった場合も、痛みや不快感を抑える緩和ケアを行い、
家族とメリット・デメリットを話し合いながら、
・麻薬
・点滴
・経管栄養
・酸素投与
・排泄の管理(膀胱カテーテルなど)などの医療的ケアを状況に応じて行います。

たとえば、脱水が可哀想と思い「点滴」をいれると浮腫みとなり、呼吸や心臓に負担がかかり苦痛となる場合もあります。
また、体位変換も行うことで血圧が急に低下して亡くなることもあるため、少しの体位変換もしくは除圧(圧抜き・褥瘡予防)にとどめることがほとんどです。
1)亡くなる前の体の変化
| 時期 | 主な変化 | 具体的な様子 | おおよその時間目安 |
|---|---|---|---|
| 数日前~前日 | 食欲・水分摂取の低下 | ほとんど食べない、口を開けない | 数日〜1週間 |
| 1〜2日前 | 意識レベルの低下 | 呼びかけに反応しづらくなる、うとうとする | 1〜2日 |
| 数時間前 | チアノーゼ(血のめぐりの変化) | 手足・口唇が青紫に、冷たくなる | 数時間〜半日 |
| 数時間前〜直前 | 呼吸の変化(下記参照) | 不規則な呼吸・無呼吸の挟まり・あえぎ | 数分〜数時間 |
| 数分前 | 心拍の変化 | 脈が弱くなり、次第に消える | 数分以内 |
こちら以外にも、尿が出ない・点状出血(毛細血管が破れて皮膚の表面に小さな赤や紫の点として現れる出血斑)などがあります。

特に「呼吸の変化」は、「そろそろかもしれない」と感じる一番大きなサインと言われています。
2)特徴的な呼吸の変化(数時間〜直前)
- チェーンストークス呼吸:深くゆっくりした呼吸→だんだん浅く→止まる→また始まる
- 死前喘鳴(しぜんぜんめい):「痰がからんだような音」がのどで響く
- 無呼吸のあとの一息(あえぎ呼吸):しばらく止まっていた後、急に大きく一息

亡くなる前の数時間〜1日ほどのあいだに、
呼吸のたびに**喉元から「ゴロゴロ」「グーグー」といった音が聞こえてくる**ことがあります。
これは、「死前喘鳴(しぜんぜんめい)」と呼ばれる自然な変化のひとつです。

これは、体の力が弱くなり、
飲み込む力や痰を外に出す力がなくなってくると、
唾液や分泌物がのどにたまってしまいます。
呼吸のたびにそれが振動して、**「のどの奥で音が鳴る」**という状態になります。また、点滴の量が多く、痰が増えている場合は、点滴の量を医師が減らしたりもします。

このゴロゴロ音を聞くと、ご家族は驚いて
「苦しそうだからどうにかしてあげて。吸引したら?」
と思われるかもしれません。
でも実は──
吸引をしても根本的に音はなくならないことが多く、
むしろ、
- 吸引の刺激で苦しさが増す
- 呼吸が乱れる
- 最後の時間を静かに過ごせなくなる
などの理由で、あえて吸引をしないという選択をすることがあります。
見ている家族にとってはつらい音に聞こえるかもしれませんが、
本人はすでに意識がほとんどない状態(聴覚は保たれていると言われています)で、不快を感じていないことも多いです。
吸引をすることで死期をはやめることもあります。
3)死期が迫っている徴候があったときの看護師の対応
基本的に、
・個室に移動していただく場合が多いです。
・面会時間も延長したり柔軟に対応してくれる場合があります。
・「最期を一緒に過ごしたいか」「一緒にいなくても大丈夫か」を確認します。
そして、呼吸の変化や皮膚の色などから、最期が近いと感じたときにはご家族に電話します。
◇最期を一緒に過ごしたい場合
緊急連絡先①(キーパーソン)に連絡するので、その方が他の親族に連絡をしていただきます。
病室に来ていただき、一緒に時間を過ごします。
医師と看護師が来て、「辛くなさそうですね。安らかに過ごされていますが、ご家族はどう感じますか?何かしたいことはありますか?」とお話しします。呼吸が止まり、心音が消えると、看護師が医師に報告し、死亡時刻を記録して黙祷を行います。
◇最期を一緒に過ごさなくてもいい場合
「次は亡くなってから電話をください」
「苦しむ姿は見たくない」
「小さな子どもがいるので夜間の連絡は避けてほしい」など人それぞれです。

「夜中の場合はすぐお電話したほうがいいですか?朝にしますか?」
「死亡診断に立ち会いたいですか?」
と事前に確認もします。
4)死後の対応・エンゼルケア(死後のケア)
亡くなった後、医師や看護師と「患者さんの思い出」や「振り返り」を行います。

「いつもは〇〇さんは、部屋をきれいに掃除していて、他の患者さんとも仲良しでしたね。」
「いつも家族のことを大切に思われていましたよ」「辛そうな表情もなく、最期は安らかに眠るように過ごされましたよ」などお話しします。
その後、
・ご家族様から葬儀業者に連絡していただきます。
・看護師がエンゼルケアを行います。
- 医療物品を外し、清拭・陰部洗浄・保湿(とくに保湿はとっても大事です)
- 髭剃りや口腔ケア
- 好きな服に着替える
最近は、エンゼルメイクや綿球処置(綿詰め)は行わないことが増えています。
- 綿球は顔つきが変わるため、行わないほうが自然
- 身体から漏液があったときに行う(おむつで対応することも)
- メイクは好みや表情の違いもあり、希望がなければ施さないことが多い
- メイクや整えは**おくりびと(納棺師)**が対応する場合もあるため

エンゼルメイクのファンデーションや口紅など、昔は市販のものを複数人に使用することが多かったですが、
現在はエンゼルメイク用で保湿成分が入っていたり、個包装になっていたりと、衛生面でも配慮されています。
👐「こうしなきゃいけない」はない時代に
- 手を無理に胸で組む・目や口を無理に閉じさせなくても自然にOK
- 浴衣の合わせも「左前」でなく、好きな服・自然な着方でOK
- 入れ歯は入れることで自然な輪郭に
- 基本的にペースメーカーは外さないで火葬業者さんに伝達のみでいいことも
5)病院でのお別れは、想像以上に“急かされる”ことも
- 霊安室の空き時間や医師の都合でバタバタする
- 「葬儀社は何時に来ますか?」と何度も聞かれる
- 家族が混乱している中で次々とお会計のことなど説明されることも
病院での看取りは、安心感と引き換えに、慌ただしさが残ることもあるのです。
2.施設での看取り──穏やかな時間のなかで

施設によっては、最期まで過ごせるところもあります(お看取り可能)。
1)デメリット
- 医療行為に制限がある
- スタッフと信頼関係が築けていないと不安を感じる
- 医師が不在の時間もあるため、医師とは電話での対応になるときも
- 時間でケアが決まっているため、ご家族が自由に主体的にケアに関われないということがあります。
2)メリット
- 病院よりもゆったりとした時間
- 24時間面会可能な施設も
- 長い間関わったスタッフに見送られながら過ごす時間
- 個室や家族の泊まり込みが可能な施設もあり、焦らずお別れができる

ご家族がつきそっている場合は、「家族の時間」を大切にします。面会が来るときはケアの時間を家族と相談して柔軟に対応します。
また、ご家族がつきそっていない場合は、
・職員が病院よりも頻繁に様子を見に来て、
・のんびりした時間を一緒に過ごす
・話しかける
・レク
・リハビリ
・マッサージ
・寄り添ってくれる
ところが施設のいいところだと思います。
3.在宅での看取り──“自分たちらしさ”を大切にできる場所

- 住み慣れた場所で、家族と過ごしながら自分たちらしい最期を迎える
- 食事、会話、テレビ、昔話……日常の中で、穏やかに
- 訪問看護や訪問診療と連携しながら、自宅でも医療ケアが可能な場合もあります
1)デメリット
- 精神的な負担が大きい
- 「これでよかったのか」「苦しくなかったのか」後悔することがある
- パニックになることがある
2)メリット
- 亡くなったあとも、すぐに医師を呼ばなくていい
「夜中に亡くなったけど、朝まで家族だけで過ごしたい」
「まだそばにいたい。少しずつ気持ちを整理したい」
- 介護をしてきたご家族が、「ケアの主役になれる」
- 清拭や着替えを行い、髪を整え、手を握り、音楽を流し
- 「ありがとう」と伝えながら見送る
それは、本人と家族にとって後悔の少ないお別れにもつながります。
3)在宅でのサポート
- 24時間対応の訪問看護が夜間も駆けつけてくれる
- 医師と電話でいつでも相談できる
- いざというときは、緊急訪問も可能
※駆けつけるまでに時間はかかりますが、しっかり対応してくれます。
4.エンバーミングとは
1)エンバーミングをご存知ですか?
亡くなった人の体に防腐処置を施し、衛生的、そして美しい状態にする技術だそうです。
エンバーメントとも呼ばれます。平均的には10〜14日程度、保冷不要でご遺体が保存が可能といわれています。(ただし高温多湿の環境では要注意)
2)歴史
・国際化により、「海外で亡くなった方の遺体を日本に戻す」ケースが増加
遺体の腐敗や衛生保持のために、エンバーミングが必須となる国も(例:アメリカ・カナダなど)
→ 日本でも国際基準に対応する必要が出てきた
・「遠方の親族が来るまで待ちたい」「きれいな顔で会いたい」という声が強くなった
→ エンバーミングにより、遺体の保存期間を延ばすことが可能に
・医療現場やホスピスで「最期のケア=看取りケア」が重視される中で、
“死後のケア”の質も大切にしようという声が医療者からも上がった
→ 死後処置を単なるルーチンではなく、「尊厳を守る医療の一環」として見直す動き
・2000年代に入って、SARSなどの感染症流行があり、
「遺体を安全・衛生的に扱う必要性」が高まった
海外では既に常識だったエンバーミングが、日本でも注目され始めた
上記のような背景を受け、2004年に厚労省がガイドラインを発表
日本遺体衛生保全協会(IFSA)による資格制度が始まる
現在は、遺族の希望があればエンバーミングは合法的に実施可能です。
3)具体的な方法・目的
血液を抜いて防腐剤を血管内に注入することで、体内の腐敗を防ぎ、衛生を保つことができます。
表情も柔らかくなり、ウイルスの不活化や感染予防にもつながるため、衛生的な処置として重要です。
また、海外へのご遺体搬送などにも対応しやすくなります。その後、専用の洗浄液で全身を清拭します。
**皮脂や脂肪分を取り除く“脱脂”**を行うことで、皮膚の変色や酸化を防ぎ、粘膜や皮膚を清潔に保ちます。
これにより、見た目の変化も抑えることができます。また、**むくみがあればドレナージ(体液の排出)**を行い、
テープやワイヤーで口元・顔の表情をやさしく整える処置も行います。
傷口や創部がある場合は、薬液で丁寧に消毒・処置されます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 資格名 | 遺体衛生保全士(エンバーマー) |
| 管轄団体 | 公益社団法人 日本遺体衛生保全協会(IFSA) |
| 国家資格? | ❌ 国家資格ではないが、厚生労働省の指針に基づいた民間資格 |
| 対象者 | 高卒以上なら誰でも可。医師・看護師・葬祭関係者でなくても取得できる |
| 養成校 | 日本ヒューマンセレモニー専門学校など(1~2年制) |
| 必要な知識 | 解剖学・病理学・感染管理・倫理・薬剤・整容技術など |
5.まとめ
| 場所 | 良い点 | 注意点 |
|---|---|---|
| 🏥 病院 | 医療体制が整っていて安心 | 慌ただしく、すぐに対応してくれない場合も |
| 🏡 施設 | 落ち着いた環境、信頼関係のあるスタッフに見守られる、付き添いやすい | 医療処置に制限あり、施設によって”やりたいことができない”場合も(〇〇を食べさせたい、水を飲ませたいなど) |
| 🏠 在宅 | 自分たちらしく過ごせる、自由度が高い | 精神的負担が大きい |
6.おわりに
人それぞれの希望や人生があります。
お盆というこの時期、
大切な人を思い出し、話し合う。そんな時間にしていただけたらと思います。
★この記事が参考になったらクリックお願いします。応援していただけると嬉しいです
にほんブログ村

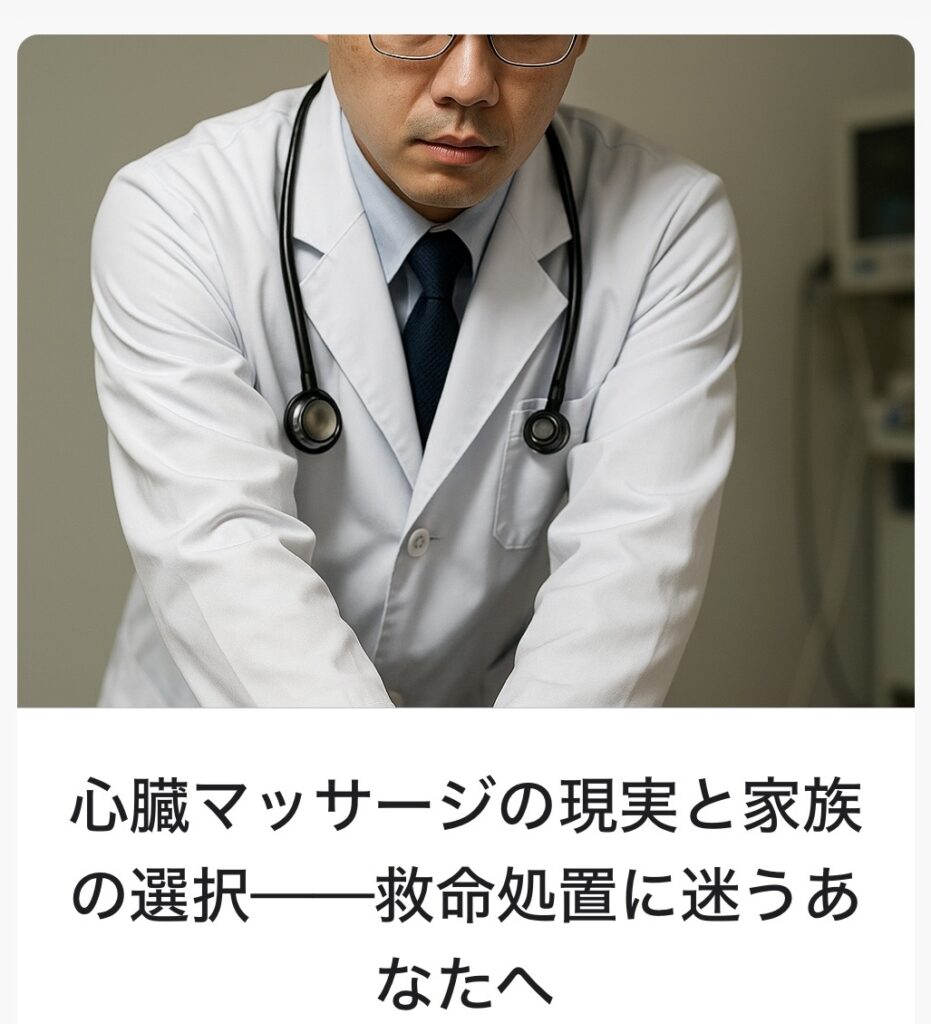
No responses yet