
医療的ケア児のママ。会社員の夫と3人暮らし

医療的ケア児のママ。夫は英語が得意だけど、わたしは苦手。
目次
1.はじめに:カタカナ言葉ってむずかしい?
あきこ: 医療的ケア児の育児をすると、よくカタカナ言葉がでてくるの。でも、まだ馴染みがなくて、ややこしいって思うの、私だけかな?
わたし: 「ニーズ」とか「サポート」みたいに、普段からよく聞く言葉だったらまだわかるんだけどね。
あきこ: 「インクルーシブ」とか「ノーマライゼーション」とか出てくると、もう頭がこんがらがっちゃう…。
わたし: それ、あるある(笑)。なんで日本語じゃなくてカタカナなんだろうね?
あきこ: たしかに。「共に学ぶ」とか「普通の生活」って言い換えられそうなのに。
わたし: 調べてみると、日本語だと長くなるし、ぴったり当てはまる言葉がないのと、海外から入ってきた“考え方”だからそのままカタカナで使ってる説があるみたい。
あきこ: なるほど。海外の制度とか条約で使われてる言葉なんだ。
わたし: そうそう。「障害者権利条約」とか国連の文書なんかにも出てくるから、日本でもそのまま使われることが多いんだって。
あきこ: よーし!今回はそんなちょっと難しいカタカナ言葉を、できるだけ簡単に、イメージしやすく説明してみようと思います!
わたし: これを読んで、少しでもカタカナの苦手意識が少なくなりますように!
2.日常生活から政治分野まで幅広く使われるカタカナ言葉
1)バリアフリーとは
あきこ: 「バリアフリー」って段差をなくすとかでしょ?
わたし: そうそう。でも最近は、段差だけじゃなくて、制度とか心の壁も含めて使われてるよ。
つまり、「社会の中にある障壁(バリア)を取り除いて、誰もが暮らしやすくすること」 を示すみたい。
段差や階段のような物理的な障害だけでなく、制度や心の壁も含まれるんだ。
2)ユニバーサルとは
あきこ: じゃあ、「ユニバーサルデザイン」でよく聞く、「ユニバーサル」は?
わたし:英語の universal から来ていて、
「普遍的な」「全ての人に共通する」「誰にでも通じる」 という意味だよ。 「ユニバーサルデザイン」は”誰でも使いやすいように作ること。”
あきこ: たとえば?
わたし: 誰でも押せる大きなボタンとか誰でも着やすい服、赤ちゃんもお年寄りも使いやすいトイレとかね。
3)インクルーシブとは
あきこ: じゃあ「インクルーシブ」は?
わたし:英語の inclusive から来ていて、
「包み込む」「排除せずに含める」 という意味。 “誰かを特別扱いするのではなくみんなで一緒に”ってこと。最近は、「インクルーシブ教育」っていう言葉をよく聞くな。障害のある子も、ない子も、一緒の教室で学ぶようなイメージ。
あきこ: そうだね。これはまだ新しいから、賛否両論あるよね。
わたし: そう。でも「できるかどうか」じゃなくて、「どうやったら一緒にいられるか」を考えるのがインクルーシブなんだって。
4)ノーマライゼーションとは
あきこ: まだまだカタカナ言葉は沢山あります!「ノーマライゼーション」についていきましょう。
わたし: 英語の normalization(標準化・普通にする)からきた言葉。「障がいがあってもなくても、誰もが当たり前に地域で暮らし、共に生きることができる社会をつくる」 という理念だよ。
あきこ:「施設に閉じ込めるのではなく、地域で共に暮らす」取り組みが今も進められているんだよね・
わたし:「地域共生社会」「インクルーシブ教育」「バリアフリー」などにつながる基盤の考え方なんだって。
5)マイノリティとは
わたし: 「マイノリティ」もよく聞くよね。英語 でminority は、「少数」「少数派」。社会の中で 人口や勢力が少ない人々、または 多数派に比べて弱い立場に置かれやすい人々 を指します。これって、障害のある人のことだけじゃないよね
あきこ: 子育て中の人も、介護してる人も、病気を抱えてる人も、立場によっては“マイノリティ”になるんだって。
わたし: 「急に子どもが入院して、仕事を休まなきゃ」って状況って、会社の中では少数派かも。周りに同じ状況の人がいないし、社会に迷惑かけてるって思うと辛くなるよね。
あきこ: そうそう。社会の仕組みが「多数派」を基準にできてると、それ以外の人たちは、声が届きづらくなるんだよね。
6)アドボカシーとは
あきこ: でもさ、「理解してほしい」「対策を一緒に考えてほしい」って思っても、伝えるのって難しくない?
わたし: だからこそ「アドボカシー」って言葉が大事なんだと思う。
あきこ: アドボカシー?
わたし: うん。「代弁」「権利擁護」って訳されることもあるけど、「声をあげにくい人の権利や思いを守り、社会に伝えること」なんだ。 親や支援者が代弁することもあれば、当事者が自分の声を届けることもアドボカシーのひとつだよ。
🔷アドボカシーの種類:
・セルフ・アドボカシー
本人が自分の意見や権利を主張すること。
・ピア・アドボカシー
同じ立場にある人同士が支え合って代弁すること。
・プロフェッショナル・アドボカシー
専門職(弁護士・ソーシャルワーカー・医療者など)が本人に代わって意見を伝えること。
あきこ:アドボカシーはどうやってやるの?
わたし:ブログやSNSで体験や思いを発信する。新聞・テレビ・イベントなどで話す。本や動画を作って多くの人に届ける。行政や政治に働きかける。仲間や団体とつながる。あとは、支援者に相談するなどがあるよ。
7)政治とリベラル
あきこ:政治の中で、「障がい者の取り組み」を掲げている人もいるよね。
わたし:「リベラル」っていう言葉があるんだ。英語の liberal に由来していて、もともとは「自由な」「寛大な」って意味なんだけど、政治の世界ではちょっと違う使われ方をするの。
個人の自由や人権を大事にして、少数者(マイノリティ)、女性、障がい者、外国人などの権利を守る立場なんだって。
それに、平等や多様性を大切にして差別をなくし、誰もが社会に参加できるようにしようという考え方。
社会保障や教育、医療などで公的な支援を広げて、「社会をより公平にしよう」とする方向性なんだよ。
あきこ:なるほど。これからは、そういう視点で政治家や政党を見て、投票するのもいいね。。
3.おわりに:誰もがマイノリティになる
医療的ケア児のママも、きょうだい児も、ケアを担う親も、介護をしている方も、状況によって、みんなある日突然マイノリティになることがあります。でも、**「少数派だから黙っていよう」「我慢しなきゃ」じゃなくて、「少数派だからこそ、困っていることを伝えよう」**という考えが大切だと気づきました。
SNSでつぶやいた小さな一言が、思いがけず大きな反響につながることもあります。
困ったときや悩んだときは、ぜひ発言してみましょう。
もしかしたら、仲間が見つかったり、誰かが素敵なアイデアやヒントを届けてくれるかもしれません。
★こちらもご覧ください★
★参考になったらクリックお願いします。応援していただけると嬉しいです
にほんブログ村

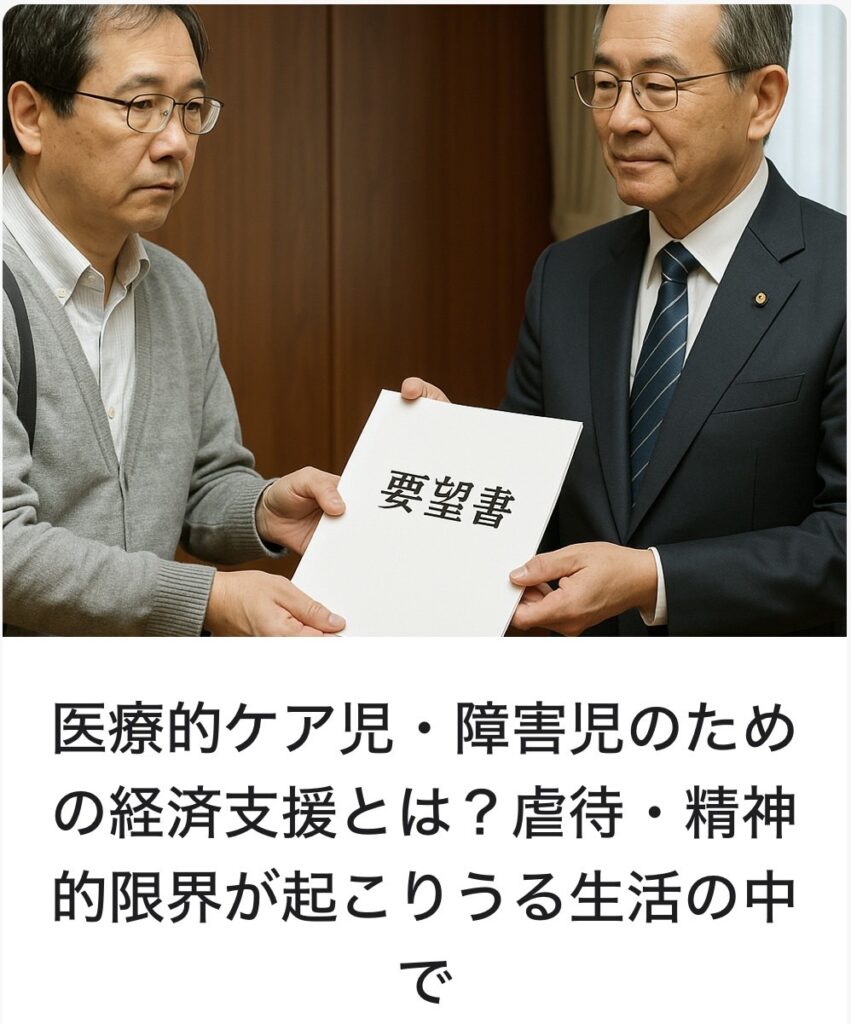
No responses yet