
障害のある子どもが施設で暮らす──
その背景はとても複雑です。
経済的な問題、支援の不足、孤立、親の限界……
その結果「虐待」をしてしまう親もいます。
今回は、障害児入所施設の現状と、親が直面する課題、そして少しでも支えになる制度について、対話形式でお届けします。
目次
1.対談:障害児施設と虐待の現実

医療的ケア児のママ。看護師(育児休業中)。会社員の夫と3人暮らし。

医療的ケア児のママ。あきことはSNSで知り合う。
あきこ:
障害児施設に入所している子どもの4割は、虐待経験があるんだね。
わたし:
そう。それは単に「虐待された子」ってことじゃなくて、家庭で支えきれなかったという背景があると思う。
あきこ:
親の精神的・経済的な余裕のなさ、社会的支援の不十分さ、孤立や偏見……
助けがない中で、限界が重なった結果なんだね。
わたし:
今回の調査(前回のブログ参照)では、入所している子どもの7割が知的障害で、2割が重度心身障害だった。
だから、医療的ケア児が虐待を受けていたかどうかは、正直このデータからはわからないんだよね。
2.経済的に苦しい現実と制度の力
あきこ:
お世話が大変だと働けないし、経済的にも困るよね…。子どもが入院したら長期間仕事を休まないといけないし。
わたし:
そうだね。仕事と育児・ケアの両立って難しいよね。
さらに、家事・兄弟・親の介護などもっと多くの問題を抱えている人もいるよね。
あきこ:
医療的ケア児を育てていて、経済的支援ってなにかしてもらっている?
わたし:
私は、
1)児童手当
2)小児医療費助成
3)特別児童扶養手当
4)障害児福祉手当
5)身体障害者手帳
6)小児慢性特定疾患
のサポートを受けているよ。でも、これってほとんど自分で調べて申請したんだ。
あきこ:
私もパンフレットを渡されて、「該当するところはもらっておいたほうがいいですよ!」としか言われず、
自分たちがどんな支援が受けられるのか、何を申請すればいいか分からなかったな。

1)~6)について、わかりやすくご紹介します。
利用できる支援はその子の状態、ひとり親、所得制限、地域差などがあります。
ぜひ、相談してみてください!
3.私たちが利用している6つの経済支援
1)児童手当
対象: 0歳〜高校卒業までの子ども
内容: 月額10,000円(3歳未満は15,000円)、第3子以降は月額30,000円
特徴: 所得制限なし。
2)小児医療費助成
対象: 自治体による
内容: 医療費を助成してくれる
特徴: 自治体によって助成内容が異なる(一部負担あり・無料など)

この制度のおかげで、私の子どもの医療費の自己負担はありません
3)特別児童扶養手当
対象: 障害がある20歳未満の子どもを育てる保護者
内容: 月額1級 56,800円/2級 37,830円(令和7年)
特徴: 所得制限あり。申請・診断書が必要。
🟢 精神障害(発達障害など)でも対象になる場合があります。
4)障害児福祉手当
対象: 重度の障害がある20歳未満の子ども
内容: 月額16,100円(令和7年)
特徴: 子どもの名前で作成した銀行口座が必要です
5)身体障害者手帳
対象: 一定の身体的障害(視覚・聴覚・呼吸器・肢体不自由など)がある人
内容: 手帳の等級に応じて税金の控除、医療費助成、交通費割引、燃料費助成など
特徴: 等級によって支援内容が変わる。
🟢 診断書が「呼吸器」「心臓疾患」などに分かれています。

多くの自治体では年齢制限は設けられていません。
ただし、3歳未満では発達中のため正確な認定が難しく、再判定や審査に時間がかかることがある場合もあります。
同年代で同じ病気でも、「赤ちゃんでももらえた」という方がいる一方で「医師から3歳からと言われた」「申請したけど通らなかった」という声もあります。
他のママさんに聞いてみた結果、自治体や地域によって審査の考えに違いがあることが分かります。
6)小児慢性特定疾患
対象: 慢性的な病気(心臓病、腎疾患、神経疾患、染色体異常など約800疾患)をもつ子ども
内容: 医療費の上限額が設定され、それを超えたら自己負担がなくなる。入院中の給食やミルクが無料になったり、福祉用具の助成など生活支援・介護・教育支援を目的
特徴: 自治体によって支援内容が異なる
🟢 教育に関する相談などもしています。詳しくは、小児慢性特定疾病情報センターのHPをご覧ください。
4.いろんな人に相談しましょう
わたし:
支援制度があっても、気づかないで申請していない方もいると思います。子どもを残して、区役所まで申請に行けない場合もあるよね。
あきこ:
家庭の状況によっては委任状を書いて代理申請できる場合もあるので、まずは
・保健師
・相談員
・医療的ケア児等支援センター
・医療的ケア児コーディネーター
・主治医
・看護師など
にぜひ聞いてみてください。また悩みや不安があっても相談してみてください。
何か解決策を考えてくれるはずです。
わたし:
相談しても、相手が「医療的ケア児のご家族と話すのは初めてなんです」「わからない」「調べてみます」という場合もあるので、
”その方だけではなく、別の支援者にも相談することが大切”だと思います。
あきこ:
医療的ケア児のサポートはどんどん増えていったり、変更もあるから、関係者でもしっかり情報を把握しきれていない場合があるよね!
5.支援の対象にならない子ども・家庭
あきこ:
所得制限や地域の考えによってギリギリ支援の対象にならない場合もあるみたい。
わたし:
そうなんだよね。
「グレーゾーン」って言われる、診断がついていない、等級に届かない、家庭の事情が複雑すぎる……
でも支援が必要ないわけじゃない。
あきこ:
SNSで訴えかけたり、市に”要望書”を提出する動きが各地で生まれているみたい。
「こういうケースにも支援が必要です」
「制度からこぼれてしまっている現実があります」
そんな声が、制度の見直しや新しい支援のはじまりになるかもしれません。
おわりに

今回は、私が利用している経済支援についてご紹介しましたが、
他にも様々なサポート体制があります。
自治体独自のとりくみもあるので、
ぜひ誰かに相談したり、SNSで呼びかけてみてください。
医療的ケア児の親に関わる、悲しい事件が報道されることがあります。
ケアに追われ、働く余裕もなく、経済的にも苦しい。
家族にも、行政にも、頼れる人がいない。
このニュースを見て、「明日は我が身かもしれない」と感じた方は沢山いるそう。
どうか──一人で抱え込まないでください。
声をあげることは、弱さではありません。
それは「助けが必要だ」と伝える、大切な勇気です。
あなたの声が届けば、変わることがあるかもしれません。
小さな声が、誰かの力になります。どうか、話してください。
★この記事が参考になったらクリックお願いします。応援していただけると嬉しいです
にほんブログ村

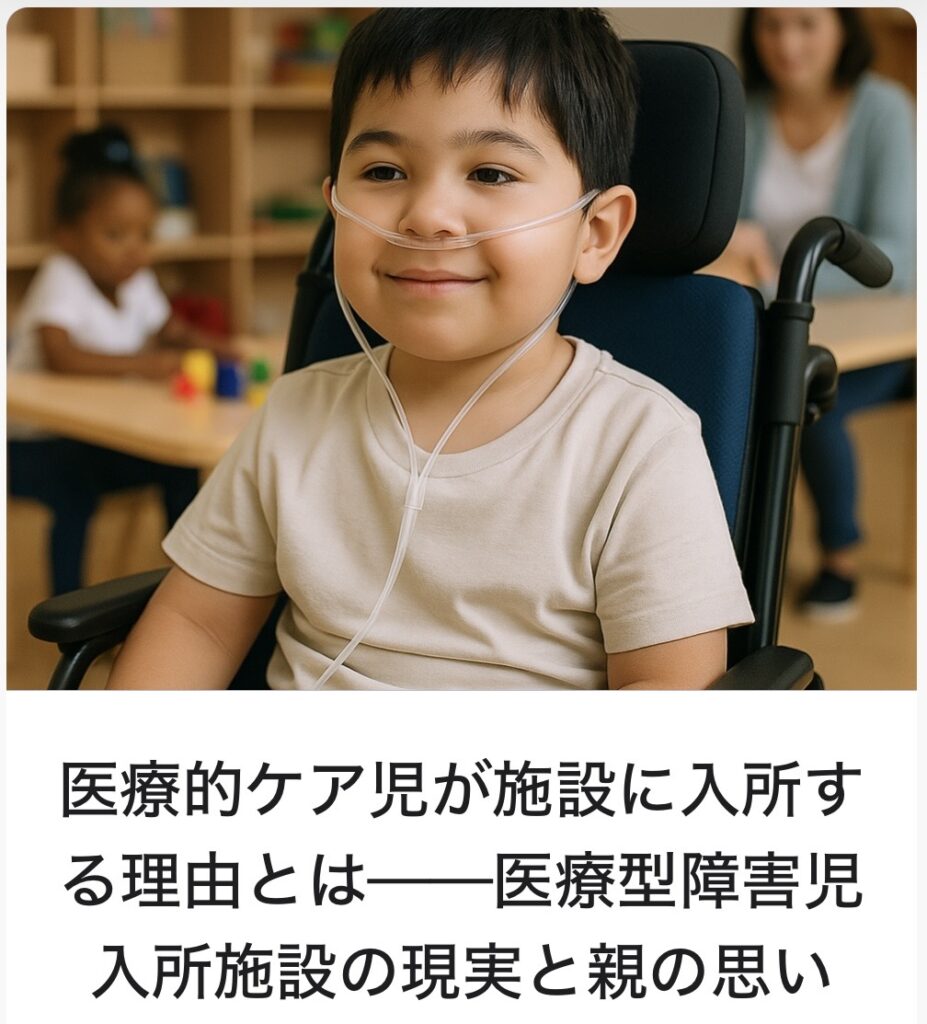
No responses yet