
みなさんのお子さんは育児中、なにかを嫌がったりすることはありますか?
目次
1.ケアを嫌がる娘と向き合って──医療的ケア児の呼吸器装着に悩んだ私の試行錯誤
私の娘は生後7カ月のとき、突然、眠っている間にSPO2(酸素飽和度)が下がるようになりました。
SPO2は身体の呼吸状態を示します。数値が低いと呼吸が苦しいことを意味します。
最初はモニターの誤作動かと思いましたが、顔色が悪く、次第に頻度も増加。
30分おきに下がるようになり、私たちは「何かがおかしい!」と不安になり、そして寝不足の日々に突入しました。
2.新しい医療的ケアが始まったきっかけ
医師の診断は「睡眠時無呼吸発作」。
放っておくと寝ている間に命に関わる問題です。そのため呼吸器の導入が必要となり、私たち親子の試行錯誤の日々が始まりました。
3.ケアに迷走した日々
◇呼吸器の変更
最初は、最初はハイフローという空気が常時流れる機器を使用しました。
しかし風が顔に当たるだけで娘はギャン泣き。風を弱めても嫌がるため、「トリロジーEVO」という呼吸器に変更しました。

しかしマスクを顔に近づけるだけで大泣き。
頭に手を伸ばすと警戒し、寝ているときに装着してもすぐに起きて泣く。
生死に関わるため装着は不可欠でしたが、娘の反応を見るのがつらく、私自身も何度も涙を流しました。
ほかに合う呼吸器やマスクがないか、医師や医療業者さんに確認しましたが、
新生児用のサイズはこれしかなく、
「まだ始めたばかりなので、様子を診ましょう」「徐々に慣れるようになります」との言葉。
★こちらもご覧ください★
◇家族の思いがバラバラ

夫は 「寝ているのに、無理に着けるのはかわいそうだ」と言う。
「もうやめよう」とも..

まるで無理に着ける私が悪いことをしているかのように感じてしまい、孤独でした。
呼吸器がつけられないので、夜間もSPO2が下がる日々。
そのたび、呼吸を再開するように、娘をしっかり起こさなければならず、親子ともに睡眠不足。心も体も限界でした。
医師に再度相談しても「無理なときはつけなくていいです」という言葉。
それでは、一向によくならないと思いました。
いつまでこの辛い生活が続くのか途方にくれていました。
★こちらもご覧ください★
4.打開のきっかけ

「もう心が折れて限界だ」そう感じていた時。訪問看護・リハビリさんが手を差し伸べてくれました。
◇訪問看護の回数と時間を増やす
これまでは週1回・1時間の訪問看護でしたが、新たに事業所と契約し、現在は週3回・1時間半の訪問に増やしました。
訪問看護師さんにも呼吸器の練習をお願いしたことで、私の負担がぐっと減りました。

「今日は訪問看護師さんが来るから、無理せずお任せしよう」
「あともう少しで訪問看護師さんが来るからそれまで頑張ろう」と前向きな気持ちになりました。
◇医療者の関わり
これまで私は、chatGPTやSNSのお友達に聞いた
「呼吸器やマスクを変える」「泣いたら無理せずにはずす」「呼吸器がこわくないと思ってもらえるようにふれあいの時間を作る」ということを実践してきました。しかし、それではうまくいかず悩む日々。
そんな時に、訪問看護師さんやリハビリさんが新たなアドバイスをしてくれました。
・娘が拒否する状況を観察して「何が嫌なのか」考えて工夫してくれた。
- 「マスクをつけるときに髪の毛が引っ張られていたいのかも」→頭とマスクの間にハンカチを挟んで摩擦を防ぐ
- 「呼吸のタイミングが合わなくて苦しいのかも」→吸った時のタイミングに合わせて装着する
- 「空気が冷たいのかも」→加湿の温度をあげる
- 「マスクを上からつけたら怖がっている」→マスクは上からでなく横からつける
- 「呼吸のモードが合っていないのかも」→医師に頼んで弱いものから正常の範囲の設定を選べるようにしてくれた
- 「他のことに集中していたらつけられるかも」→動画を見ながら起きているときもマスクに触れる練習をする
- 「最初は5秒間頑張ってみよう」と●秒間ずつ、マスクのみの装着を少しずつ練習する

どれも、私には想像できなかった”嫌がらない工夫”を考えてくれました。
もっとはやく相談すればよかったと思いました。
とても心強かったです
・「大変でしたね」と言ってもらえた
「これはお母さん、大変でしたね」と言ってもらったとき、張りつめていた心がほぐれ、涙があふれました。一緒に悩み、試行錯誤してくれる人の存在は本当に心強いものでした。
・無理をしないという選択肢
訪問看護師さんの提案で、リハビリ中でも呼吸器の練習を実施。今では訪問看護・訪問リハビリを含めてスタッフさんと週4〜5回練習できるので、私が無理して練習しなくてもよくなりました。
・今後の見通しについてのアドバイス
赤ちゃんに合うサイズのマスクや呼吸器は少ないのが現状ですが、「大きくなれば選択肢が広がる」と希望をもらえました。
また「徐々に慣れてきたから、きっとつけられるようになりますよ!」と言ってくれた時は嬉しかったです。

「ただがむしゃらに頑張ってつけることでしか、慣れる道はない」と思っていた私ですが、
身近な存在の訪問看護・リハビリさんの協力を得ながら、焦らず少しずつ慣れていくスタンスに代わってきました。
娘も、以前のようにギャン泣きではなく、笑顔で呼吸器を手で振り払うレベルになってきたので、負担なく練習できているなと安心しています。
おわりに
SNSで、離乳食を床に投げる赤ちゃんの動画を見かけました。医療的ケア児にかかわらず、「拒否をするのは当たり前」
「赤ちゃんって、そういうもんかもしれない」。そう思ったとき、少し心が軽くなりました。
ケアを嫌がる姿に悩み苦悩を感じる母親は私だけじゃない。
子どもの意思があるのは、生きている証拠。
悩んだときは、たくさんの人に相談することで、何か解決の手がかりが見つかるかもしれません。
自分と娘の意思も大切にしながら、これからも少しずつ困難を乗り越えていきたいと思います。
★この記事が参考になったらクリックお願いします。応援していただけると嬉しいです
にほんブログ村
★こちらもご覧ください★

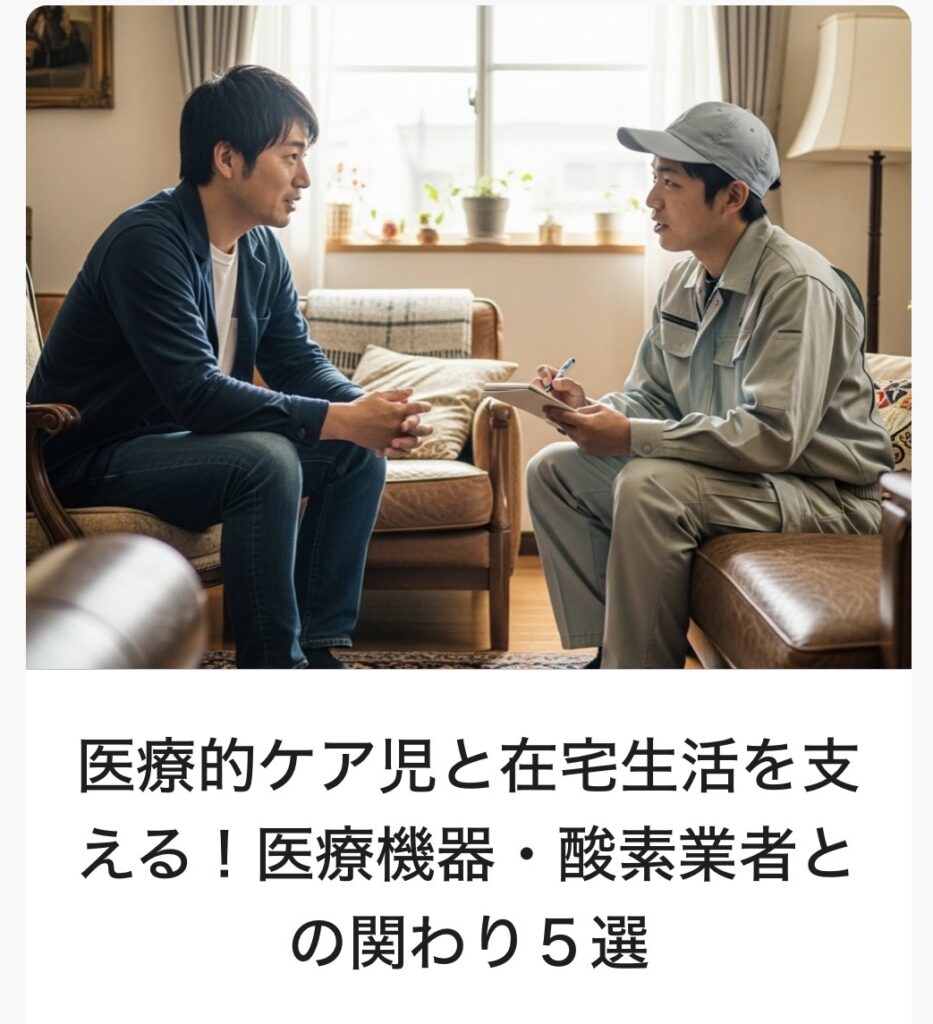

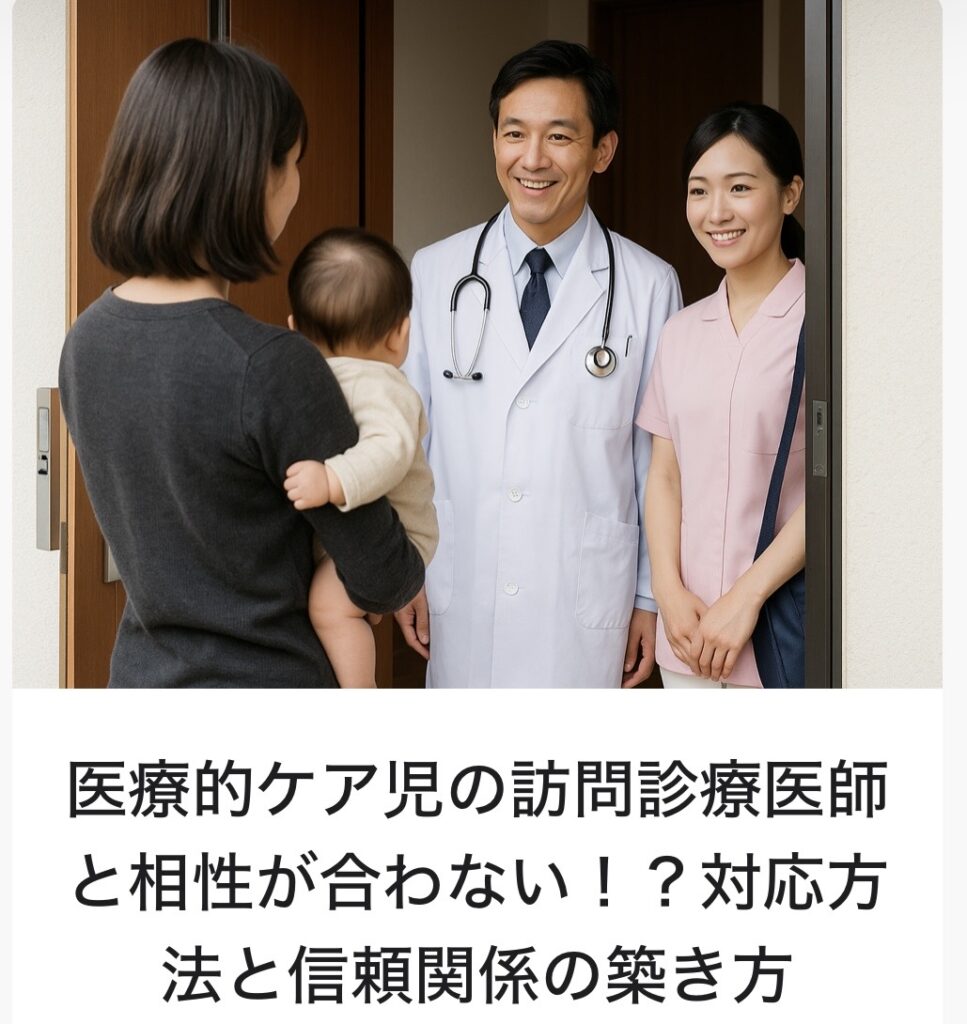
No responses yet