前回は、医療的ケア児の育児における、父親のさまざまな葛藤や不安をご紹介しました。
今回は、”母親の苦悩”に関して厚生労働省の調査によって分かったリアルな声を整理してみました。
※本記事の一部は厚生労働省資料(p.78-82)令和元年 医療的ケア児者とその家族の生活実態調査
報 告 書を参考に、AIの力を借りて構成しています。
1. 調査から分かった医療的ケア児をもつ母親の大変さ
1. 保育園・学校に通わせたくても通えない
- 医療ケアがあることで受け入れが拒否され、母親は仕事を続けられない
- 学校でも看護師不在、付き添い必須で共働き困難
- 通わせてあげたいのに、母親の負担が大きすぎてできない
2. サービスが十分に受けられない
- 放課後デイ・児童発達支援、ショートステイに医療ケア対応の施設が少ない、予約が取れない
- 医療的ケアの経験がない看護師、スタッフ不足で受け入れ拒否
- 土日や夜間の預かりがなく、送迎がない
- きょうだい児との外出も困難
4. 働けない・働いても不安がつきまとう
- 退職せざるを得ない。それにより経済的な不安がある
- 放課後デイの短時間だけではまとまった仕事ができない
- 子どもの体調不良・入院で休みがちになり解雇の不安がつきまとう
5. 睡眠不足と心身の限界がある
- 命の危険と隣り合わせで、そばから離れられない
- 昼夜問わずケアや育児が必要
- まとまって眠れない
- 睡眠不足で頭がぼーっとする
6. ストレス・孤独感・体調不良がある
- 医療的ケアを初めて数年、精神的にも肉体的にも限界
- 一人になりたくてもなれず、感情があふれてしまうことも
- 社会から孤立していくような感覚
- 先が見えない不安。子どもにあたってしまう
- 自分の体調管理ができないまま「介護者」で居続けるつらさ
- 障がい児を持つ家族とのつながりが欲しいが方法がわからない
- 外出しても周囲の目が怖い。「可哀想」と思われそう
- 病状に一喜一憂して心が揺れ動く
- 大変すぎて愛情がもてない。もっとゆっくり育児を楽しみたい
7. きょうだい児へのしわ寄せがある
- ケア児につきっきりで他の子に目が向けられない
- 外出、遊び、送迎が必要な習い事…親がやってあげたいこと・子どもがやりたいことを諦めさせてしまう
- 両親が揃って関わることが難しく、学校の行事、外出が家族みんなでできない
- きょうだい児に我慢ばかりさせてしまう
8. 緊急時の対応ができない不安がある
- 自分やきょうだい児が体調を崩しても、医療的ケア児のケアや育児を代わってくれる人がいない
- 家族も高齢で頼れず、「何かあったらどうしよう」が常に頭をよぎる
- 医療ケア児本人の緊急対応には慣れてきたけれど、家族や母親自身が倒れたら何もしてあげられていない
9. ひとり親家庭はより不安がある
- シングルマザーはより一層の負担と不安
- 学校や放課後デイだけでは働く時間が足りない
- 急な呼び出し・ケア対応があると、就労も経済的自立も難しい
- 頼れる人、預けられる施設がない
10. 将来への不安がある
- 子どもが学校卒業後、日中どうすればいいのか分からない
- 自分の体力が心配だが、施設は空いていない・情報もない
- 親が亡くなったあとの居場所が見えない
11. 「母親のみ」できるケア・育児がある
- 家族が部分的にしかケアを担えず、結局「母じゃないと無理」に
- そのため、母の外出が限られる
12. 行政支援が追いついていない
- 手続きや情報収集がすべて自己責任で、外出すら難しい家庭には負担
- 市役所に聞いても情報不足でたらいまわし
- どんなサービスがあるのか分からない、窓口に相談しても親身に聞いてもらえない
13. 時間がないので手続きも通院も後回しになる日々
- 子どものお世話と食事の準備だけで一日が終わる
- 家事・育児・介護・仕事を抱え、自分の病院に行く時間すら取れない
- 持病が悪化しても、治療に専念できる環境がない
- 入院が必要になっても「子どもをどうするか」で身動きが取れない
14. 移動困難と送迎の限界
- 呼吸器や機材で荷物が多く、ひとりでの外出が物理的に不可能
- 福祉タクシーは高額で継続的に使うのが難しい
- 交通機関では乗車拒否されそうになったという声もあり、外出そのものがストレスに
- 利便性の高い場所に子どもと引っ越したため、夫と別居になった
15. 成長とともに変化するケアのかたち
- 子どもの身体が大きくなることで、移乗・入浴・移動などの介助が困難に
- 18歳を超えると、医療費の負担や現在のサービスを継続できるのか不安
- 自宅で介護ができるのか、家の構造・家庭状況が心配
- 安心して生活できる施設が少なく、入所のハードルが高い
16. 経済的不安と将来設計の難しさ
- 医療費・通院費・送迎費などの出費がかさむ一方、離職による収入減
- 再就職と育児が両立できるのか不安
- きょうだい児、老後の蓄えの不安
17. 「医療的ケア児」でも受け入れが違う
- 知的障害はなく歩けるが、気管切開や呼吸器などの医療的ケアが必要な子は施設によって受け入れ対象外となる
- 障害者手帳や療育手帳が取得できないケースがあり、支援の対象外となってしまう
- 実際は目が離せず非常に大変なのにサービスが受け入れられない
2.周りからの言葉

「子どもが寝ているときは、母親も休めるからいいよね」
「24時間ずっと育児をしているわけじゃないでしょ?」
「働ける場所は絶対あるよ!ちゃんと探したの?」
「いつから働くの?」
そんなふうに言われることがあります。
「子どもが寝ている時には、母親も休める」という言葉に対してですが、
医療的ケア児の状態によっては、**「眠っている間こそ目を離せない」**ということもあります。

たとえば、私の娘は睡眠時無呼吸があります。
これは、寝ている間に呼吸が止まってしまう病気です。また、てんかん発作もあり、いつ起こるか予測ができません。
「寝てくれているから安心」ではなく、「寝ている間もそばから離れられず緊張と不安が続く」毎日です。
一時期は「寝ないでくれた方が安心だから、寝ないで」と思っていたことがあります。
私と娘が一緒に寝ており、パルスオキシメーターのアラームに気づかなかったときは自分を責めました。
娘の体調が悪くならないか、辛くなかったか不安でした。
また、お友達の話だと、ちょっとトイレに行ったとき、その間に呼吸器がずれて呼吸が苦しい姿を発見したことがあると。
また、育児だけをしていればいいわけではありません。
医療機器の洗浄、注入準備、家事、掃除、洗濯…やるべきことは尽きません。
★こちらもご覧ください★
3.周りからの視線

「夫が家にいてくれるから生活は楽でしょう」
「夫のことも、ちゃんと気を遣いなさいよ」
夫も頑張ってくれていますし、「家にいる自分がやらなきゃ」と思っているのですが、
実際は寝不足で頭がぼーっとして、思うように進まないことも多いです。
気づけば一日があっという間に終わっていて、「私、なにしてたっけ?」と感じることさえあります。
私は、夫が娘を見てくれる21時から3時までの間に睡眠をとっています。
周囲のサポートも得られているほうだとは思います。
でも、この環境があるから今の生活をなんとかまわせている、というのが正直なところです。
もしこの支えがなくなったら、どうなってしまうのか、想像するのも怖いです。
私は運転ができませんし、娘も一人で黙って車に乗っていることはできないので、
外出や病院受診も夫のサポートが不可欠です。

「外出したいけど、周囲の目が怖い」という気持ち、とてもわかります。
私も病院で、「赤ちゃんも通院してるんですか?」と驚かれたことがありました。
なにげない一言が、心に重くのしかかることもあります。
日々の忙しさのなかで、「育児を純粋に楽しめない」気持ちも痛いほどわかります。
ケアを拒否されると、命の危機と拒絶された悲しさで胸が苦しくなります。絶望も感じます。
そして母親自身の体調が崩れた時、娘はどうなるのか私も不安です。
これは、早めに対応策を考えなければいけないと思っています。
3.おわりに
◇理想と現実のギャップ
本来であれば、我が子の成長を見守ることは、もっと楽しくて、もっと嬉しいはずなんです。
「初めて笑った」「今日も無事に一緒に過ごせた」──
そんな一つひとつの変化を、心から喜びたい。
でも実際には、
「この先どうなるんだろう」
「本当に大丈夫なのかな」
「身体の負担が…」
そんな不安や日々の大変さに押されて、純粋に育児を楽しめない自分がいることに気づきます。
◇情報がしっかり手に入ったら不安は減らせる
必要な情報がすぐに手に入るわけでもありません。
調べてもよくわからなかったり、「この地域では対応していません」と言われたり…。
医療的ケア児の支援自体がまだ新しく、制度も整いきっていないからこそ、
**「知らない」「対応できない」**という壁にぶつかることも多くあります。
たとえば、娘はいまベビーバスで入浴していますが、
「大きくなったらどうやってお風呂にいれよう」「私の腰もたぶん限界がくる」と、ずっと不安に思っていました。
でもあるとき、福祉用具に“入浴補助具”がたくさんあることを知りました。
バギーを契約するときに、担当の方が教えてくれたんです。
「こんな方法があったんだ」
「これなら続けられるかもしれない」
「もっとはやくに知りたかった。悩んでいる時間が無駄だった」
と安堵した瞬間でした。
知らなければ、不安のままひとりで抱えていたこと。
でも、誰かが教えてくれたことで、ぐっと気持ちが楽になったのを覚えています。
◇相談できる場所の大切さ
だからこそ、
「必要な情報がきちんと届くこと」
「わからないままにしないで相談できる場所があること」
それがどれだけ大切か、今あらためて感じています。
◇対処法がわからない現実
また、医療的ケアは、ただの“お世話”とは違います。
命にかかわることだからこそ、子どもにも親にも、ものすごく大きな負担がかかります。
医療的ケア児を育てる母親たちは、目の前のケアだけでなく、
制度のはざま、将来への不安、見えにくい“今まで経験したことがなく、対処法がわからない”現実に向き合っています。
◇母親・家族のやりたいこととの両立
母親・家族のやりたいことと、育児・ケアを両立するにはどうすればいいのか――
母親のひとりひとりの声に耳を傾け一緒に考えていただき、必要な支援が届く仕組みがあってほしい。
この声が、少しでも誰かの心に届くことを願います。
★こちらもご覧ください★
4.追記
最近では、医療的ケア児とその家族が楽しめるイベントや医療的ケア児を受け入れてくれる訪問看護、保育園も、以前より広がりつつあります。
こうした取り組みは、本当にありがたく心強いものです。
でも残念ながら、地域によってサービスの有無や質に大きな差があるのが現状です。
今後も、誰もが平等に必要な支援を受けられる環境づくりが広がりますように願っています。
★この記事が参考になったらクリックお願いします。応援していただけると嬉しいです
にほんブログ村
★こちらもご覧ください★




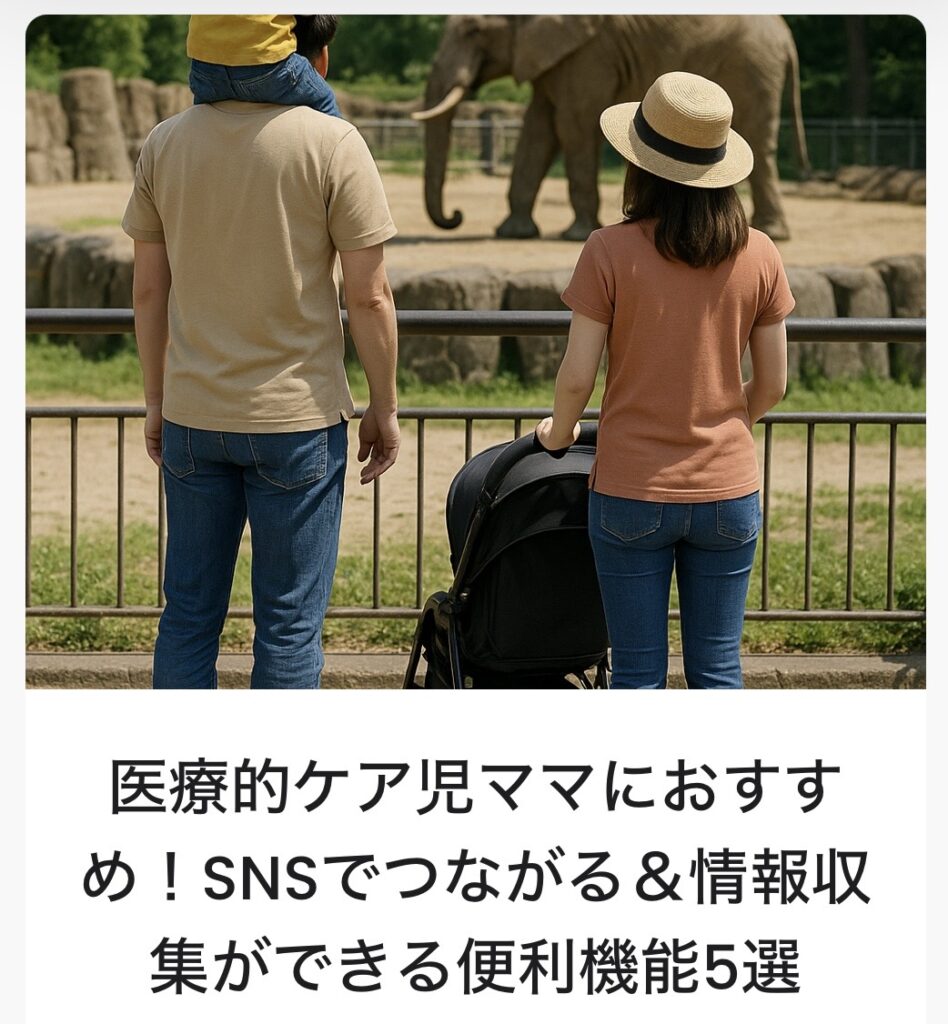
No responses yet