医療的ケア児やその家族が、SNSやテレビに登場するとさまざまな反応があります。温かい応援の言葉もあれば、残念ながら心ない言葉も少なくありません。
私の友人がYouTubeに出演した際に、「この子は〇〇みたい」「医療的処置なんて親のエゴだ」「医療的ケア児の育児って、早く亡くなるから大変じゃないよね笑」などのコメントが書かれていました。友人が傷つく前に、削除依頼を出しても消えず、大きな心の傷を残しました。
この記事では、誹謗中傷とは何か、人権侵害との関係、そして具体的な対処法についてまとめます。
目次
1.誹謗中傷とは?|侮辱罪・名誉毀損罪・プライバシーの侵害
「誹謗中傷」とは、根拠のない悪口や、事実かどうかに関わらず人を傷つける発言を指します。
法律上も以下のように処罰対象となる可能性があります。
- 侮辱罪(刑法231条)
公然と人を侮辱する行為。「〇〇(ひどい例え)みたい」「気持ち悪い」など、事実を示さなくても処罰対象になり得ます。2022年の改正で刑罰が厳しくなりました。 - 名誉毀損罪(刑法230条)
事実を示して人の社会的評価を下げる行為。「親のエゴで生かされている」などが該当します。 - プライバシー侵害・個人情報保護(刑法にはない)
本人の承諾なく私生活上の情報を公開すること(民事責任になることが多い)

無断で拡散したり、茶化したりすることはプライバシー侵害+名誉毀損の両方に該当する可能性があります。
2.人権侵害と刑法
”人権侵害”という刑法はありません。
しかし、人権を侵害する行為が刑法のさまざまな罪にあたることがあります。
1)人権侵害に関する刑法の例
- 名誉毀損罪(刑法230条)
→ 公然と事実を示して人の名誉を傷つけた場合 - 侮辱罪(刑法231条)
→ 公然と人を侮辱した場合 - 脅迫罪(刑法222条)
→ 「殺す」「危害を加える」といった言葉で脅した場合 - 住居侵入罪(刑法130条)
→ 勝手に住居に入りプライバシーを侵害した場合 - 強要罪(刑法223条)
→ 自由な意思を奪うように強制した場合
2)民事上の責任
刑法にあたらなくても、
- 民法709条(不法行為責任)
→ 権利や利益を侵害して損害を与えた場合は損害賠償請求が可能
このように、刑事罰ではなく**民事上の責任(慰謝料など)**になることも多いです。
3.日本国憲法で保障されている主な「自由」
1)〇〇の自由(例)
1. 思想・良心の自由(憲法19条)
自分の考えや信念を持ち、それを強制されない自由。
2. 信教の自由(憲法20条)
宗教を信じる・信じない、どんな宗教を信じるかを選ぶ自由。
3. 学問の自由(憲法23条)
学問研究や教育を自由に行える権利。
4. 表現の自由(憲法21条)
言論・出版・集会・デモなどで意見を発信できる自由。
5. 居住・移転の自由(憲法22条)
どこに住むか、どこへ移動するかを決められる自由。
6. 職業選択の自由(憲法22条)
どんな仕事に就くかを選べる自由。
7. 婚姻の自由(憲法24条)
結婚する・しない、誰と結婚するかを自分で決める自由。
8. 経済活動の自由(憲法22条・29条)
営業活動や財産を持つ自由。

「自由」には表現の自由だけでなく、思想・信教・学問・職業・居住・婚姻など多くの自由が憲法で保障されています。ただし、他人の権利や社会の秩序を壊さない範囲での自由です。
2)表現の自由による社会的影響
表現の自由とは、日本国憲法21条で保障されている基本的人権のひとつで、誰もが自由に意見を述べたり情報を発信したりできる権利です。民主主義の基盤であり、とても大切なものです。
しかし、表現の自由は無制限ではありません。他人の権利や社会の秩序を守るために、**「公共の福祉」**という制限があります。
- 批判や意見 → 表現の自由として保障される
- 誹謗中傷や差別 → 表現の自由を逸脱し、人権侵害にあたる
誹謗中傷は「意見」ではなく「人を傷つける行為」です。
- 「〇〇みたい」→ 侮辱罪(刑法231条) にあたり得る
- 「親のエゴで生かされている」→ 名誉毀損罪(刑法230条) にあたり得る
- 無断で住所や顔写真を晒す → プライバシー侵害(民法709条/個人情報保護法)
このように、誹謗中傷は表現の自由の範囲を超えて、法律で制限される対象になります。
子ども本人や家族の尊厳を深く傷つけ、社会的な偏見を助長する危険性があります。
4.誹謗中傷への対処法
1)相手と無理に関わらない
誹謗中傷に直接反応すると、さらに炎上することも。まずは冷静にスクリーンショットを保存して証拠を残しましょう。
2)SNS運営会社に通報・削除依頼
YouTubeやX(旧Twitter)、Instagramには「違反報告」「ブロック機能」があります。ただし削除されないことも多いのが現実です。
3)公的な相談窓口を利用
- 警察:悪質な場合は侮辱罪や名誉毀損罪で相談できます。
- 法務局(みんなの人権110番):人権侵害の相談窓口。誹謗中傷の削除を促してくれることも。電話やメールで連絡可能です。
- 弁護士会:インターネット誹謗中傷に詳しい弁護士につないでもらいましょう。
4)法的対応
- 発信者情報開示請求(投稿者を特定する手続き)
- 刑事告訴(侮辱罪・名誉毀損罪)
- 民事訴訟(慰謝料請求)
時間や費用はかかりますが、法的機関を通して声をあげる手段となります。
5)心のケア
誹謗中傷は「言葉の暴力」です。信頼できる人に話す、同じ立場の親とつながるなど、一人で抱え込まないことが大切です。
5.法務局に相談した体験
私自身も、友人に対する誹謗中傷のコメントが削除されないため、**法務局の「みんなの人権110番」**へメールしました。
(電話も選択できます。)
土日を挟んだこともあり、メール送信後4日目に返答が来ました。
担当者は思いによりそってくれましたが、国の機関であるため「表現の自由を不当に制限しないように慎重に審査する必要がある」と説明されました。そのため、基本的には被害者本人や同居の親族からの申し出や聞き取り調査が必要になるそうです。
私のような第三者からの訴えだけでは本格的な対応は難しいと知り、少し残念でしたが、それでも「電話で詳しく教えてください」と言っていただけたことは心強く感じました。

こちらは、私の体験談です。みなさんがご相談された際には、違う回答となる場合があります。
一人で悩まずに気軽に相談しましょう。
★法務省:人権相談
こちらからご相談ください。
6.おわりに:SNS誹謗中傷への対応は「無視」か「法的対応」か
SNSで誹謗中傷を受けたとき、よく言われるのが「無視するのが一番」「メディアに出るというのはそういうこと」という意見です。
発信者を特定したり法的に動くとなると、大きな労力が必要になると言われているからです。
- 弁護士を探す→専門の弁護士を紹介してもらう
- 依頼してやり取りをする
- 着手金や依頼料を振り込む
- 発信者情報開示請求 → プロバイダやSNS事業者とのやり取り
- 裁判で特定しても、直接謝罪がない場合や慰謝料の支払いが難しい場合もある
このように、たとえ相手を特定しても、必ずしも気持ちが救われる結果になるとは限らないのが現実です。
無視するか、法的に動くか。どちらの道を選んでも、誹謗中傷によって受けた心の傷は簡単には癒えない場合があります。けれども、誹謗中傷のコメントを無視するだけでは辛い気持ちは残ります。
ポジティブな意見もネガティブな意見もあることは理解できますが、プライバシーの侵害や侮辱など「人権を侵害する言葉」は許されないのです。
私たち一人ひとりが「これは表現の自由ではなく人権侵害だ」と気づき、支え合うことが大切だと感じています。

誹謗中傷に対して、実際に裁判で戦い、納得のいく結果を得たご家族もいます。
手続きにはどれくらいの時間や費用がかかるのか――そうした体験談がネット上に公開されているので、一度調べてみるのも参考になります。
その方に相談したり事例を知ることで、法的対応を選ぶかどうかを検討しやすくなるかもしれません。
★参考になったらクリックお願いします。応援していただけると嬉しいです
にほんブログ村
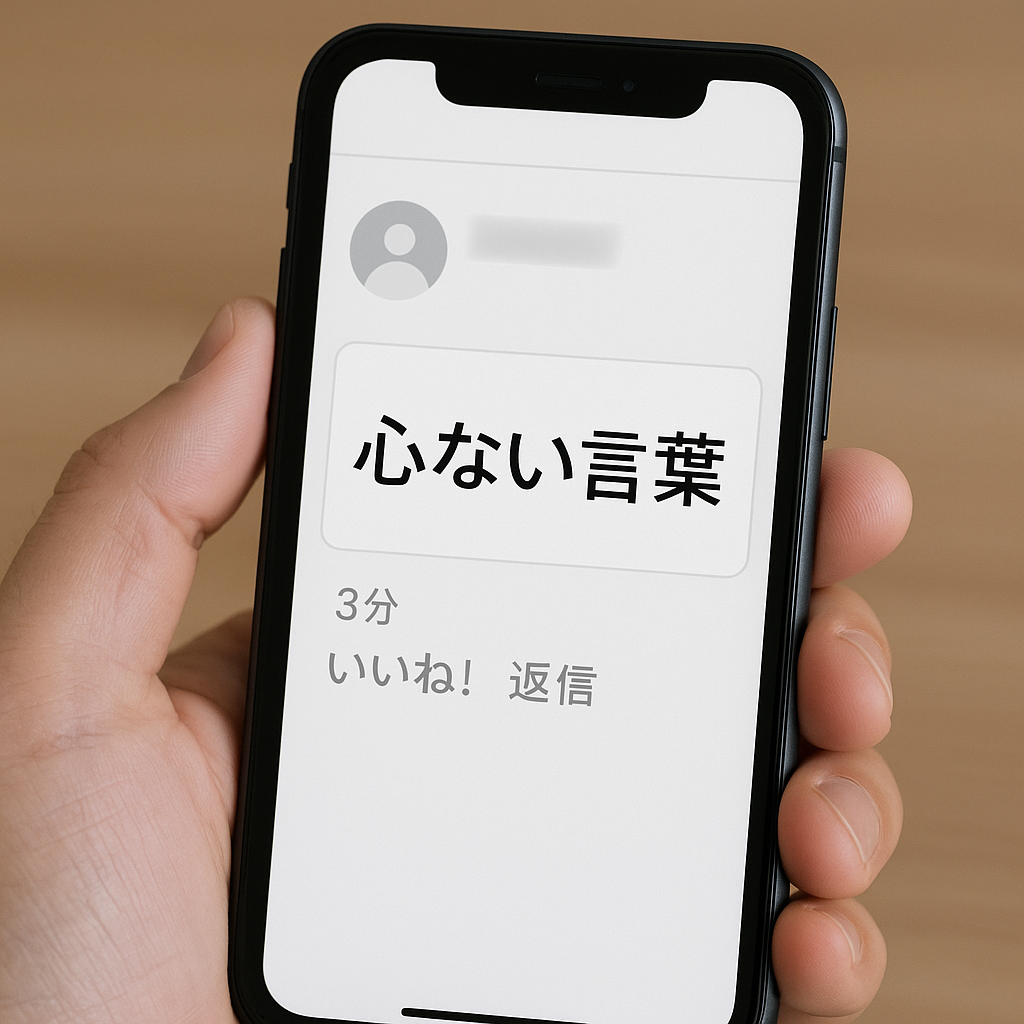
No responses yet