
前回は、お看取りの場所やグリーフケアについてまとめました。
今回は、終末期に関するお話です。
あまり考えたくないテーマですが、終末期は、人生の最終段階に関わる非常に重要な選択の時期です。
どのような医療やケアを受けるのかは、本人や家族の価値観、これまでの生き方、そして望む最期の形によって大きく変わります。
だからこそ、元気なうちから話し合い、選択肢や考えを共有しておくことが大切です。
目次
★こちらもご覧ください★
1.終末期の定義
全日本病院協会のガイドラインより
「「終末期」とは、以下の三つの条件を満たす場合を言います
1.医師が客観的な情報を基に、治療により病気の回復が期待できないと判断すること
2.患者が意識や判断力を失った場合を除き、患者・家族・医師・看護師等の関係者が納得すること
3.患者・家族・医師・看護師等の関係者が死を予測し対応を考えること」
引用:平成21年5月社団法人 全日本病院協会終末期医療に関するガイドライン策定検討会 「終末期医療に関するガイドライン
~よりよい終末期を迎えるために~」

こちらのガイドラインでは、終末期の長さは病気(がん・事故による外傷・難病など)や状況によって大きく異なるため、一律に期間を決めることはできないとされています。
2.終末期にみられる症状
終末期には、次のような心身の変化や症状が現れることがあります。
- 全身倦怠感(体のだるさや疲労感)
- 食欲不振(食べられない、食べたい気持ちが湧かない)
- 便秘
- 不眠
- 意識障害(混乱やもうろうとした状態)
- 日常生活動作(ADL)の障がい(起き上がる・歩く・着替えるなどが難しくなる)
- 精神的・社会的苦痛(不安、孤独感、経済的負担など)
- スピリチュアルペイン(生きる意味や死への恐怖、価値観の揺らぎなど)
- ボディイメージの変化(外見や身体機能の変化による自己イメージの低下) など
こうした変化は人によって出方や進行が異なり、身体的苦痛だけでなく、心・社会・魂の痛みが複合的に関わることがあります。
3.せん妄
せん妄とは、急に起こる意識の混乱で、時間や場所、人の認識があいまいになったり、幻覚や錯覚が見られたりする状態です。
症状は日によって、あるいは一日の中でも変動することが多く、夜間に悪化することもあります。
1)主な特徴
- 注意力・集中力の低下(周囲を気にする、周囲の現状を理解することができない)
- 見当識障害(今が何日で、ここがどこか分からない)
- 幻覚や妄想(幻視が多い)
- 興奮・不穏、または反対にぼんやりして反応が遅くなる
- 睡眠と覚醒のリズムが乱れる など
2)原因
感染症、脱水、薬の副作用、低酸素、代謝異常、環境の変化など、さまざまな要因が重なって発症します。
終末期では身体の機能低下や薬の影響、環境要因によって起こることがあります。
3)頻度
竹下医師・福井医師によると「終末期のがん患者さんでは、その8~9割でせん妄を生じ、さらにそのうち5~7割の方は回復せずに死に至るという報告があります」と書かれています。
引用:西春内科・在宅クリニック「せん妄になると死期が近い?原因や認知症・妄想との違いについて解説」
4)ケア
・原因・リスク因子を探して対処する(便秘→排便処置、低酸素→酸素投与、疼痛→鎮痛剤、不眠→環境調整など)
・できること:危険物を近くに置かない、転倒予防策を行う(ベッドの下にマットを敷くなど)
めがね・補聴器をつける
ゆっくり落ち着いた声ではなしかける
その方の口癖やなじみのある言葉で話す
わかりやすい簡単な説明をする
カレンダーや時計を準備する
家族の写真をかざる
つじつまがあわなければさりげなく説明 など
・家族への説明:せん妄は、どなたにも起こりうる症状です。
意識や会話がはっきりしている時間と、混乱している時間が一日の中で入れ替わることがあります。
一時的な症状であることが多く、必ずしもずっと続くわけではありません。
・家族にできること:
- 穏やかに日常会話をする
- 手を握る、肩に触れるなど、安心感を与えるタッチングをする
- 静かで落ち着いた環境を整える
です。
こうした関わりは、本人の安心感につながり、症状の悪化を防ぐ助けになります。

終末期のせん妄では、点滴や酸素マスクといった医療処置がかえって混乱や不快感を強め、暴れたり危険な行動につながることがあります。そのため、状況によってはこれらの処置を中止する選択がされることもあります。
5)寝たきりとせん妄の違い
| 項目 | 寝たきり | せん妄 |
|---|---|---|
| 主な原因 | 病状の進行、体力・筋力の低下、安静による体力温存 | 脱水、感染症、低酸素、薬の副作用、代謝異常、環境変化など |
| 経過 | 徐々に進行することが多い | 急に発症し、日や時間帯で症状が変動する |
| 症状の特徴 | 動けない・動かない状態が続く | 意識の混乱、見当識障害、幻覚・妄想、不安・興奮または反応低下 |
| 改善の可能性 | 病状次第だが、進行性の場合は難しいことが多い | 原因を特定・除去すれば改善する可能性がある |
| 対応の目的 | 安静・体位変換・褥瘡予防・生活の質を保つ | 原因の治療、環境調整、安心できるケア |
寝たきりは自然な経過ですが、せん妄は対策により症状が落ち着くことがあります。
4.終末期の医療
終末期医療は苦痛緩和や安楽を目的とした医療を行います。
例えば、以下のものがあります。
1)医療用麻薬
- 貼付剤(貼るタイプ)
- 液体の内服薬
- 錠剤の内服薬
- 粉薬
- 注射薬(静脈・皮下注射など)
痛みが強いときには、あらかじめ医師の指示のもとで**患者さん自身がボタンを押して投与量を調整できる方法(PCA:患者自己調節鎮痛法)**が使われることもあります。
2)鎮静(セデーション)
3)酸素投与
4)点滴
水分・栄養を入れるが、むくみや苦痛を増すこともあり、中止されることもある。
5)輸血
貧血や出血に対応するが、体力が低下していると効果が一時的な場合もある。
6)抗けいれん薬や抗不安薬
けいれんや不安・焦燥のコントロール。
7)口腔ケア・褥瘡予防・皮膚ケア・腹部ケア・フットケアなど
医療処置だけでなく、安楽とリフレッシュを目的に行う
5.鎮静(セデーション)
鎮静とは、強い苦痛や症状を和らげるために、薬で意識のレベルを下げる医療行為です。
特に終末期では、がんや難病などで苦痛が強く、ほかの方法では和らげられない場合に行われます。
1)適応となる症状
「鎮静の対象になりうる症状は、せん妄(痴呆に伴うせん妄など臓器不全を伴わないせん妄は除く)、
呼吸困難、過剰な気道分泌、疼痛、嘔気・嘔吐、倦怠感、痙攣・ミオクローヌス、不安、抑うつ、心
理・実存的苦痛(希望のなさ、意味のなさなど)などである。」と書かれています。
引用:苦痛緩和のための鎮静に関するガイドライン2005(p.7)
2)鎮静の種類
会話ができる程度の浅い鎮静、眠るような状態の深い鎮静。夜だけ、家族と面会するときは鎮静をやめるなど間欠的鎮静。ずっと投与する持続的鎮静があります。

眠っている間は患者さん自身で食事をとることはできませんが、鎮静は安楽死ではありません。
あくまでも苦痛を和らげることを目的として行われます。
3)安楽死との違い
| 項目 | 鎮静 | 安楽死 |
|---|---|---|
| 目的 | 苦痛や症状を和らげること | 患者の生命を終わらせること |
| 方法 | 薬で意識レベルを下げる | 薬物などで死に至らせる |
| 生命への影響 | 命を縮めることを目的としない | 生命を終わらせることが目的 |
| 適応条件 | 他の方法で症状が和らげられない場合の最終手段 | 国や地域で法的に認められた条件下でのみ実施 |
| 患者・家族の同意 | 必要 | 必要(法的手続きを含む) |
| 実施される国・地域 | 世界各国で緩和ケアの一環として行われている | 限られた国や地域でのみ合法化 |
6.薬だけじゃない苦痛緩和
緩和ケア普及のための地域プロジェクトでは、
痛み、息切れ、吐き気、便秘、腹部膨満、食欲低下、倦怠感、せん妄、不眠についてのパンフレットを作成しています。
医師や看護師が患者さん・ご家族に説明するときに使用されます。
どのような対処ができるのか等とても分かりやすいパンフレットですので、気になる症状があれば、
医療者にパンフレットについてご確認ください。
医師や看護師など医療者のかたはこちらからダウンロードできます。
緩和ケア普及のための地域プロジェクト パンフレット等[1.患者・家族のためのツール]

たとえば、通常吐き気や便秘には治療薬があります。
しかし、緩和ケアでは、効果がない場合もあり、薬だけでなく患者さんに寄り添い、触れ合うことの大切さも学びました。
こちらのパンフレットには、私が看護師として勤務したり勉強してきた中でも知らなかったことが載っていて、とても勉強になりました。
7.家族へのサポート
緩和ケア普及のための地域プロジェクト「これからの過ごし方について」の冊子をご家族に渡して、医師や看護師が)患者さんの今後の流れを説明することがあります。とても分かりやすい内容なので、ぜひご覧ください。
1)家族の看取りの反応
🔷生理的反応
- 睡眠障害(眠れない、夜中に何度も目が覚める)
- 食欲不振や過食
- 倦怠感、頭痛、肩こり、胃痛
- 動悸や息苦しさ
- 免疫力の低下 など
🔷感情的反応
- 深い悲しみ、喪失感
- 不安、恐怖
- 怒りや苛立ち
- 罪悪感(もっとできたのではないかという思い)
- 安堵感(苦しみから解放されたという気持ち) など
🔷認知的反応
- 集中力や判断力の低下
- 現実感の喪失(まるで夢の中にいるような感覚)
- 故人やこれからの生活に関する思考の反芻
- 将来への見通しが持てない
🔷行動的反応
- 人付き合いの減少、孤立
- 介護や看取りへの過集中
- 泣く、声を荒げる
- 故人の持ち物や写真を頻繁に見返す
- 日課や趣味の放棄

予期悲嘆とは、大切な人の死が近づいていると感じた時点から始まる悲しみの反応を指します。
看取りの過程では、まだ生きている間から次のような感情や行動が見られることがあります。
- 「失うかもしれない」という不安や恐怖
- 先に喪失感を体験してしまう
- 残された時間をどう過ごすかに悩む
- 家族や本人との関わり方に変化が出る(優しくなる、距離を置く など)
予期悲嘆は自然な反応ですが、長く続くと心身への負担が大きくなるため、周囲のサポートや休養も大切です。
2)看護師の関わり(例)
亡くなるまで:適切な情報提供(患者さんの状態や今後どうなるか)、家族の思いを傾聴し心理的に支える、信頼関係を築く、ケアへの参加・助言
亡くなった後:エンゼルケアを一緒に行う、家族の今後の状況を確認(誰かそばにいてくれるのかなど)、家族会・サポートの紹介
8.終わりに
家族として、終末期にどんなことができるのか分からず、戸惑うことも多いと思います。
そんなときは、各地域や医療機関が作成しているガイドブックを参考にしてみてください。
そこにはケアの工夫や声かけのヒントが載っており、大切な人との最期の後悔しない時間をつくる手助けになります。
★参考になったらクリックお願いします。応援していただけると嬉しいです
にほんブログ村


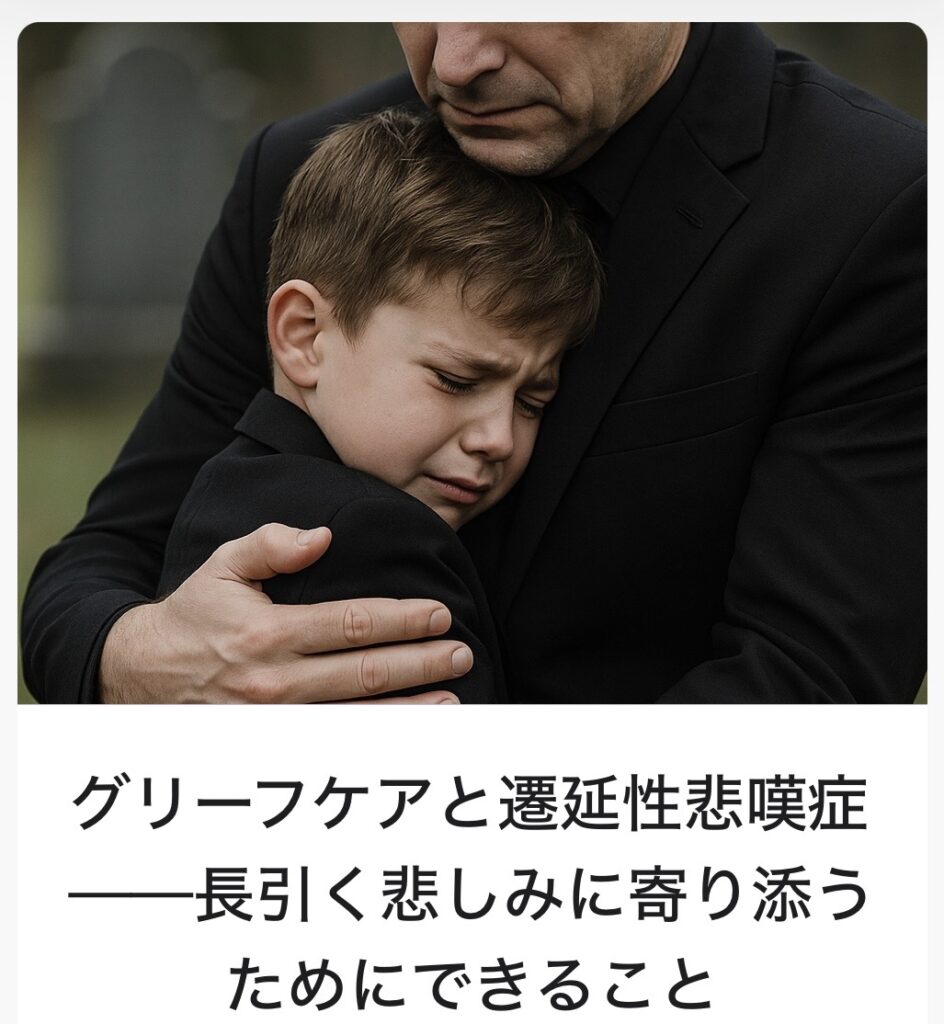
No responses yet