
みなさん、最近暑いですね。
我が家ではついに【soyoマット】を導入しました!
医療的ケア児のママ・パパさんのSNSで
「すごくいいよ!」と話題になっていて、
娘の頭の汗が酷くて困っていた私は、すぐにポチってしまいました。笑
クーラーだけでも大丈夫かなと思ったのですが、
厳しかったようです。
でも──
買って正解でした!
そよマットは、「内部に搭載されたファンが熱を逃がし、
マットの中を風が抜けるような仕組みになっています(公式サイトより)」
引用:快眠マット「SOYO」
ちょいマット・ハーフ・ミドル・シングルなど豊富な種類・サイズがあります

うちの子は、
• 寝返りが打てない
• 頭に汗がかきやすい
• 体に熱がこもりやすい
• 皮膚が弱い
• マットと皮膚がこすれやすい
という状況だったので、皮膚トラブル予防にも!!
この「風が体の下を通り抜ける仕組み」が本当に助かっています。
最初は「風が直接あたって、髪がなびいたりするのかな?」と想像していましたが、
実際には風を強く感じることはなく、ふんわりとした“ひんやり感”があります。
娘もその心地よさで、すやすやと眠ってくれています。
自治体やお子さんの状況によっては”日常生活用具給付事業”の対象となり、
助成を受けられる場合があるそうです。

私は、SOYOマットを購入する前に相談員さんに連絡してみました。すると、保健師さんと連携して、助成の対象になるか確認をしてくれました。
結果として、
私の娘の場合は対象外となり、全額自己負担になりました。それでも、快適さと安心感を考えると価値はあったと思っています。
さて、医療的ケア児を育てていると、
「ほかのご家庭はどんなふうに過ごしているんだろう?」
「うちの子に合う遊びって、どう見つけたらいいのかな?」
「うちみたいに、無呼吸がある子どもはいるのかな?」
──そんなふうに、日々の中でふと疑問や不安が湧いてくることがあります。
そんなとき、
SNSで見つけた“誰かの生活”や“知恵”に救われることがありました。
「みんな、頑張ってる人がいる」 「この工夫、うちでも試してみたい」
SNSは、私たち医療的ケア児を初めて育てるママ・パパにとっても、
心強い味方になってくれるツールです。
今回は、私が実際に使ってよかったと感じたSNSの活用方法を5つご紹介します。
目次
1)励まし合える仲間に出会える
これはもう、いちばんのメリットです。
インスタのストーリーで「朝3時でも起きています」と投稿すると、
フォロワーのママさんが
「私も起きているよ!笑」とメッセージをくれて、
私は涙が出るほど救われました。「うちだけじゃなかった」と。
誰かの投稿を読んで、ただ「いいね」するだけでも
心が軽くなることがあります。
物理的な距離は遠くても、心の距離は近く、
”仲間”のような感覚です。
- 「うちも同じだよ」
- 「今日もがんばったね」
- 「夜中の経管栄養つらいよね…」
身内には言いづらい育児の本音も、
SNSでは素直に言葉にしやすいから不思議です。

同じ病気のお子さんを育てているママさんが、
なんと同じ地域に住んでいることが分かり、
SNSで頻繁にメッセージをやりとりするようになりました。
ある日、通院先の病院でばったり再会!そんな偶然にも感動しました。
そのときに一緒に撮った写真は、
今でも宝物のような一枚で、一生の思い出になっています。
2)病気やケアに関する情報が得られる
「嘔吐するのは、うちの子だけ…?」
「いつから笑顔が見れるの?」
「胃管は、いつから6Frに変えたらいいの?」
医療的ケア児の育児では、病気の小さな変化に戸惑ったり、
成長にあわせてケアの見直しが必要になることがよくあります。
そんなとき、SNSで見つけた「同じような経験をしてきたご家族」の声に、
何度も励まされ、助けられてきました。
たとえば──
・「うちも嘔吐があったけど、ミルクをE赤ちゃんに変えたらよくなったよ」
・「うちは半年ごろからしっかり笑うようになったよ。これから楽しみだね」
・「まだ6Fr使っているよ」など
病名や症状、使っている医療機器が似ているご家族とつながれることで、
病院ではなかなか聞けなかった“実践的な知識”や
“ちょっとした工夫”を知ることができます。


娘の嘔吐がひどくて悩んでいたとき、ママ友さんが
「E赤ちゃんは、消化にやさしいミルクだよ」と
教えてくれました。
ミルクを変えてみると、消化も早くなり、
娘にも合っていました。
しかも缶ミルクより軽くて、持ち運びにも便利。
お出かけのときも助かっています。
3)遊びや日常生活に役立つ情報も見つかる
病気やケアのことだけでなく、
**「子どもとどう楽しむか」**も大切な毎日のテーマです。
SNSでは、こんな工夫や体験談にもたくさん出会えます。
- 「シーツの両端を持って、寝たままブランコみたいに揺らすと、楽しんでいるよ。
いつも子供や夫と一緒にゆらゆらして遊んでいるよ。」 - 「”しなぷしゅ”をずっと見てるよ」
- 「家族で行けたバリアフリーの水族館、最高だった!」
- 「〇〇の医療的ケア児のイベント行くので、見かけたら声をかけてください!」など

SNSを通じて、「みんな工夫しながら楽しんでるんだ」と分かり、
参考にしたり、
「私たちも、もっと楽しいことにチャレンジしてみよう!」
と前向きな気持ちになれました。
また、児童発達支援の公式アカウントや、
医療的ケア児向けのイベント情報もSNSで流れてくるので、
そこからイベントを見つけることができています。
実際の活動の様子が写真や動画で紹介されていることも多く、
児童発達支援の雰囲気がわかったり、参加のハードルがぐっと下がったと感じました。
「NPO AYA」さんは、様々な地域で医療的ケアがあっても
安心して参加できるようなイベントを開催している団体です。
たとえば、「普段は映画館に行くことを遠慮している方でも、
気兼ねなく映画を楽しんでほしいという想いで
誰でも見れる”インクルーシブ映画上映会”」を開催されています。
私はインスタでフォローして随時イベントをチェックしています。
引用:NPO AYA
他にも医療的ケア児が参加できる団体さんもたくさん見つかりましたが、
地域に根ざして活動されているケースが多いと感じました。
そのため、「〇〇県 医療的ケア児 イベント」「〇〇県 ホスピス」など、
地名を入れて検索すると見つかりやすいです。
私も実際にその方法で、近くのイベント情報を見つけることができました。
4)出会える、支えになる「もの」
◉素敵なアイテムとの出会い
SNSで知ったハンドメイド作家さんが、
娘のサイズに合わせて 特別に洋服を作ってくれたことがあります。
SNSで直接やりとりができたので、
「着やすい&可愛い」洋服が届きました。
こまめにやりとりをしながら作ってくれたので、相談して本当によかったなと
思っています。
◉ちょっとした収入や気分転換に
アメブロではアフィリエイトやPR案件にも応募できます。
「たいしたブログではないけど当選しました!」という声も。
新しい商品を試せたり、読者の反応をもらえたり。
ケアの合間に、ほんの少し自分の世界が広がる時間になりました。
5)記録として残せる
私は最初、手書きの育児ノートに日々の様子を記録していましたが、
徐々に書く時間が無くなったり、書きたい内容を忘れたりすることがありました。
今はスマホでの記録のほうが手軽で、すぐに見返せるので便利だと感じています。
たとえば──
・Instagramでは、
写真+ひとことコメントでその日の出来事を記録
(イベント参加日や体調の変化、受診の記録など)
・アメブロでは、育児日記として、
気持ちの整理もかねて文章で残しています(呼吸器の練習の様子など)
・X(旧Twitter)やThreadsは、たわいもないことをつぶやいています。
ぜひお友達になっていただけると嬉しいです!

SNSは、誰かと情報をシェアするだけでなく、
“あとから自分が見返す”ためにもとても便利だと気づきました。
たとえば診察のとき、医師から「この薬、いつ始めた?」
「前回の入院はいつだった?」と聞かれても、SNSを見ればすぐに確認できます。

「この日は動物園に行って楽しかったな」
「ここから体調が悪くなってきたかも」
そんな記録が、自分自身の思い出となり、
ふとしたときに自分を励ましてくれる大切な記録にもなっています。
使い分けしよう!SNS別のおすすめ活用法
| SNS名 | 特徴 | おすすめ活用法 |
|---|---|---|
| 写真や動画がメイン。共感・交流しやすい | ケアグッズ・日々の暮らしを共有・記録に◎ | |
| X(旧Twitter) | 短文で気軽につぶやける。タグ検索が便利 | リアルタイム情報・緊急性のある情報共有に◎ |
| アメブロ | 長文で自分の気持ちを振り返ったり、日記形式に向く | 育児記録・アフィリエイト・心の整理に◎ |

使うSNSは違っても、それぞれに心強いお友達ができて、
本当に救われています!
💡SNSの注意点:自分のペースで、取捨選択を
SNSは便利ですが、 情報の量が多いからこそ
「見すぎない・信じすぎない」ことも大切。
- 他人の育児スタイルと比べない
- 自分の思いや気持ちに合わない情報はスルーしてOK
- 様々な考えがあるけれど、“それは一部”であって全てではない
疲れたり落ち込んだら、スマホを閉じて休んで。
“自分らしいSNSとの距離感”が、きっと見つかるはずです。

SNSには、同じような病気の子の情報がたくさん流れてきます。
「この薬で効果があった」「手術してよかった」
そんな声を見ると、心が揺れます。
「うちはこのままでいいのかな?」
「同じ薬を使えばよくなるんじゃないか?」
たとえ主治医と納得して決めた治療方針でも、他の子と比べて不安になることもありました。
★こちらもご覧ください★
おわりに
SNSは、顔が見えなくても、気持ちがつながる場所です。
「今日ちょっとしんどかった」 「このグッズ、よかったよ。みんなも試してみて」
「これからも、一緒にがんばろう」
そんな声が誰かの心を支え、明日の自分も支えてくれる。
SNSを、あなたらしく、やさしく使っていきましょう。
なにか、ひとつでも”我が家らしい生活のヒント”になることがありますように。
★この記事が参考になったらクリックお願いします。応援していただけると嬉しいです
にほんブログ村

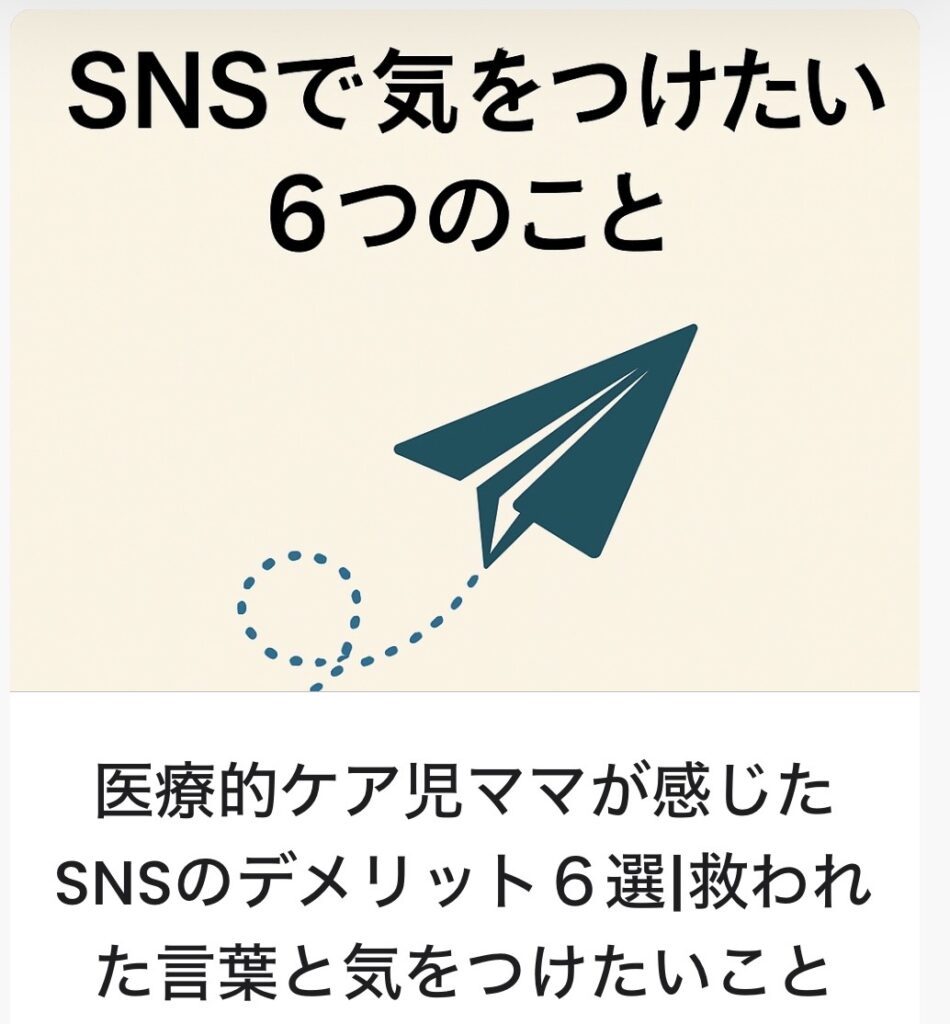
No responses yet