
SNSで目にした投稿に驚きました。
「昔の母子手帳には『障害児を産むな、育てるな』と書かれていた」。とありました。
添付画像にはたしかに、母子手帳の表紙にそのようなこと記載があったのです。
ただ、戦争が起きる前の時代には、障害児に対して現在のような差別的な表現は多く見られなかったそうです。
今回は、戦後80年という節目にあたって、「障害児と社会の歴史」について改めて調べてみました。
過去の記述や考え方を振り返ることは、未来をよりよいものにしていくための第一歩だと思います。
※万が一、事実と異なる点がございましたら、お手数ですがご指摘いただけますと幸いです。
1.「日本の障害者の歴史」より
今回、古代から中世までの障害者の歴史について調べるにあたって、花田春兆 さんの「日本の障害者の歴史―現代の視点から―」を特に参考にさせていただきました。
1)花田春兆さんについて
花田春兆さんは、
・障害者の歴史をはじめてしっかりと調べてまとめた人の一人です。
・脳性麻痺があり、話すことや歩くことが難しい障害がありましたが、日本で最初の肢体不自由児のための学校「光明学校(今の都立光明特別支援学校)」に通いました。
・その後、仲間と一緒に作った文芸雑誌『しののめ』では、詩や文章を通じて気持ちを伝えるだけでなく、障害者の思いや権利を社会に訴える活動も行いました。
・この活動がきっかけで、「青い芝の会」など多くの障害者の団体が生まれていきました。
・花田さんは、多数の本や論文を執筆しており、社会をより良く変えていこうと努力し、多くの賞も受けています。
参考:岡本明「文学にみる障害者像」『ノーマライゼーション 障害者の福祉』2011年9月号、日本障害者リハビリテーション協会
2)古代から中世の日本

実は戦前までは、障害児は必ずしも否定的に見られていたわけではありません。
詳しくはこちらをご覧ください★
出典:
花田春兆(1987)『日本の障害者の歴史 ―現代の視点から―』リハビリテーション研究、第54号、pp.2-8、公益財団法人日本障害者リハビリテーション協会
・昔、「障害児が生まれるとその家は栄える」という言い伝えがありました──
これは「福子伝説」とも呼ばれ、障害のある子どもが生まれると、「この子が将来困らないように」と家族全体が力を合わせて働くようになり、その結果として家庭が繁栄する──そんな姿を見た周囲の人々が「この子は福を呼ぶ」と感じたことが由来とされています。
・奈良時代には障害者に対する減免措置(租税や労役の免除など)がとられていたことが知られています。これは、障害を持つ人々を支える文化や制度が、すでに当時から存在していたことを示しています。
3)仏教の影響
鎌倉・室町時代(中世)にかけて仏教が庶民にも広まり、障害観にも影響が与えられました。
特に仏教の中心的思想である「因果応報(いんがおうほう)」。

この教えは次第に「今、障害があるのは、前世で悪いことをしたからだ」といった形で障害を“罰”のように捉える偏見に利用されていきました。
一方で、「悪い行いをすれば悪い報いが、善い行いをすれば善い結果がもたらされる。」という教えもあり、
仏教寺院が障害者や貧困者を保護・救済する制度を整えていた時代もありました。
4)明治時代
明治政府は「富国強兵」や「文明開化」を推進し、国民に健康で勤労可能な身体を求めるようになりました。
その中で、障害者は「労働力にならない」「国家の負担」とみなされ、施設に隔離・収容される傾向が強まります。
さらに、のちに「優生思想(※障害を“劣ったもの”とする思想)」が加わり、障害者を「社会から遠ざける」流れが加速しました。

ただし、成人障害者が施設に入れられる一方で、子どもの障害は家庭の“責任”とされ、母親が一人で抱え込むケースが一般的でした。
家の中で「隠される」「外に出さない」「教育の対象にならない」など、**「家の恥」**という風潮もありました。学問を受ける機会もありませんでした。
しかし、1878年(明治11年)京都にて 「盲唖院(もうあいん)」 設立されました。
これは、視覚・聴覚障害の子どもたちに教育を行う、日本初の公的施設です。
なぜ設立されたかというと、
- 明治~大正期になると、都市化・近代化が進む一方で、**教育を受けられない子どもたち(特に障害児)の存在が“社会的な課題”**として見えるようになってきました。
- 当時の日本は、ドイツやアメリカなどから特別支援教育(特殊教育)の概念を学び取り入れつつありました。
- 欧米では障害があっても学ぶべき、働くべき、社会に参加すべきという考えが生まれており、日本でもその影響が波及していました。
- そして、「読み・書き・計算(そろばん)」などの基礎教育が可能と見なされた視覚・聴覚障害者は、**職業的自立(あんま師・手工業など)**が期待されていた背景もあります。
- 当時の社会的価値観では、**「教育すれば働ける人」**が優先されやすかったのです。
一方で、「国民すべてに教育を」とする明治期の学制改革の理念がありましたが、障害児は対象外とされがちでした。
- 肢体不自由児は、「働けない」「教育しても意味がない」とされていたため、長らく教育の対象にされませんでした。
- しかし、「障害児も国民の一員である」という考え方から、“公立”で教育の門戸を開く必要があるという動きが始まったのです。1904年東京市立光明学校の設立には、実際に障害児を抱える家庭や医療関係者、教育者の働きかけがありました。こうした民間の声が、行政を動かし、「公立」で身体障害児の教育が実現したのです。

「障害があっても、教育を受ける権利がある」という理念のもと、公立で設立されたのは当時としては画期的でした。
子どもたちが家庭から外に出て、“人として学ぶ”機会を得たことで、社会の見方にも少しずつ変化が現れます。
5)戦時中
1940年代、日本が戦争状態に入ると、社会の基準は「国のため」と変化します。
産業や戦弾製造に役に立たない、成長の要求に従えない障害者は、公然に「不要」とされるようになりました。
当時のドイツ(ナチス)などの影響も受けて、日本でも「健常な子を産み、育てることが国益」という思想が広まりました(優生思想)。
6)戦後
戦後の混乱と経済的困窮の中で、障害者と家族はますます孤立していきました。
戦時中の優生思想が引き継がれ、
・1948年には「優生保護法」が制定され、障害や疾患があると診断された人に対して、本人の同意なしに不妊手術が行われるという重大な人権侵害が長く続きました(1996年に廃止されるまで約50年続行)。
・母子手帳(かつての「妊産婦手帳」)にも、
「遺伝性の病気がある場合は妊娠・出産を避けるように」
「障害のある子は産まない・育てないほうがいい」といった、優生的な内容が記載されていた時期がありました。
これらは行政の名のもとに、家族や医療者に「障害のある子を排除する判断」を促すようなものでした。
しかし、1947年の教育基本法・学校教育法の整備により、すべての子どもに教育を保障する流れがつくられました。その延長として、障害のある子どもも対象に含まれていきました。
7)障害者運動がおこる
「日本の障害者運動には、「最も身近な敵は親である」という主張があった。障害者の親は、「我が子が世間に迷惑をかけないように」と思い詰めて、子どもを自分一人で抱え込んでしまうことがある。そうした義務感が、 「この子を残して死ねない」というかたちに高まって、親子心中や障害児殺しという最悪の結末になることもあった」
引用:荒井裕樹 黙らなかった人たち――理不尽な現状を変えることば 第12回 2019年
施設の中で隔離された障害者たちは、自立と解放を求め運動をおこしました。
また、国際的な動きもありました。
・1981年:「国際障害者年」→ 世界中で、障害のある人が社会に参加する権利や平等な扱いについて考えよう、行動しようという呼びかけ。これをきっかけに、日本でも障害者福祉や雇用、バリアフリーなどに対する関心が少しずつ高まりました。
2.現代の変化

国際障害者年の影響はとても大きく、障害のある人も**“市民の一員”として生きる権利がある**という認識が広まり始めました。守られるから共存する社会へ
・18トリソミーなど重い障害や病気を持つ子どもに対しては、「延命治療しないことが優しさ」と言われ積極的な治療がされなかった過去がありますが、現在は「個々の状態」に合わせて、家族と相談しながら治療が行われています。
・2013年障害者総合支援法により障害者=施設で隔離ではなく、地域で暮らせるように居宅支援を拡充
・「ノーマライゼーション」や「統合教育」「インクルーシブ教育」という考え方が徐々に紹介されるように
★こちらもご覧ください★
3.おわりに
社会の歴史を見ると、障害者は「福の存在」として生かされた日もあれば、「社会に迷惑な存在」として隔離された日もありました。
障害のある子どもたちも、そしてその家族も──
我慢して家に閉じこもるのではなく、社会に参加し、自分らしく「やりたいこと」ができるような社会へ。
私たちの今が“完成形”ではありません。
小さな一歩でも、自ら動くことで未来は変えられます。
誰もが安心して暮らせる、より良い社会をみんなで一緒につくっていけたらと願っています。
★こちらもご覧ください★
★参考になったらクリックお願いします。応援していただけると嬉しいです
にほんブログ村

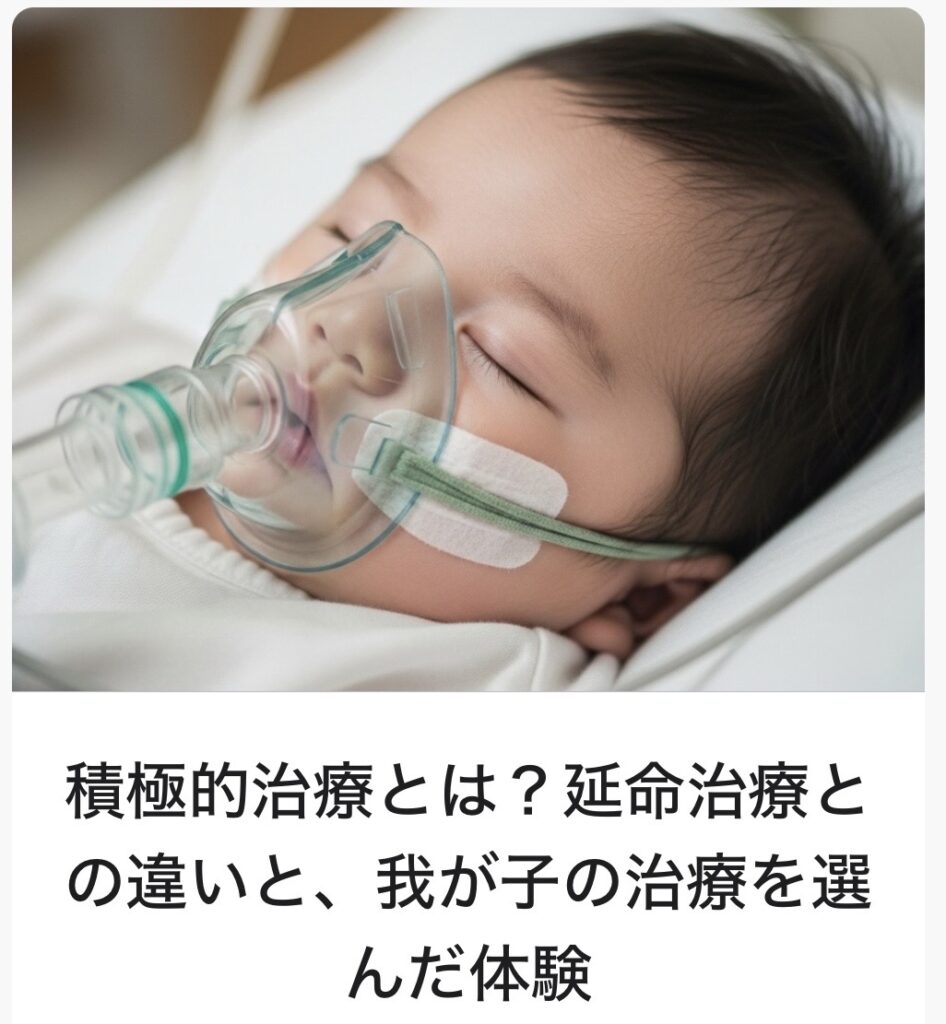

No responses yet