「私じゃなきゃダメ」と思ってた私が、娘の笑顔で気づいたこと

みなさんのお子さんは、「児童発達支援」「デイサービス」「レスパイト」などを利用したことがありますか?私は”自分がそばにいないとこの子の命は守れない!”と考えてなかなか利用できませんでした。
そんな私が「自分自身と子どもの自立」について考えたことを綴ります。
目次
1.子どもと母親の一体化
大人になると、褒められることは減っていきませんか?
何をしても「当たり前」で、娘のために頑張るのも、当然のように受け止められる。
私自身がどれだけ疲れていても、大変でも、
親として、私は娘のことを第一に考えて行動しなければいけない。
いつしか私は「〇〇ちゃんのママ」としか呼ばれず、自分の名前を最後に呼んでもらえた時っていつだっけ?と思いました。
「ごはん食べましたか?」──娘の話。
「よく眠れましたか?」──それも娘のこと。
「今日も元気ですか?」――もちろん母親自身のことではない。
徐々に“娘のママ”としての私しか見られていない気がして。
でも、たぶん一番”私自身”を見失っていたのは──私だったんだと思います。
2.親だけにしか子どもは守れない?
娘のことを誰よりも知っているのは、一番そばにいる親です。
娘は病状が不安定。自分で言葉にして訴えることはできないから、
私がそばにいないとだめなんだ。
娘のことは、私にしかできない。
呼吸の変化、吸引のタイミング、わずかなサイン──
それを読み取れるのは、私しかいないと思い込んでいました。
だから、誰かに任せるのが怖かった。
デイサービスやショートステイをすすめられても、
「そんな無責任なことできない。何か起きたらどうするのか」と、拒否していました。

「レスパイト」を勧められるたびに、嫌な気持ちになりました。
「なんで勧めるの?私はいま、娘と一緒にいるのが幸せなのに。」と不思議に思いました。
たしかに、大変なこともあります。
でも、私が「休みたい」と思っていないのに、
“休め”とすすめられると、かえって傷つきます。
「私はダメな母親なのかな」
「弱いって思われてるのかな」
そう思ってしまう日もありました。
善意って、押しつけられると、少し嫌なものになります。
3.娘の成長
でもある日、娘が訪問看護師さんに笑顔を向けている姿を見ました。
読んでくれる絵本に夢中になっているその表情は、
私には見せたことのない、いきいきとした顔でした。
そのとき、私はハッとしたのです。
「この子に依存していたのは、私の方だったのかもしれない」と。
「娘のことを一番理解しているのは、私」
「私が娘を守らなきゃ」
そう強く思い込み、
いつの間にか、”娘は私の一部”として見ていたことに気づきました。
そして「私がこう思うなら、きっと娘もそう感じている」──
そんなふうに、知らず知らずのうちに決めつけていたことに気づきました。

娘はゆっくりだけれど、確実に成長しています。
最近はなんと一人で遊ぶようになりました!
だから私も、いつまでも娘を“赤ちゃん”としてではなく、
一人の人間として、向き合っていこうと思いました。
親として、そっと見守りながら、
娘の成長を支えていきたい、いろんな経験をして人生をもっと楽しんでほしい──
そう思えるようになったのです。
4.子どもの発達段階

みなさんは、「エリクソンの発達段階」について聞いたことがありますか?
私は、高校や看護学校のときに勉強しました。
エリク・エリクソンは、発達心理学者で、人が成長するうえで乗り越えるべき心理的・社会的なテーマや課題(発達課題)を示しました。
0〜1歳:「基本的信頼 vs 不信」
発達課題:「世界は安心できる場所だ」と思えるかどうか。
親のかかわり方は、安心感を感じさせることがポイント
- 泣いたら安心感を与える関りをする(スキンシップ・声かけ)
- 母乳やミルク・抱っこ・表情で愛情を伝える
- 一貫した養育者との関係(できれば同じ人とのふれあい)など
▶ポイント:
「あなたは大切だよ」「ちゃんと見てるよ」と安心感を積み重ねることが信頼形成につながります。
1〜3歳:「自律性 vs 恥・疑念」
発達課題:「なんでも自分でやってみる」体験が、自信につながる。逆に、失敗ばかりを責められると、「やってはいけない」と萎縮してしまう
親のかかわり方は、安全な範囲で「やってみる」ことを見守る
- 「自分でやろうとしている」ことを見守る
- 胃管を引っ張る様子があれば、紐などの代用方法を考えて遊ぶ(安全のため必ず見守りで)
- 危なくない範囲で自由に選ばせる
▶ポイント:
「あなたならできるよ」と信じて見守る姿勢が、自己肯定感を育てます。
3〜6歳:「自発性 vs 罪悪感」
発達課題:「自分で考えてやってみよう」と思える主体性を育てられるか。「これをやりたい!」という気持ちを認められると、自ら行動する力が育つ。反対に、「ダメ」と否定され続けると、罪悪感を感じやすくなる。
親のかかわり方は、何を考えているか気持ちを考える。自分で考えるように促す
- 児童発達支援などに通い、好奇心を尊重し、遊びや創造活動を拡大
- できたことを褒める(過程も◎)
- 失敗しても人格を否定しない(叱るより理由を話す)
▶ポイント:
「やってみたこと」を大事に受けとめると、自信や意欲につながります。
6〜12歳:「勤勉性 vs 劣等感」
発達課題:「努力すればできる」と感じられるか。
親のかかわり方は、子どもの努力を伝える
- 毎日学校に行くことや、生活面の小さな努力を認めて声かけ
- 他の子と比べず、その子なりの成長を見守る
- 適度なチャレンジ課題を用意して成功体験を増やす
▶ポイント:
「努力すれば成果が出る」という経験が、将来の挑戦力を支えます。
5.たくさんの人と接するメリット

医療的ケア児も、「自分でやってみたい」という気持ちはちゃんと育っています。
でも、ケアや制限が多くなるぶん、「やらせるのが怖い」「手伝いすぎてしまう」「何をやらせてあげればいいか分からない」ということが起こりがちです。
レスパイト入院
レスパイトの利用には、はじめは抵抗がありました。
「私が頑張ればいい」「まだ休んじゃいけない」──そんなふうに、自分を追い詰めていたのです。
でも、ある日ふと思いました。
**「レスパイトって、私のためだけじゃなく、娘のためにもなるんじゃないか」**と。
たとえば、私が突然、育児やケアができなくなったとき。
娘は一時的にレスパイト入院をすることになるかもしれません。
そのとき“初めて”利用するよりも、あらかじめ少しずつ経験して慣れておく方が、娘も安心して過ごせるはずです。
他の人と関わること、違う空間に身を置くこと。
それは、私たち親子の**「気づきのきっかけ」**にもなります。
うまくいかなかったとしても、「どうすれば娘が心地よく過ごせるか」を医療スタッフと一緒に考えていけます。

私の住む地域では、最近、医療的ケア児がレスパイトでお泊まりできる施設ができました。
対象は3歳からですが、小学生の子どものリピーターが多いそうです。
日中は同年代の子どもたちと一緒に遊び、夜になるとそれぞれ自分の部屋で過ごすというスタイルです。
この施設の特徴は、「親の休息のため」だけではないという点。
この取り組みには、**子どもの発達段階に応じた“成長の機会”**をつくるという意図もあるそうです。子どもたちも生き生きと楽しみながら過ごしているそうです。
児童発達支援・保育園
児童発達支援では、娘と同じような医療的ケアが必要な友達と出会えます。
保育園では、健常なお子さんと関わることで、戸惑いや驚きもあるかもしれません。
でも、その一つひとつの出会いや出来事が、**娘の“可能性を広げる種”**になると信じています。
失敗すること・悲しい思いをすること
娘には、もっとたくさんの楽しい経験をしてほしい。
「挑戦する」「感じる」。そんな中で、好きなことを増やしてほしい。
一方でときには、「できないこと」に直面することもあります。
でも、それは「環境を整えるヒント」が見えたということ。
できないことがわかるからこそ、できることが増えていく。
他の子どもと関わる中で刺激を受けて、工夫して、
”自分もできる”と、少しだけ頑張ってみようとする姿も見えてくる。
子どもって、大人が心配しすぎなくても”子ども同士”でも支え合って、友情もゆっくり育っていくんだと思います。
6.医療的ケア児の「自立」とは
医療的ケア児でも「自立」はできるのでしょうか。
「自立」とは、決して”親から離れる””突き放して自分で何でもできるようにする”ことではありません。
**「自分の人生を、自分らしく生きる力」**を育てること。
たとえば──
「楽しい」「嫌だ」「気持ちいい」などの気持ちや行動を、自分で見つける。他者に伝える。
ママ以外とでも安心して楽しく過ごせる時間がある。
子どもにとって新しい発見や可能性が広がる、”充実した人生”につながります。
7.おわりに

医療的ケア児の親は、責任感がとても強いと言われています。
心から安心してお任せできる場所や人と出会えたら、
きっと生活もよりいい方向へと変わっていきます。
何でも子どものことをやっていた時期から徐々に変わって
親は、だんだんと「見守る」側にもなります。
大切なのは、親がすべてを抱えこまないこと。
子どもが自分のペースで、世界を広げていけるよう、
少しずつ“私の手”をゆるめていくことだと、今は思っています。
そして私自身も、少しずつ「娘のママ」から「一人の私」へと、戻っていけたら──
それもまた、親としての“自立”なのかもしれません。
★この記事が参考になったらクリックお願いします。応援していただけると嬉しいです
にほんブログ村
★こちらもご覧ください★

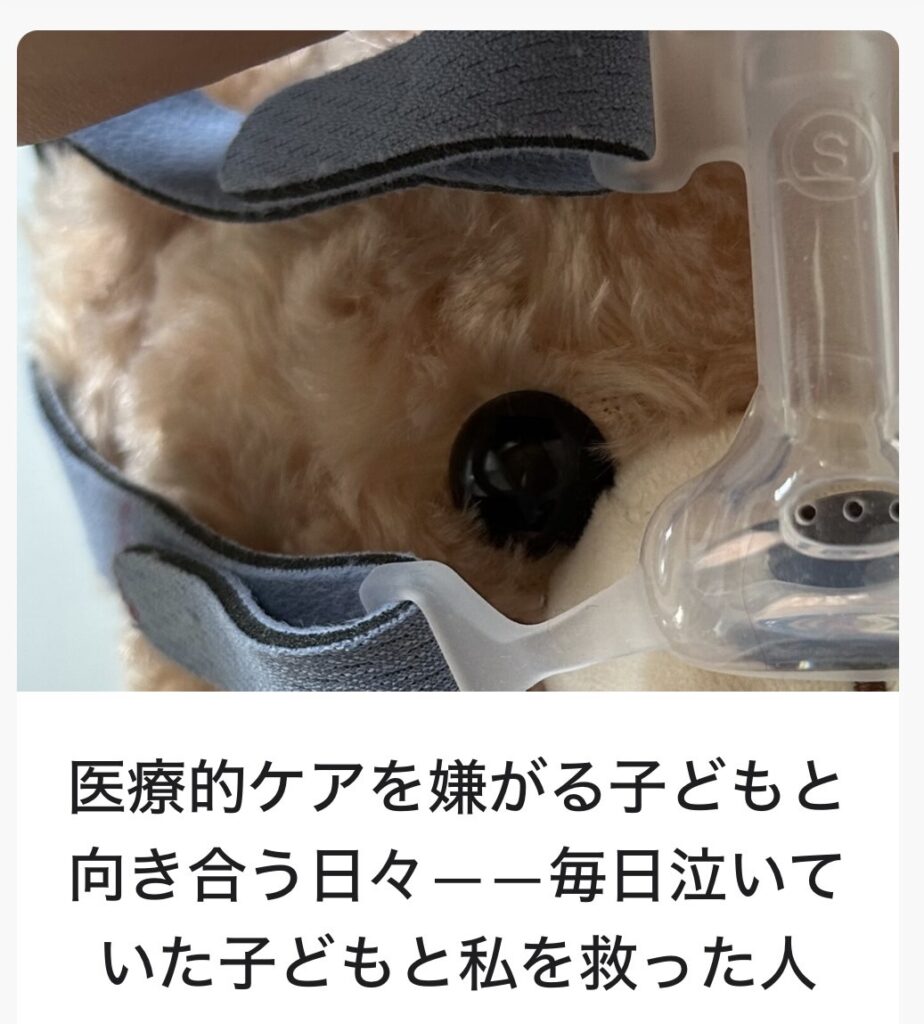

No responses yet