今回は、”医療的ケア児のきょうだい”に関して厚生労働省の調査によって分かったリアルな声を整理してみました。
※本記事の一部は厚生労働省資料(p.83-84)令和元年 医療的ケア児者とその家族の生活実態調査
報 告 書を参考に、AIの力を借りて構成しています。
目次
1.きょうだい児とは?
”きょうだい児”とは、障害や病気のある兄弟姉妹がいる子どもを指す言葉です。
厚生労働省などでは明確な定義はありませんが、多くの支援現場や学術界で広く使われています。
2.なぜひらがな?
「きょうだい児」という言葉を目にしたとき、「なぜ“ひらがな”で書くの?」と不思議に思いました。
この理由を調べてみました。
1. 性別を限定しないため
「兄弟」や「姉妹」という漢字には、それぞれ性別のイメージがあります。
- 兄弟=男のきょうだい
- 姉妹=女のきょうだい
ですが、病気や障害のある子どもをもつすべてのきょうだいが対象ですので、男の子・女の子に関係はありません。
そのため、性別にとらわれず中立な言葉で、「きょうだい」とひらがなで表すようになりました。

文部科学省の定める「常用漢字表」では、「きょうだい」の正式な表記は“兄弟”のみとされています。
しかし、日本語には「兄弟」「姉妹」「兄妹」「姉弟」などさまざまな漢字表記があり、
日常的にはどれも“きょうだい”と読まれています。
2.当て字の混乱を避けるため
漢字で表記しようとすると、どの組み合わせが正しいのか迷うことがあります。
- 「兄妹」?「姉弟」?「兄弟」?「姉妹」?
読者によって受け取り方が異なり、混乱を招くこともあるため、あえてひらがなで統一することで、わかりやすく・やわらかい印象にするという配慮があります。
3. やさしく、親しみやすい印象に
「きょうだい児」という言葉は、時に見えにくくなりがちな存在に光を当てるために生まれました。
だからこそ、子どもたち自身にも、まわりの大人たちにも伝わりやすく、やさしく響くように、ひらがなが選ばれているのです。
このように、「きょうだい児」という言葉には、性別への配慮や、わかりやすさ、やさしさが込められています。
見過ごされがちな“きょうだい”たちの存在に、社会がようやく目を向け始めた証とも言えるのではないでしょうか。
3.「きょうだい児」という言葉は誰が作ったの?
「きょうだい児」の名づけ親は調べてみましたが、明確には出てきませんでした。
- 「医療的ケア児」「障害児」「難病児」と同じように、「〜児」という形で支援対象として可視化しやすくなる
- 「兄弟」や「姉妹」では性別を限定するため、ひらがなで中立的に表記する言葉が必要だった
などという背景があり、現場や研究・支援の中で自然と「きょうだい児」という言葉が定着していったという考えがあります。

それでは、ここから前回と同様に、厚生労働省の調査に基づき
”きょうだい児”の大変さについてまとめていきます。
4.調査から分かった医療的ケア児のきょうだいの大変さ
1.家族と自由にゆっくり外出ができない
- 時間や場所を気にせず遊びに行きたい。旅行にも行きたい。
- 親の送迎が必要な習い事ができない。
- 家族みんなで、お母さんとおでかけしたい。
- 医療的ケア児が行けるときは一緒におでかけしたい。
- バギーが無理な場所があって行き先が限られる。
- 外出しても医療的ケアのお世話で親が大変で落ち着けない。
2.医療的ケア児ばかり優先されるように感じる
- ひとりぼっちで後回しにされる。体調が悪い時も放っておかれる。
- 医療的ケア児ばかり可愛がられて、自分は怒られることが多い。甘えたくても甘えられない。
- アラームが鳴ると親が飛び出していくので落ち着かない。
- 用があって呼んでも、医療的ケア児の世話を優先される。
3.親と過ごす時間がほしい
- お母さんと遊びたい。ゆっくり話したいが聞いてもらえない。
- 出かける約束が体調不良などでよくキャンセルになる。
- お母さんが時間に追われていて、一緒にゆっくりした時間を過ごせない。
4.ストレスや我慢がたまる
- たくさん我慢していることがあると感じる。
- 医療的ケア児の泣き声が続くとストレスを感じる。
- 友達に医療的ケア児をばかにされ、心無い言葉でストレスを感じる。
- 医療的ケア児ではなく自分ばかり注意される。
- 母親に言いたいことやお願いしたいことが言いづらい。
- 医療的ケア児の苦しそうな姿を見るのは辛い。
5.さみしさがある
- 両親が忙しくてかまってもらえずさみしい。
- 付き添い入院で母親がいなくなり、自分は祖父母に預けられるのが嫌だ。
- 自分も病院のつきそいで、週末が過ぎることがある。
- 医療的ケア児の学校行事にはいくのに、自分は来てもらえない
6.その他:将来への不安・生活の制限
- 将来、自分が面倒をみるのか不安がある。
- 医療的ケアのお手伝いが大変。自分が家を出たら、両親の負担が大きくなるので心配。
- 友達を家に呼べない。
- 両親がいつも疲れて寝ているのが嫌。
5.最近のきょうだい児へのサポート
きょうだい児のいる友人に話をきくと、きょうだい児に配慮したサポートが増えてきているそうです。
例えば、
●障がい児と医療的ケア児、家族とみんなで一緒に楽しめるイベントが開催されている。
●サービスを活用することで、きょうだい児と自宅や外出先で一緒に遊ぶ時間が確保しやすくなっている。
●偏見をなくすように、学校で障がい児や医療的ケア児の授業、親が伝える場がある。
●医師がきょうだい児にもわかりやすいように説明したり、困っていることがないか声をかけてくれることがある。
まだ地域差はありますが、少しずつ社会も変わってきていると感じます。
私たちも、子どもたちの声にもっと耳を傾けながら、
きょうだい児にとっても「自分は大切にされている」と感じられる環境や、地域のつながりを大切にしていきたいですね。
6.我が家の将来設計
◇我が家にはきょうだいがいません
私たち夫婦にとって、いまの子どもが初めての子どもです。
医療的ケア児であるこの子の育児だけでも、正直毎日が精一杯です。
そんな中で、「きょうだいを持つこと」についてもたびたび話し合ってきました。
◇きょうだい児への不安と葛藤の声
私自身もSNSや書籍などを通して、
「医療的ケア児がいるのに、きょうだいを作るのはかわいそう」
「これ以上、子どもに負担をかけたくない」
「親の時間も体力も足りない。きょうだいに“我慢”ばかりさせてしまうのではないか」
──そんな声をたくさん目にしてきました。
また”きょうだい児”から、どれほど寂しく、大変だったかという体験談もたくさん見ました。
どれもまっすぐな不安であり、本音だと思います。
◇私たち夫婦の選択:サポートを得られる環境へ
何度も話し合った末に、私たちは義実家の近くへ引っ越すという選択をしました。
夫婦だけで育てるのではなく、支援を受けながら“きょうだい”を迎える準備をするためです。
しかし、上記に「付き添い入院で母親が不在になり、自分が祖父母に預けられるのが嫌だった。」という意見を
目にして、「自分がもし”きょうだい児”の立場だったら?」と考えるようになりました。
◇支援を受けるのは悪いことではないが…
「しかたない」「少しの間だけ我慢してね」
──そう声をかけることは簡単だけど、本当にそれでよかったのか?
私は、自分の子ども時代を思い出すと、祖父母と過ごすよりも、両親と一緒にいた時間のほうがずっと楽しかったことを思い出しました。
そしてふと、こんなことも思いました。
もし親からの愛情をじゅうぶんに感じられないまま祖父母と長く過ごしたら、
「おばあちゃんは優しいけど、なんでママはここにいないの?」と、心の中に葛藤が生まれることもあるのかもしれない──と。
”きょうだい児の”サポートを誰かにお願いしたり、支援を受けることは決して悪いことではないですが、
その中でも”きょうだい児”にも寄り添った工夫が必要だと考えます。
◇「母親しかできないケア」ではなく、みんなでケアできるように
医療的ケア児の育児では、「お母さんじゃなきゃできないケア」が本当に多いです。
でも、それが続くと「ママと遊ぶ」「ママと出かける」「甘える」時間を、他のきょうだいが持てなくなってしまいます。
だからこそ、家族みんなでケアを担える体制にしていくことが大切だと思っています。
◇レスパイト制度の活用もひとつの手段
最近ではレスパイト(短期預かり)など、制度をうまく使って育児をしている家庭も増えてきました。
友人の中には、レスパイトを活用してきょうだいと過ごす時間をしっかり確保している方もいます。
「頼ること=甘え」ではありません。
必要な人にとっては、**家族みんなが笑顔でいられるための“手段”**なのだと思います。
最後に:家族のかたちはひとつじゃない
きょうだいを持つかどうかは、とても個人的な選択です。
誰かの意見や正解が、自分たちの正解になるとは限りません。
忘れないでいたいのは、
私たち親だって、本当は子どもと平等に関わりたいし、たくさん愛情を伝えたいということ。
余裕があれば、きょうだいひとりひとりの思いに寄り添いながら、
ゆっくり育児をしたいと思っている親がほとんどだと思います。
きょうだいにとっても、医療的ケア児にとっても、親にとっても、今この時の時間は等しくかけがえのない大切なものです。
誰かが我慢するのではなく、みんなを、そして自分自身も大切にしながら、
わが家にしかない育児のかたちを、これからも一緒に探していきたいと思います。

私が子どもだったころを思い出すと、
親が疲れていたり、忙しそうにしていたり、体調が悪そうだったりすると、
自分まで元気がなくなったり、不安になったり、さびしい気持ちになったことがあります。
子どもって、親の表情や雰囲気にとても敏感なんですよね。
だからこそ、きょうだい児が少しでも穏やかに過ごすためには、
まず親である私たちが、心と体に余裕をもっていることがすごく大切だと思います。
とはいえ、それは決して簡単なことではありません。
毎日いっぱいいっぱいで、余裕なんてない、そんな日もたくさんあります。
全部を完璧にやろうとしなくていい。無理しなくていい。
「子どもと目を合わせて話せたな」「ハグできたな」
そんな小さな時間の積み重ねが、子どもにとっての安心感につながっていくんじゃないかと思います。
★この記事が参考になったらクリックお願いします。応援していただけると嬉しいです
にほんブログ村
★こちらもご覧ください★


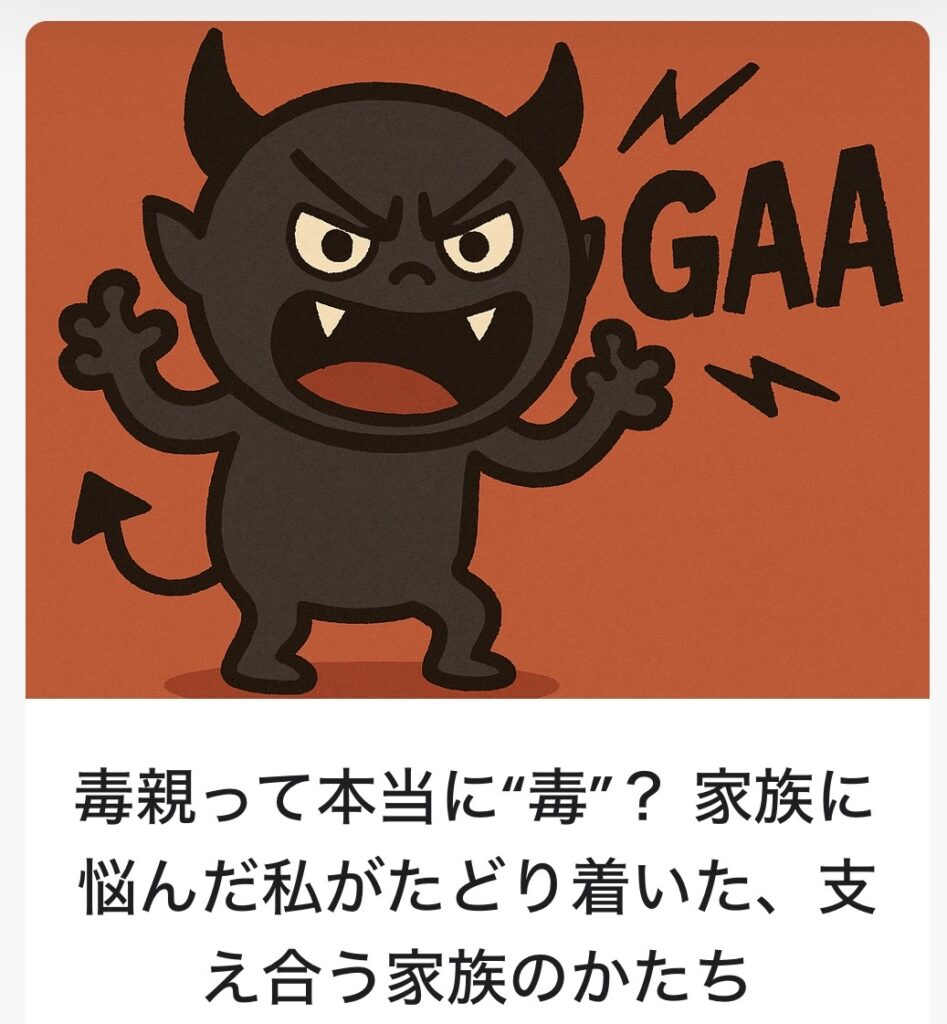
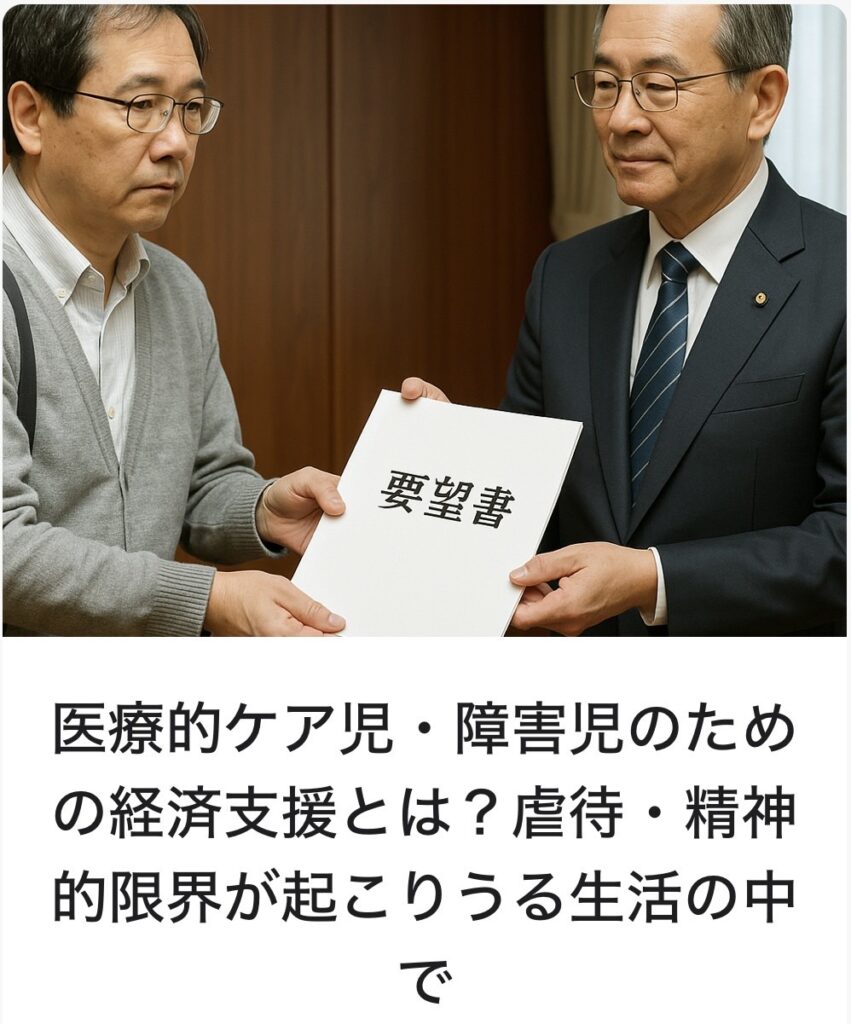
No responses yet