みなさんは、この医師とあんまり相性が合わないかも…?と思ったことはありませんか
医療的ケア児を育てていると、たくさんの医師と出会います。
NICUの医師、小児科外来・病棟の医師、訪問診療の医師──
限られた時間で日々沢山の子どもを診察して、親とも関わる中で、
みなさん説明のスタイルは少しずつ違います。
★この記事が参考になったらクリックお願いします。応援していただけると嬉しいです
にほんブログ村

今回は、私が実際に出会った医師たちとのやりとりの中で感じた“相性”や“信頼”、
そして「思いが伝わらないとき、どう工夫するか」を模索した体験をお話ししたいと思います。
目次
⸻
1. NICUの医師は、「慎重な」説明だった
NICUに入院していたとき、娘の病状については、
医師が毎回書類を使って説明してくれました。
おそらくそれは、混乱する親に視覚的にもわかりやすく伝えるため、
後から見返して疑問を整理するため、そして記録・方針決定のためでもあったのだと思います。
説明してくれたのは中堅〜上級医が多く、私たちの表情や反応を見ながら、
丁寧に言葉を選んでくれているのが伝わってきました。
そして、毎回個室で説明をしてくれて、
週3回は、しっかりお話しをする機会を作ってくれました。
⸻
2. 外来では、必要なときに文書でフォローも
退院後は外来通院が始まりました。
NICU時代の主治医が引き続き診てくれるので、信頼関係があります。
必要に応じて書面を作成してくれることも多く、
安心して相談できました。
ときには訪問診療医や訪問看護師さんにも「共有しておくね」と言ってくれて、
在宅と病院をつなぐ配慮も感じられました。

入院病棟では「初めまして」の医師がたくさん回診に来てくれますが、
主治医がしっかり関わってくれるので、
「娘の情報がきちんと共有されている」と感じられ、心強かったです。
★こちらもご覧ください★
⸻
3. チーム制の訪問診療
一方、在宅に入ってからの訪問診療は“チーム制”で、
毎回どの医師が来るかはわかりません。

まだお会いしたことのない医師もいるそうで、
信頼関係が築けていないこともあります。
そのため娘のことをあまり知らなかったり、
「説明のばらつき」や「相性の差」も感じました。
4.モヤモヤが残ったやりとり
◇呼吸器について①..
たとえば、娘がハイフローを嫌がったとき、
私は「他に合う呼吸器はありませんか?」と相談しました。
ある医師は、
「ハイフローしかありません」と即答。話はそれで終わってしまいました。
でも、別の医師は、
「それ、困りますよね。
じゃあ違う呼吸器で圧を調整しながら一緒に考えてみましょうか」と、
選択肢を提案してくれました。
私にとって大切なのは、「正しいかどうか」よりも、
なぜそれを不安に思っているのか、
なぜ疑問に感じているのかに寄り添ってくれるかどうか。
一緒に解決しようとしてくれる姿勢があるかどうかで、
信頼や安心感は大きく変わります。
★呼吸器についてはこちら★
https://slowlifewithlove.com/sekkyokutekitiryou-ennmei-tigai/
⸻
◇正常値を逸脱したとき…
訪問診療では毎回ETCO₂(呼気終末二酸化炭素)を測定していますが、
今回正常値を初めて逸脱していました。
そこで、「どうしてですか?」と尋ねました。
返ってきたのは、
「そういう状態なんだと思います。あ、首が後屈してたのかもしれませんね」という言葉。

「だったら正確に測定してほしい」──
そう思ってしまいました。なんだか、ちゃんと考えてもらえてないような気がして、
モヤモヤが残りました。
心配している親に対して、もう少し寄り添ってほしかったのです。
⸻
◇ 「それは他職種に聞いて」と言われて…
経口摂取について「ペースト状のものをお口から食べられないかな?」と
相談したとき、
「それはSTか歯科医師に聞いてください」と返されました。
医師からも何かアドバイスがもらえると思っていたので、驚きました。
病院の医師とは経口摂取についてよく話していたので、
あまりにもあっさりと終わってしまい、拍子抜けしてしまいました。
⸻
◇呼吸器について②…
娘が呼吸器をつけているときに苦しそうな様子だったので「つらそうです」と伝えると、
「無理してつけなくていいです」とだけ言われたこともあります。

「なぜつらそうに見えるのか」「どこに原因があるのか」を一緒に考えてほしかった。
こちらの気持ちをちゃんと受け止めてほしかった──それが正直な思いです。
⸻
5.訪問診療医の“苦悩”を理解する8つの視点
◇時間との戦い
• 多くの患者を短時間で回らなければならず、1人1人とじっくり向き合う時間が取れない
• スケジュールが過密で、「本当は往診したいけど、電話対応しかできない」ことも
◇設備の限界
• 医療機関のような高度な医療機器・検査設備がなく、症状判断が難しい
• ETCO₂などの数値異常が出ても、正確に原因をつかみにくいこともある
◇重症対応のプレッシャー
• 呼吸困難やけいれんなど、緊急対応が必要な場合、プレッシャーは大きい
• ミスが許されない環境で“見抜く力”が常に求められる
◇チーム制ゆえの「人間関係の希薄さ」
• 毎回違う医師が来ることで、信頼関係が築きにくい
• 患者や家族の特性を把握する前に交代になってしまう
◇主治医ではない「中継ぎのつらさ」
• 大学病院の主治医の方針に従わなければならず、自分では薬の調整などを判断できないことも
• 家族が言っている指示と、自分に伝えられている情報が異なる場合もあり混乱する
◇孤独な医療者
• チーム医療の病院と違い、訪問現場では「相談相手がいない」孤独感がある
• 判断に悩んでも、自分で抱え込むしかないことも
◇地域性・移動・人手不足
• 移動距離・天候(特に北海道など)・人員不足により、どうしても対応に限界がある
• 1日のうち半分以上が車の中で、記録や連絡も移動しながらこなす
◇「万能さ」を求められる
・小児医療は、日々進化しており、最先端機器の導入や治療の選択肢も細かくなっている
・医師が小児科の専門医とは限らない。また小児科の中でも専門分野の知識が必要となることがあるため、高度な知識が必要。細かく診察する一方で、幅広く全身状態も診る必要がある
・呼吸器・在宅酸素・気管切開・胃ろうなど、機械トラブルや調整、処置を一人で対応しなければならない
・医療的ケア児特有の症状や管理がまだ模索段階

医師は多忙な診察後に、
日々勉強会やカンファレンスを開いて、
情報共有や対応を考えてくれています。
★こちらもご覧ください★
6. 思いが伝わらないとき、どう工夫するか
医師を自由に選べない、説明や信頼関係のばらつきもある。
そんななかで、せっかく訪問に来て診察してくださっているので、
有意義な時間にしたいと思います。
• 医師とのやりとりで疑問に思ったことはメモに残す。
後から「なぜモヤモヤしたのか」を振り返り、
訪問看護師に”どうすれば伝わったのか”と相談にし、次回の診察時に活かす
• 本当に不安なときは病院に連絡して聞いてみる
• 医師が変わっても、これまでの経過や特性を自分の言葉で伝える
(プリントなど視覚的な資料を用意するのも◎)
• 訪問に来た医師に質問してもモヤモヤするようであれば、
クリニックに電話して他の医師に確認する
• 一般的な質問から入ることで、医師も答えやすくなる
• その医師の専門分野を知る。医師も分からない分野があることを理解する
• 訪問看護師さんに同席してもらうと、話しやすくなり、情報共有もスムーズに
• 必要に応じて、看護師さんから医師に確認してもらうよう依頼する
• 納得できないときは、勇気を出して「分からない」と伝える
• AIで内容を整理してプリントアウトして持参する(うまく言葉にできないときに便利)
• 「○○先生にも伝えてもらえませんか?」とお願いする(電話相談ならできることも)
まだ”モヤモヤしたとき”に「これは分かりません」と伝える勇気は出せていません。
でも、ストレスを抱え続けるよりも、
自分の気持ちを少しずつ言葉にしていくことが大事だと感じています。
⸻
7.雑談のすすめ
最近読んだ記事で、
「患者さんと医師が心の余裕を持って、お互いの気持ちを近づけるためには”雑談”が良い」
と書いてありました。
「今日は寒いですね」や「最近娘が笑うようになってきて」──
そんな何気ない、お互い負担のない言葉のやりとりをしつつ、
私自身の苦手意識も、少しずつほどいていく必要があると思っています。
参考:yomi.Dr「担当医とうまくコミュニケーションをとるにはどうすればよいですか?」
⸻
8.おわりに

小児科の訪問診療の需要も増えて、
医師は本当に忙しそうです。
時には診療が長引いたりバタバタしていて、
お昼を食べる時間も遅くなるそうです。
そんななか、私たちの家まで来て診てくれる──そのことにまず非常に感謝しています。
医師も家族も、みんな人間です。
すべての医師が、家族が望むような完璧な対応をしてくれるわけではないし、
相性の良し悪しも当然あります。
でも、「わかろうとしてくれる人」に出会えたとき、
その医療は、親子にとって安心と希望になります。
これからも私は、「分かりやすく伝える努力」と「苦手意識をなくす」ことを目標に、
感謝の気持ちを忘れず、
信頼を育てていきたいと思います。

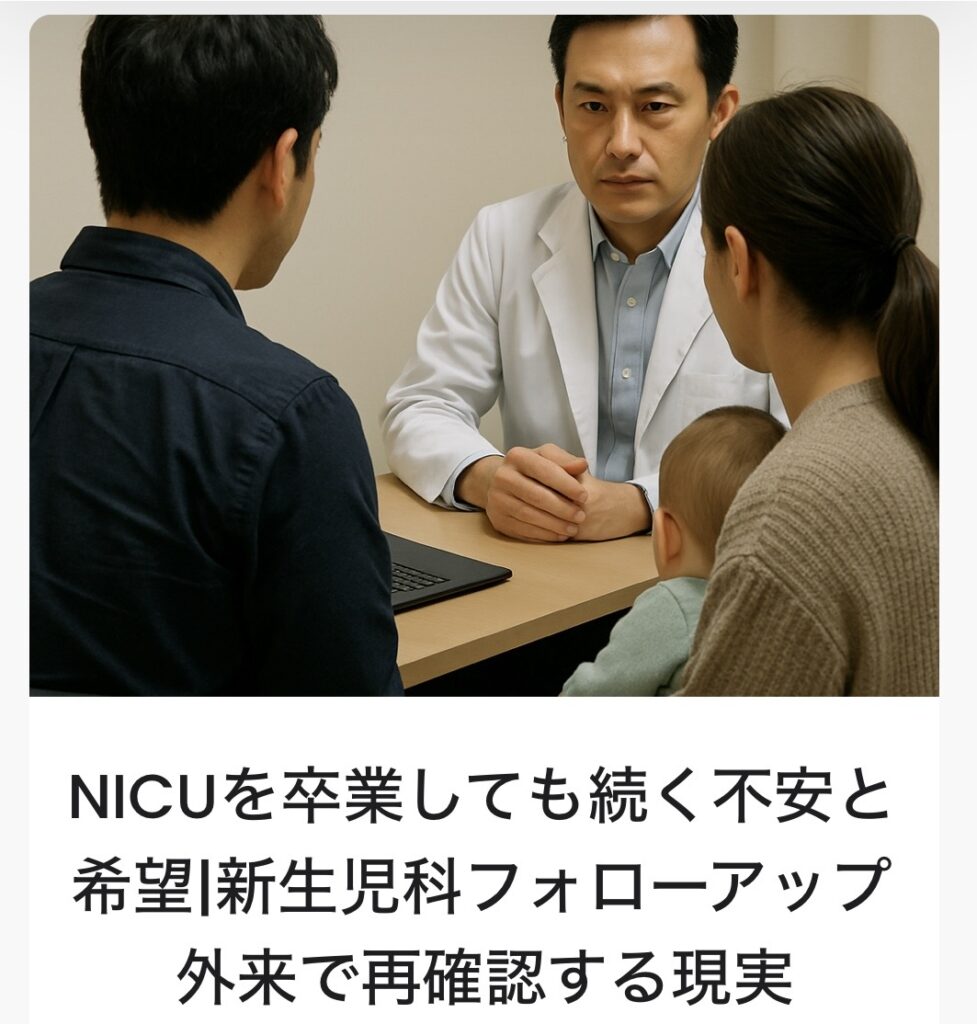
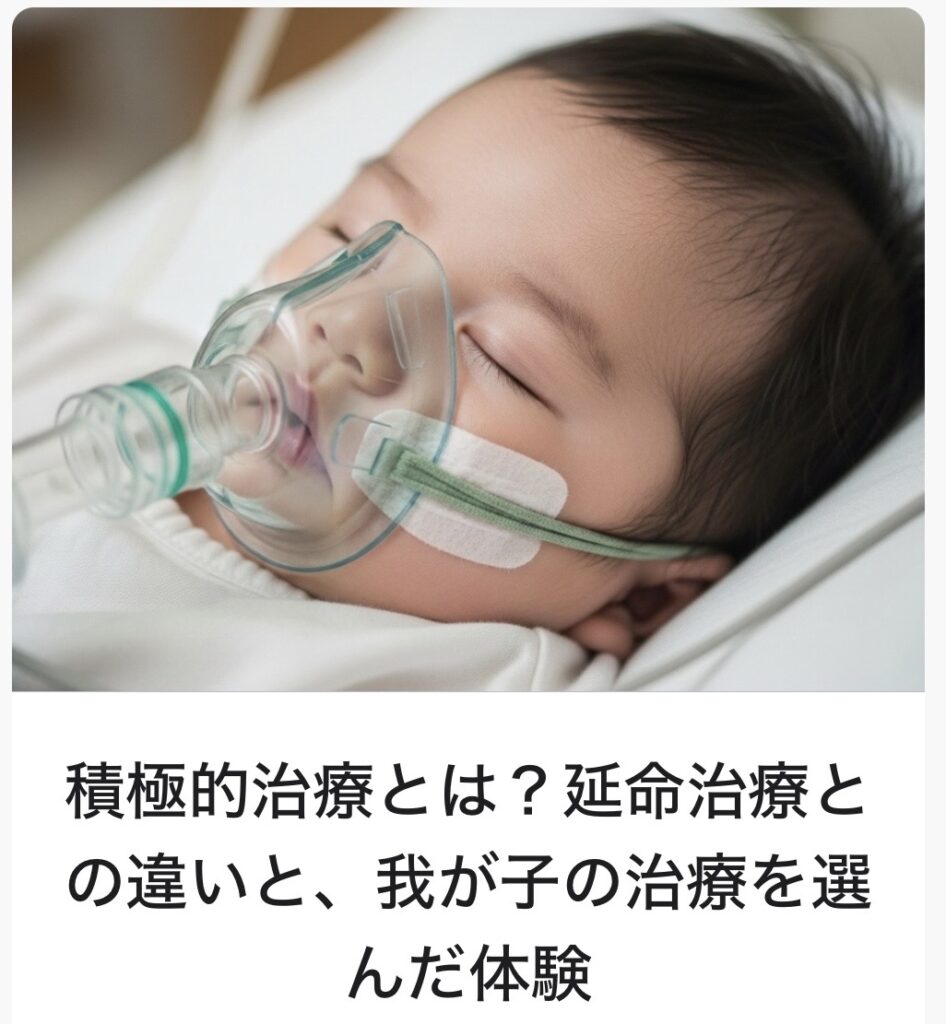
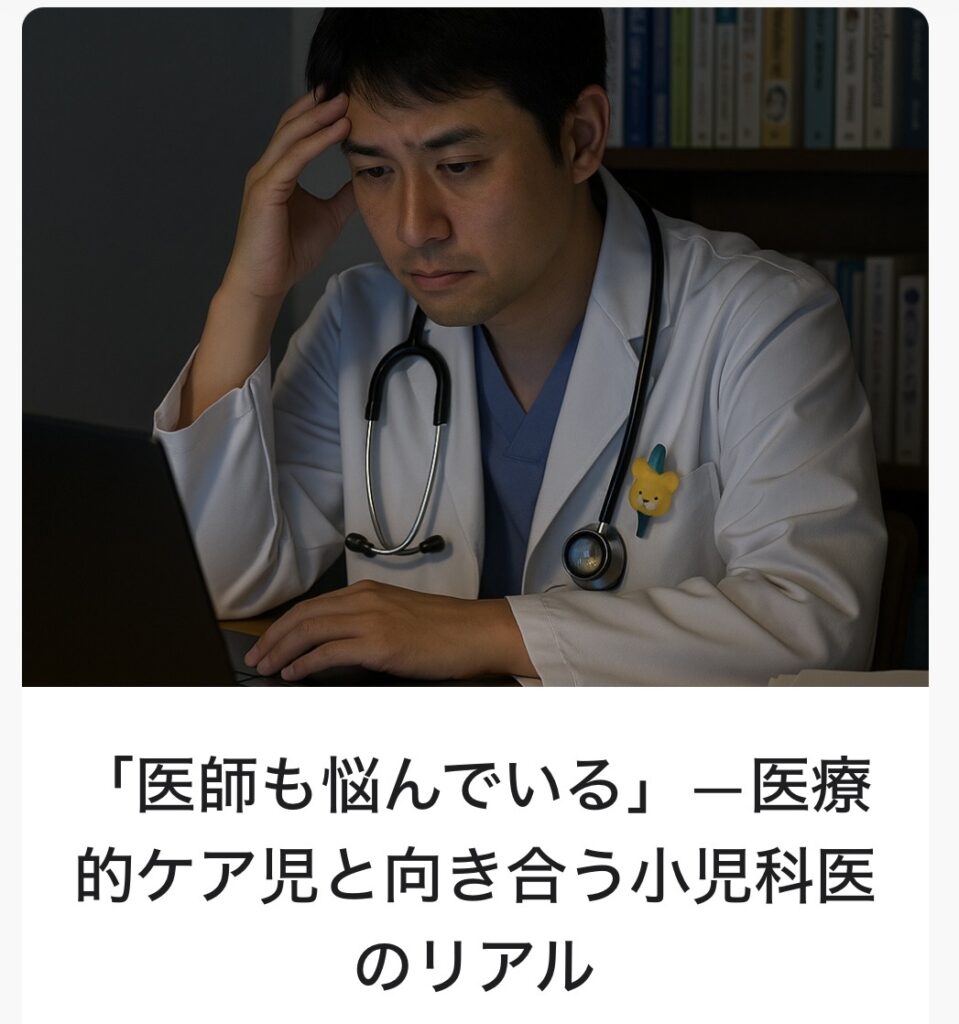
No responses yet