私は看護師として脳外科病棟で働いていた頃、
人工呼吸器をつけた気管切開の患者さんと出会いました。
鎮静をかけているため、意識はなく、体も動かせず、
点滴や経管栄養、頻回な吸引などの医療的ケアが欠かせませんでした。
多い時では15分おき、少なくとも2-3時間に1回、吸引が必要で、
その際、患者さんの目から涙が流れたのを見て、
ただただ早く良くなりますようにと祈りながら看護を行いました。
その経験があったからこそ、
娘が無呼吸や呼吸不全、誤嚥性肺炎などの可能性があり、
医師から「気管切開」の話が出たときは、非常に複雑な想いを抱きました。
※現在、娘は気管切開をしていません。医師から「必要になるかもしれない」と言われたことで、
私の中に迷いと葛藤が生まれました。

医師からは、「もしもの場合、挿管や気管切開を希望しますか?」と尋ねられ、

私はこう答えました。
「苦しい思いはさせたくありません。
もしかしたら今後、気持ちが変わるかもしれませんが、
現時点では、できる限りしない方向で考えています。」
当時の私は、
「気管切開=延命治療」
「生きているけれど、寝たきりで意識もなく…」
そんな姿を想像してしまっていたのです。
今回は、そんな私が当初抱いていた気管切開のイメージと、
そこからどう考えが変わっていったのかをお話ししたいと思います。
目次
1.気管切開が必要になるのは、どんなとき?
気管切開が必要になるのは、
①空気の通り道(気道)に問題がある場合
②長期的に呼吸を助ける必要がある場合
③痰が出せない場合です。
代表的なケースは以下のようなものです。
- 無呼吸や呼吸不全が続いている
- 何度も肺炎や誤嚥を繰り返す
(誤嚥性肺炎の場合は、
食道と気道を分離することでリスクを下げる効果もある) - 気道が狭く、呼吸の通りが悪い
- 長期間、人工呼吸器による管理が必要な場合
こうした状況では、「呼吸を楽にする」「気道を確保する」
ために、医師から気管切開が提案されることがあります。
ただし、急ぐべき救命処置として行われることもあれば、
じっくり話し合って決められることもあります。
2.イメージが変わったきっかけ
そんな中、SNSで気管切開をしているお子さんたちの様子を見かけました。
呼吸器をつけながら、ごはんを食べている子。
おもちゃで遊んだり、声を出して笑っている子。
私の中で「延命治療」と思っていた気管切開が、
「これは、呼吸を楽にするためのサポートなんだ」と、
前向きに捉えるようになりました。

病院では「カフ付き」の気管切開カニューレを
使用することが多かったので、
声が出ている子を見て、驚きました!
3.気管切開の歴史
気管切開の歴史は古く、紀元前のエジプトですでに記録が確認されています。
しかし当時は、麻酔や衛生管理が未発達だったため、
命を落とす危険も高く、あくまで“最終手段”とされていました。
その後、18~19世紀にはジフテリアやポリオなどの感染症が流行し、
小児にも気管切開が行われ始めましたが、
成功率はあまり高くありませんでした。
やがて医療技術が進歩し、手術の安全性や管理体制が整い、
ScienceDirectの分析(1980〜1990年)では、
1980年代後半にかけて小児の気管切開症例が増加したことが示されています。
小児や在宅ケアにおける「気管切開の選択肢」としての普及は、
1990年代以降であると考えられるそうです。

気管切開が「子どもにも行われる一般的な医療の選択肢」として
受け入れられるようになったのは、
ほんのここ30年ほどのことみたいです。
4.気管切開が「ハードルが高い」と感じられる理由
気管切開は、呼吸を助けるための非常に重要な医療的ケアですが
「ハードルが高い」と感じられます。
その理由を考えてみました。
●痛み・違和感への心配
- 子どもが違和感を感じそう
- 見ていて痛そう
- 吸引するとき、苦しそう
- 手術後の絶対安静がつらそう
- 傷からの感染症が怖い
こうした身体的な負担や痛みに対する想像が、強い不安につながることがあります。
● 延命治療のイメージと重なる
「気管切開=命を無理やり延ばすこと」と感じてしまう方も少なくありません。
とくに高齢者医療の現場では、終末期の延命処置として語られることが多く、
その印象が残っているのかもしれません。
● 声・見た目への戸惑い
首に穴があいている、チューブが見える、声が違う──
見た目や音の変化に対する戸惑いから、
「かわいそう」「つらそう」と感じる人も多いです。
● 医療的ケアの大変さ
気管切開後は、吸引・加湿・モニター管理などの医療的ケアが必要になります。
「自宅でちゃんとできるの?」「夜中も吸引が必要なの?」
「アラームが鳴ったときにすぐ吸引しないと、窒息するの?」
といった不安から、
ハードルの高さを感じる方も少なくありません。
● 情報・支援の少なさ
気管切開について、正しく・分かりやすく説明してくれる場所が少ないのも現実です。
インターネットで検索しても、医療用語ばかりで理解しづらかったり、
「リアルな生活」が見えてこないこともあります。
だからこそ、**「よくわからないからこそ怖い」**という気持ちが生まれてしまうのです。
● 周囲に前例がない不安
気管切開は、まだ比較的新しい医療的ケアで、
まわりに同じ経験をした人がいないことも珍しくありません。
- 同じ病院や地域で、前例が少ない
- 友人や知人に経験者がいない
- SNSやネットを見ても、実際の生活が想像できない
こうした状況では、**「本当にこれでいいの?」
「誰にも相談できない」**という孤独感や不安につながります。
また、保育園やデイサービス、地域の支援機関でも、
「気管切開のお子さんは初めてです」と言われ整備が整っていないこともあるそうです。
● 周囲からの理解のなさ・反対の声
気管切開はまだ一般的に知られていないため、
周囲の人から心ない言葉や、反対の声を受けることもあります。
- 「そんなことするの?」
- 「やめなよ」
こうした言葉は、決して悪意からではなく、
ただ「知らない」「見たことがない」ことから生まれていることがほとんどです。
それでも、親として我が子のために選んだ選択に対して、
理解されない苦しさや孤独感を抱えることは、とてもつらいことです。

”妻と夫の間”でも意見がよく分かれます。
たとえば、妻はSNSで多くの情報を目にして気管切開のイメージがポジティブなものに変わったけど、
夫は消極的なままというケース。
私も看護師の経験があるので、
私の中では“見慣れてきた医療ケア”。でも、夫にとっては現実味がなくて怖いのかもしれないと思いました。
5.実際に気管切開を選んだご家族の声

「DIPEx JAPAN医療的ケアの導入と決断」こちらのサイトに、
実際にお子さんの気管切開を決断したご家族のインタビューが載っています。
葛藤や苦悩など、リアルな意見が感じられます。
●何割の医療的ケア児が気管切開をしている?
令和元年に厚生労働省が行った「医療的ケア児者とその家族の生活実態調査」では、
41.8%が気管内挿管、気管切開をしているというデータがあります。(p.24)
ただしこの数字には、気管内挿管も含まれているため、純粋な「気管切開のみ」の割合としては、やや低い可能性があります。
平成 22 年〜平成 24 年の調査では、
NICU/GCU病棟から転出時に気管切開が必要となったのは37%
(引用:—医療的ケア児に関する実態調査と医療・福祉・保健・教育等の
連携促進に関する研究— p.33)
という報告もあり、対象年齢や調査対象によっても差があります。

気管切開を選択したご家族の中には「気管切開があったから退院でき、子どもと自宅で過ごせるようになった」というポジティブな意見がある一方で「後悔している」という意見もあります。
気管切開には、良い面もあれば、不安や負担に感じる面もあります。
●メリット
✅ 呼吸が安定しやすくなる
呼吸が弱い子どもや、
無呼吸のある子にとって、
確実に空気を肺に送れることは命を守る大きな助けになります。
✅ 肺炎(特に誤嚥性肺炎)のリスクが下がる
痰を吸引しやすいため肺に痰が溜まりづらくなります。
風邪をひいた際も、重度の肺炎になることを予防できます。
誤嚥性肺炎を繰り返していた場合、
食道と気道を分けることで、肺を守ることができます。
✅ 吸引がしやすくなる
痰をためやすい子どもにとって、
吸引がしやすくなることで呼吸が楽になり、
気管切開をする前と比較して
1回の吸引の時間が短縮され、苦痛が少なくなる場合があります。
✅ 声帯を守ることができる
長期の経口挿管(口からのチューブ)に比べて、
声帯を傷つけにくく、痛みも少ないとされています。
✅ 在宅医療が可能になるケースもある
病院にずっといなければいけなかった子が、
気管切開をしたことで状態が安定し、
自宅での生活に移行できたというケースもあります。
風邪をひいた際、入院が必要だった子どもが
おうちで診れる場合もあります。
●デメリット(注意点)
⚠️ 見た目や音への抵抗感がある
首にカニューレが入っていることで、周囲の視線が気になることも。呼吸音や声の変化も、人によっては気になる場合があります。
⚠️ 声が出にくくなる(特にカフ付きの場合)
空気が声帯を通らなくなるため、発声が難しくなることがあります(※個人差あり、工夫や訓練で改善する場合もあり)。
⚠️ 感染・合併症のリスク
傷口からの感染、チューブ閉塞、皮膚トラブルなどが起きる可能性もあり、日々のケアが欠かせません。肉芽が出来た場合は、必要に応じて切除する必要があります。
⚠️ 医療的ケアの負担が増える
吸引・加湿・カニューレ交換など、家庭で行うケアの内容が増えるため、家族や支援者の理解とサポートが必要です。
⚠️ 急なトラブルに備える必要がある
カニューレが抜けてしまったり、詰まってしまうと命に関わるため、緊急時の対応方法を家族も身につけておく必要があります。
⚠️ 術後の安静や、痰の増加によるつらさ
手術後は絶対安静が必要になるため、本人にとってもつらい時間が続きます。
また、気管切開をした直後は痰の量が一時的に増えることがあり、吸引の回数が増えて「本当にこの選択でよかったのだろうか」と悩むご家族も少なくありません。
⚠️ 思っていたイメージと違ったと感じることもある
「もっと簡単に呼吸が楽になると思っていた」「そんなこと聞いてなかった」
「声が出ると思っていた」「すぐに退院できると思っていた」など、
事前に思い描いていたイメージと実際の様子が違い、戸惑いを感じることがあります。

デメリットに関して、ご家族は「やらなきゃよかった」と
全否定しているのではなく、
「大変だったし、今もその判断で良かったのか迷うことはあるけれど…それでも、この選択で良かったと思える日もある」
「後悔したけど、それ以上に救われたこともあった」という、
**複雑で揺れる“親の想い”**を抱いていることが多いです。
6.気管切開=吸引が必要?
気管切開をすると、「吸引」が必要となるイメージがありますが、
吸引が必要な頻度は、状況とお子さんによって様々です。
◇吸引が必要な理由
● 痰があることに気づきにくくなる
●痰がもともと痰がたまりやすい体質・状態
気管や気道が細い、弱い
筋力が弱く、咳をする力が足りない
よだれや唾液をうまく飲み込めない
気道に分泌物がたまりやすい病気がある
● 気管切開をすると、痰を出す力が弱くなる
気管切開をすると空気が直接首から入るため、
咳やくしゃみで痰を上手く押し上げる力が弱くなるのです。
その結果、痰が気道の中にたまりやすくなり、詰まったり感染の原因になることがあります。
● 加湿が不足して痰が固くなりやすい
鼻や口から息を吸うとき、自然と空気は加湿・加温されます。
でも、気管切開では首から空気を取り込むため、空気が乾燥しがち。
その結果、痰が固くなって出しにくくなることがあります。

痰が詰まってしまうと、
呼吸ができなくなってしまうこともあります。
とくに赤ちゃんや小さなお子さんは自分で訴えられないため、
呼吸音の変化や表情、モニターの数値を見てすばやく吸引をする必要があります。
「実際、どれくらい吸引が必要なのか。
本人も親も大変なのかは、やってみないとわからない」
これが、気管切開を前に立ち止まってしまう大きなの理由の一つかもしれません。
SNSで情報を見たり、医師の説明を受けたりしても、
在宅でのケアが自分たちに本当にできるのか、
どれほどの負担があるのかは、想像しきれないのです。
ちなみに、平成30年度に栃木県で調査された、
「医療的ケア児実態調査結果報告書 p.17」では
吸引が必要な医療的ケア児(気管切開ではない場合も含む)80人について、
以下のデータがあります。
- 1日に6回未満の吸引で済む子どもが25人(約31.3%)
- 1日に6回以上の吸引が必要な子どもが28人(約35.0%)
- 1時間に1回以上の高頻度の吸引が必要な子どもが27人(約33.8%)
約3人に1人が「1時間に1回以上」という頻度で吸引が必要な状況であり、家庭や施設でのケア負担がとても大きいことが分かります。
回数が増えるほど、保護者や支援者の休息がとりづらくなり、訪問看護や支援制度の充実がより重要になります。

YouTubeで「医療的ケア児 吸引」と検索すると、
”3時間おき”・”1日200回”など様々でした。
親も疲弊しないように、
医師や看護師さんに、
他のご家族はどんな工夫をしているのか
聞いてみてもいいかもしれないですね!
7.おわりに
「子どもの気管切開なび」さんが、Q&Aや手術の流れなど、分かりやすく詳しく
気管切開について紹介しています。ぜひ、ご興味のある方はご覧ください。
気管切開は、たくさんの迷いと勇気のなかで選ぶ医療的ケアです。
気管切開に限らず、「間違っていないかな」
「これでいいのかな」と考えることもあります。
「自分たち家族が納得して選べるかどうか」
「その子がその子らしく生きられるか」を考え、
「そのとき出した精一杯の答え」で決断していきたいと思います。
★この記事が参考になったらクリックお願いします。応援していただけると嬉しいです
にほんブログ村
★こちらもご覧ください★

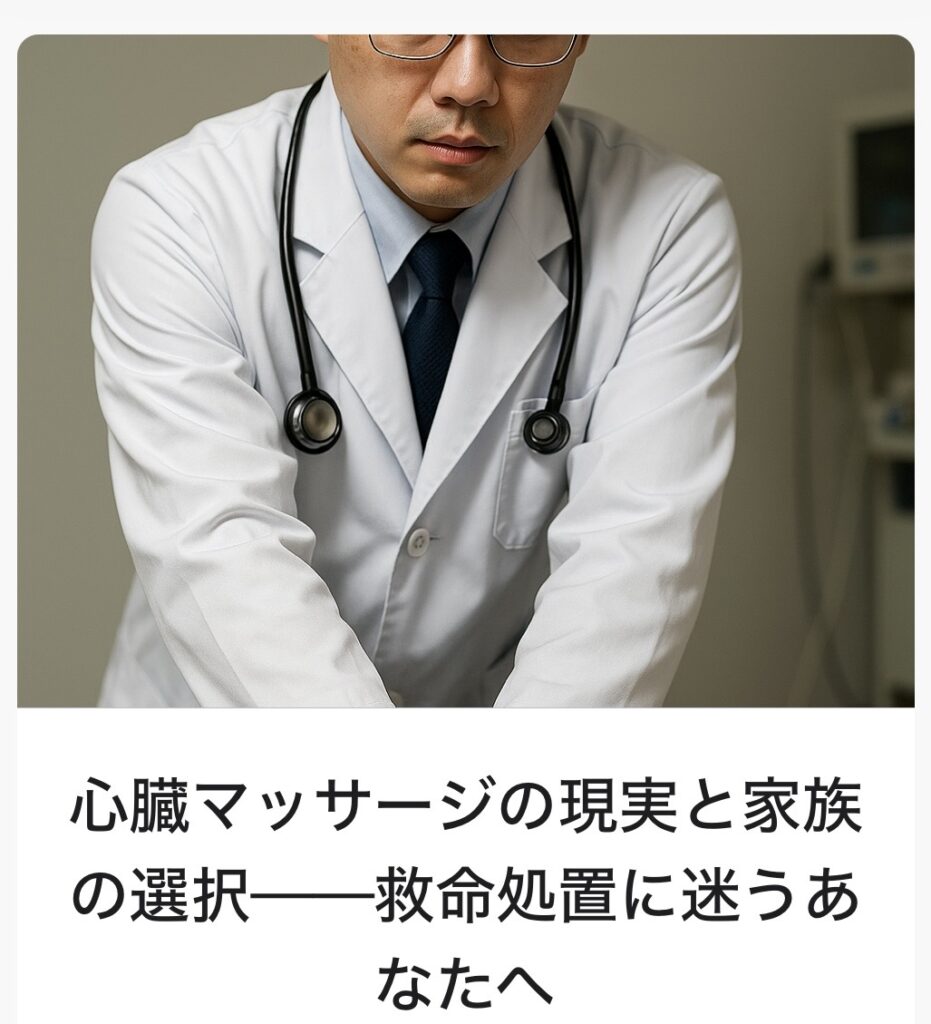

No responses yet