
みなさんは、SNSを利用していますか?
私は主に情報収集や同じ病気をもつ家族との交流をメインに使っています。
利用して良かったと思う一方で、注意するポイントがあることにも気づきました。
今回はSNSを利用するうえで気をつけたいこと6選をご紹介します。
目次
1.妊娠中から在宅生活まで、SNSに救われた日々
子どもの病気が妊娠中にわかったとき、私はしばらく塞ぎ込んでいました。
出産のこと、育児のこと、何もかもが不安でいっぱいで、
「この子と私たち家族はどうなってしまうんだろう」――
そう思うだけで、毎日涙が止まりませんでした。
少し気持ちが落ち着いたとき、
SNSで同じ病気の子どもを育てている方々の投稿を探しました。
「無事に出産できるのかな」「この先どうなっていくのか不安です」
とつぶやいた私に、たくさんの方が励ましの言葉をかけてくれました。
お空へ旅立った子の記録も見ました。
今を生きる子どもたちの笑顔と、
前を向いて暮らす家族の姿も見ました。そして、勇気をもらいました。
近所に住む、同じ病気・同い年のお子さんともつながることができ、
実際に会うこともできました。

たくさんの生活のヒントをもらい、
私にとって、SNSはまさに無くてはならない「救い」でした。
2.でも今、私はSNSから少し離れています
出産してから1年。
いま私は、SNSから少し距離を置いて生活しています。
それは、あるときからSNSを見ると悲しい気持ちになったり、疲れてしまったからです。
3.SNSを使うときに気をつけたい6つのこと
① 投稿が勝手にシェアされることもある
ある日、自分の投稿が他の人に無断でシェアされていることに気づきました。
悪気があったわけではないのかもしれませんが、
「知らないところで広まっている」という事実にとても驚きました。
それ以来、私は「シェア禁止」とプロフィールに明記し、
鍵アカウントに切り替えました。
大切な情報は、自分で守る必要があると実感した出来事でした。
② 写真や情報から個人が特定されることも
子どもの顔写真、住んでいる地域、病院名──
何気ない投稿の中に、意外と多くの
「手がかり」が含まれています。ありがたいことにたくさんの人が応援してくれたり、
心配してくれたりします。
でもある日、今まで交流もなかったフォロワーさんから、
突然「会いたい」と言われたことがあり、
正直とても驚きました。
その方に悪気があったわけではないと思います。
でも、共通点もなく、面識もない方から急に
「会いたい」「お見舞いに行ってもいいですか?」と
言われた時の戸惑いは大きかったです。

私は、「顔はぼかす」「病院名は出さない」
「場所が特定されそうな背景は避ける」など、
自分なりのルールを決めることにしました。
③ 比較や情報の多さに心がゆれる
あるとき、SNSで「手術したほうが長生きできる」
という投稿を見ました。
実際に、私も論文を読んでおり、根拠があるのは知っています。
でも私の子は、医師と相談した上で内服治療を選んでいます。
その投稿を見たとき、「今の治療は間違っているのかな」と、
ものすごく不安になりました。
また、フォロワーさんから
「病院を変えた方がいい。〇〇病院がおすすめです」
とアドバイスをいただいたことがあり、困惑しました。
そんな私に、同じ病気のお子さんを育てているパパさんが
こう言ってくれました。
「同じ病気でも、症状や状態は様々で、
その子に合った治療がある。
みなさん色々言っているけど、
医師を信じて、他の子と比べないほうがいいです。」
その言葉で、心がふっと軽くなりました。
比べなくていい。今の私たちの選択も”間違いじゃない”――
そう思えた瞬間でした。
さらにその後、
「内服治療でも長生きしています」という投稿も見かけて、
ほっとしたのを覚えています。

SNSを見ていると、
都会ではできる検査や治療が、
地方では受けられないこともよくあります。
「どうしてうちはできないんだろう」
「この地域に住んでいるから不利なのかな」
そんなふうに思ってしまうこともありました。
でも、それぞれの場所で、それぞれの環境のなかで、
みんな自分たちなりに迷いながらも一生懸命に向き合っている。
情報はありがたいけれど、すべてを真に受けすぎないこと。
「できないこと」ばかりに目を向けすぎず、
今、この状況で、できることを大切にしていこうと思えるようになりました。
⸻
④ 悲しい知らせに心が追いつかない
ずっと仲良くやりとりしていた方から突然メッセージが返ってこなくなる。
その理由が「お空へ帰ったから」と知ったとき、
胸がつぶれそうになりました。
SNSでは、そういった喪失や別れの報告も突然届くことがあります。
関わりの深さに関わらず、心に大きな波がくることがあります。
だからこそ、SNSを見るタイミングや、距離感はとても大事です。
必要なときには、離れる選択も「自分を守る手段」です。
⸻
⑤ メッセージや交流がプレッシャーになることも
SNSで知り合った方々とのやりとりは、本当に励みになりました。
でも、体調が悪いときや余裕のないときでも「返信しなきゃ」と思ってしまい、
苦しくなることもありました。
SNSは「自分が元気なときだけ」「読む専にしてみる」
「しばらく非公開にする」など、自分のペースでつき合うのが一番だと気づきました。
⑥ NIPTや障害児へのネガティブな意見に心が揺れる
SNSでは、NIPT(新型出生前診断)や出生前診断についての投稿も多く見かけます。
中には、「陽性だったから中絶した」
「産む選択をした人の気が知れない」といった、
意見が書かれていることもあります。
それぞれの人に、
それぞれの事情や想いがあることは分かっています。
その考えを否定する気持ちは全くありません。
でも、我が子と向き合い、懸命に育てている立場からすると、
ふとした言葉に傷ついてしまうこともあります。
「この子たちはかわいそう」「苦しむだけ」──
そんな言葉を見かけるたびに、
我が子の存在を否定されたような気がして
胸が痛みます。

SNSは自由な場所だからこそ、
すべての意見を受け止めようとすると心が壊れてしまうこともあります。
心がざわつくときは、画面を閉じる。
見ないことも、自分と子どもを守る手段のひとつです。
⸻
⑦時間があっという間に過ぎる
SNSを見ていると、あっという間に時間が過ぎませんか?
その影響で寝不足になったりも。生活に影響がでることもあるので、時間を決めるようにしました。
4.おわりに──SNSと「ほどよくつながる」ために
SNSは、同じ境遇の人とつながれたり、心が救われたり、
情報が得られたりする、とても大切なツールです。
でも、使い方を間違えると、
自分や子どもを傷つけてしまうこともあるということも忘れたくありません。
私は今、SNSとの距離を少しだけ置いて、心地よいバランスを探しています。
あなたとあなたのお子さんの毎日が、どうか心穏やかでありますように。
★この記事が参考になったらクリックお願いします。応援していただけると嬉しいです
にほんブログ村
★こちらもご覧ください★

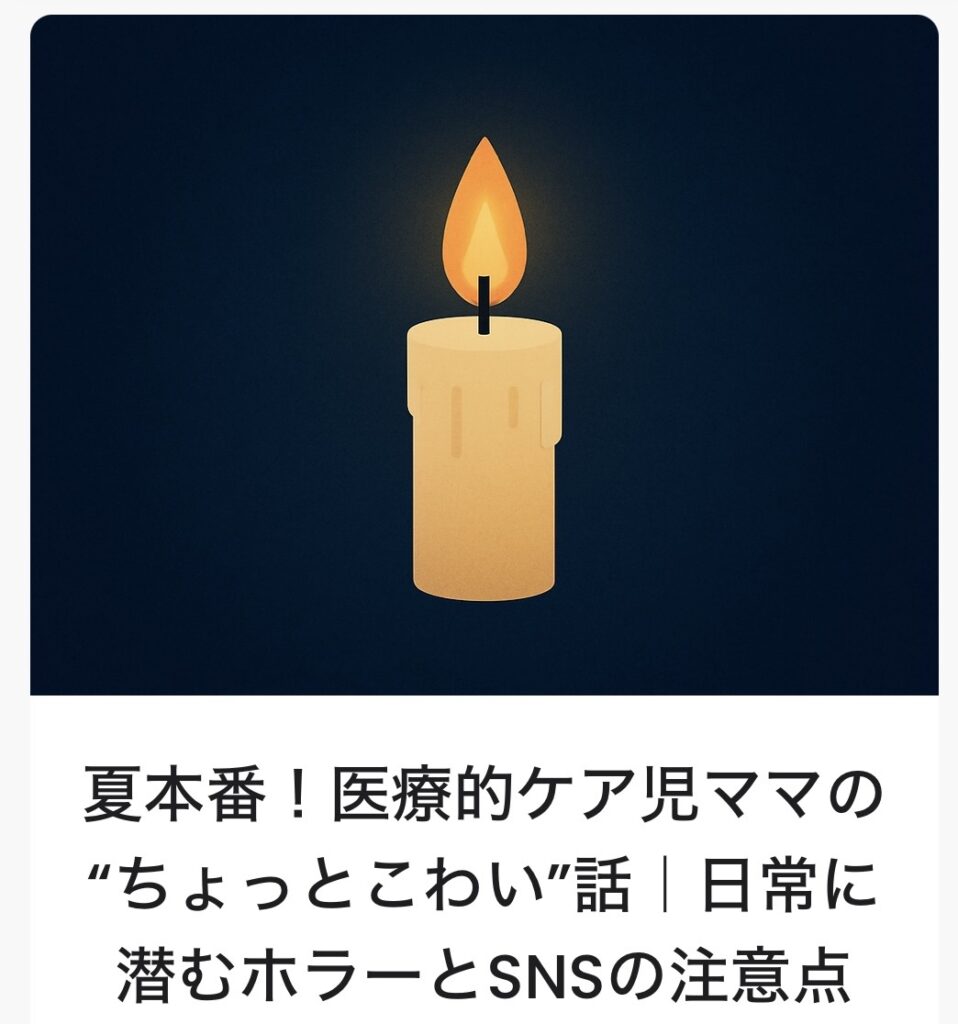
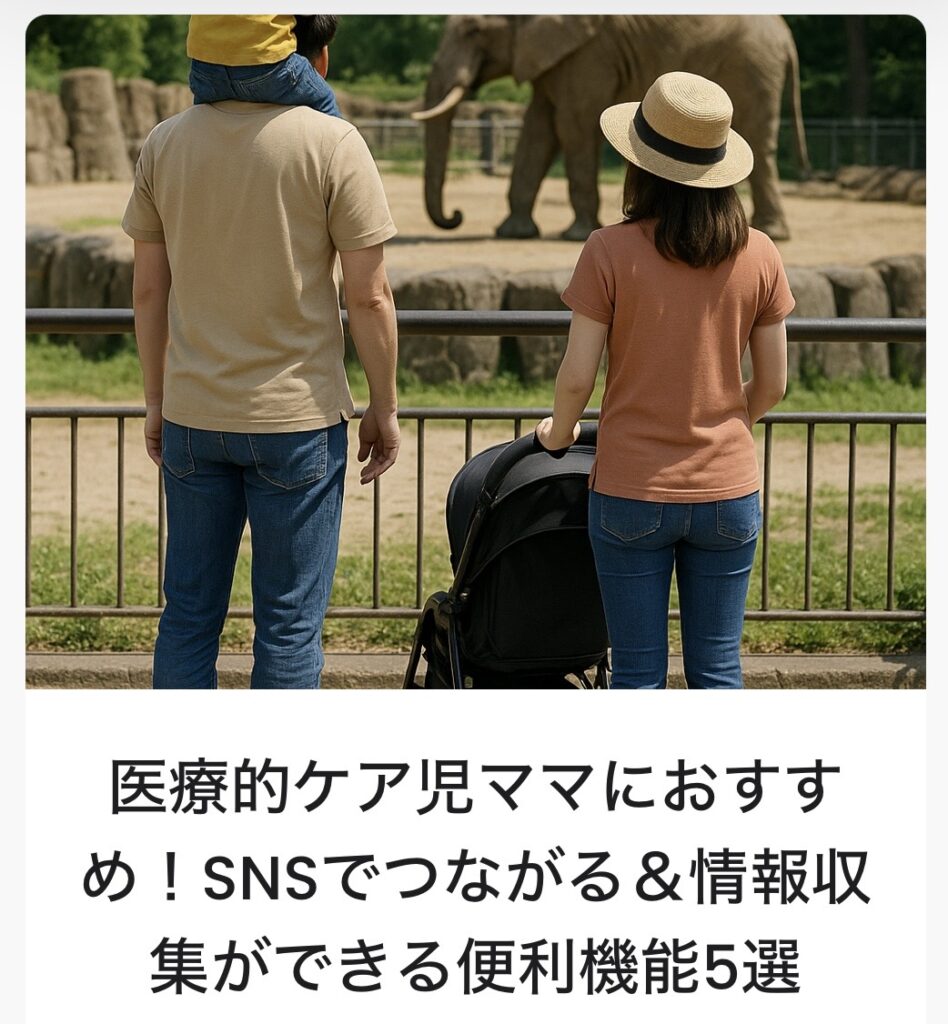
No responses yet