
医療的ケア児を在宅で育てるご両親にとって、
「この大変な生活が、ずっと続くのでは…」と不安になることもあるかもしれません。
今回は、NICU退院直後の生活と、現在の私たちの生活を比較しながら、
少しずつ変わっていった日々をご紹介します。
NICUを退院した時はすべてに精一杯で、自信が全く持てない”医療的ケア児との暮らし”でした。
3時間おきの経管栄養と搾乳、夜の呼吸確認、頻回な通院…。
すべてが初めてで、責任の重さに押しつぶされそうな日もありました。
それでも少しずつ、娘も私たち家族も変わってきました。
「今はこうなったよ」と言えるようになるまでの、10の変化を振り返ります。
【1】経管栄養の回数が減った
NICUから退院したばかりの頃は、1日3時間おき・8回の経管栄養に追われていました。
当時はミルクではなく母乳だったため、
- 冷凍庫から母乳パックを取り出す
- 40℃のお湯で解凍し、温まったか確認する(20分ほど)
- 解凍した母乳をボトルに移す
という手順を踏んでから、30分かけて注入。
その後はボトルやシリンジを食器用洗剤で洗い、ミルトンに浸けて消毒。
片付けが終わるころには、また次の注入がやってくる──その繰り返しでした。
さらに合間には搾乳もあり、
常に「搾乳」と「経管栄養」に追われているような感覚でした。
本当は、経口摂取に向けておしゃぶりの練習をしたほうが良かったのかもしれません。
でも、目やにを拭く余裕すらなく、ただ「生かす」ことに必死だった日々でした。
それが今では、成長に伴い消化スピードが速くなり胃の容量も増えた結果、1日4時間おき6回に。
生活もメリハリがつき、呼吸がしやすくなったような気がしています。
【2】搾乳をやめて、自責の気持ちも和らいだ
搾乳を続けていたのは、免疫のある母乳を届けたいという思いと、
「健康に産んであげられなかった」という罪悪感があったからです。
私が娘にできることは「これしかない」と思っていました。
「娘は精一杯頑張っているんだから、私もちゃんと頑張らなきゃ」──そうやって、自分を追い込んでいました。
でも、常に時間に追われ、キャパオーバーな毎日。
アラームが鳴って目を覚まし、
ミルトンからパーツを取り出して搾乳器を組み立て、
30分かけて搾乳し、それを母乳パックに移して冷凍庫へ。
全然眠れない日々でした。
それでも、「健康な子どもを産んだお母さんだって、最初は3時間おきの授乳をしてるんだから」──
そう自分に言い聞かせて、なんとか踏ん張っていました。

でも、うまく搾乳器が密着しておらず、母乳が出なかったときは、本当にショックで、心が折れそうになりました。
モーター音もうるさくて、家族の眠りを妨げないように、私は寝室を離れ、
真っ暗な部屋でひとり、静かに搾乳していたのを覚えています。
そんな日々を続け、疲労で倒れそうだったある日、夫からの提案もあり、
思い切って搾乳をやめることにしました。
最初は「母乳をやめてしまった」という罪悪感でいっぱいでした。
でも、SNSで他のママさんから
「私もそう思ったけど、ミルクのほうが体重増えたよ」
と声をかけてもらい、少しずつ前向きな気持ちになれました。
時間に追われない分、娘としっかり向き合う時間が生まれました。
その時間で、動画を撮ったり、可愛いお洋服を着て写真を撮ったり。
ゆっくり丁寧なケアをして、楽しい時間を一緒に過ごしたりできるようになってきました。
【3】おでかけできる場所が増えた
医療的ケア児は風邪一つでも命にかかわることがあるので、人ごみを避けていました。
その結果「ホテル泊」だけで精一杯だったお出かけ。
今では、美術館の展示会にも足を運べるようになりました。
もちろん、事前に下調べをして閉館間際に行くことで人ごみを避けられています。
準備は大変だけど、
「行ってみよう」「楽しみだね」と思える気持ちが持てて行動範囲が広がったことが、なによりの変化です。
【4】訪問看護も、わたしたちの形で
最初は週2回・1時間だった訪問看護。
途中で相性が合わず、月2回・30分に減らしたことも。
でも事業所を変え、現在は週3回・90分に。
いまは「支えてもらっている」ではなく「どうすれば娘、そして家族にとってよりよい生活になるか」、
考え合える仲間のような関係です。

訪問看護の頻度は人それぞれ。週1の人もいれば、週5の人もいます。
そのときどきの家族の生活状態に合わせて、柔軟に変えていけばいいと思っています。
★こちらをご覧ください★
【5】生活リズムが整ってきた(でも眠れない)
退院直後は娘がよく寝ていて、逆に「生きてるの?」と不安になるほど。
ところがある日から、突然4時間も泣き続けることがありました。
そんな時は、寝るのをあきらめて、ずっと抱っこしながらユーチューブを一緒に見ていました。
いまは昼夜のリズムもできてきました。
けれど睡眠時に無呼吸があるため、寝ている時も親は休めません。
また、てんかんも起こるようになったため、常に緊急時の備えもしています。
【6】自分のやりたいことも、少しずつできるように
すべてがケアに追われていた日々から、少しだけ自分の時間も持てるように。
やりたいことに手を伸ばすことが、罪悪感ではなく「大切なこと」だと思えるようになりました。
★こちらもご覧ください★
【7】未来のことも考えられるようになった
NICUで「予後不良」と言われていた娘。
当時は、1年先を想像することすら怖かった。
でも今は、「保育園に入れるかな?」「通える場所あるかな?」と
少しずつ未来の話ができるようになっています。
不安はあるけれど、そこに希望も見えるようになってきました。
★こちらもご覧ください★
【8】通院の頻度も変化した
以前は月に2〜4回の通院が当たり前でした。
でもいまは小児科は月1回、循環器(心臓)は2ヶ月に1回に。
病院での治療が生活の中心でしたが、今は「おうち」でどうやって楽しく過ごしていくかが軸になりつつあります。
★こちらもご覧ください★
【9】医療から在宅へ──慣れてきた分、責任も感じる
病院にいた頃は、医師や看護師が判断してくれていた。
でも在宅になると、すべての判断が親に委ねられます。
ケアに慣れてきたからこそ、
「この判断で大丈夫か?」と責任の重さを強く感じることも。
それでも、娘が家で笑ってくれること、家族で過ごせるあたたかさを思うと、
「この選択でよかった」と思えます。
訪問診療や訪問看護などの在宅支援を活用していることで、不安なことはすぐ相談できています。
★こちらもご覧ください★
【10】夫も協力的になってきた
以前は搾乳ごとに私が起きて、経管栄養もすべて一人でしていました。
でも今では、夜中の3時に夫が起きて交代してくれるように。
ほんの数時間でも眠れることが、こんなに心を軽くするなんて思わなかった。
夫婦で分担できるようになって、「ふたりで育てている」という実感も増えてきました。
おわりに──家族で、一緒に生きていく

医療的ケア児を育てることは、毎日が不安と選択の連続です。
でも、あの頃の私が「今日を生きるだけで精一杯だった」ことを思うと、
いまは本当にたくさんの変化がありました。
娘も私も、夫も、少しずつできることが増えて、
笑い合える時間も、希望も、確実に増えてきました。
もちろん、てんかんや無呼吸といった不安や、
在宅ケアの責任の重さに押しつぶされそうになる日もあります。
「前のほうが楽だったかもしれない」と感じる夜も、まだあります。
それでも、変わりながら対応していくのが、家族なのだと思います。
今の私たちは、以前よりも協力し合えていて、
一体感のある“家族”らしくなったと感じています。
泣いて、笑って、支え合いながら──
私たちは、これからも一緒に生きていきます。
ただ、この記録は**あくまで“わが家の一例”**です。
すべての家庭が同じように変化できるわけではありません。
住んでいる地域によっては、支援の体制が整っていなかったり、
周囲の理解や協力が得られず、今も過酷な状況の中で頑張っているご家族もたくさんいます。
だからこそ私は願います。
少しでも多くの家族に、必要な支援が届く社会になりますように。
そして、どんなかたちであっても、一人ひとりの「人間」としての存在が尊重されますように
★参考になったらクリックお願いします。応援していただけると嬉しいです
にほんブログ村




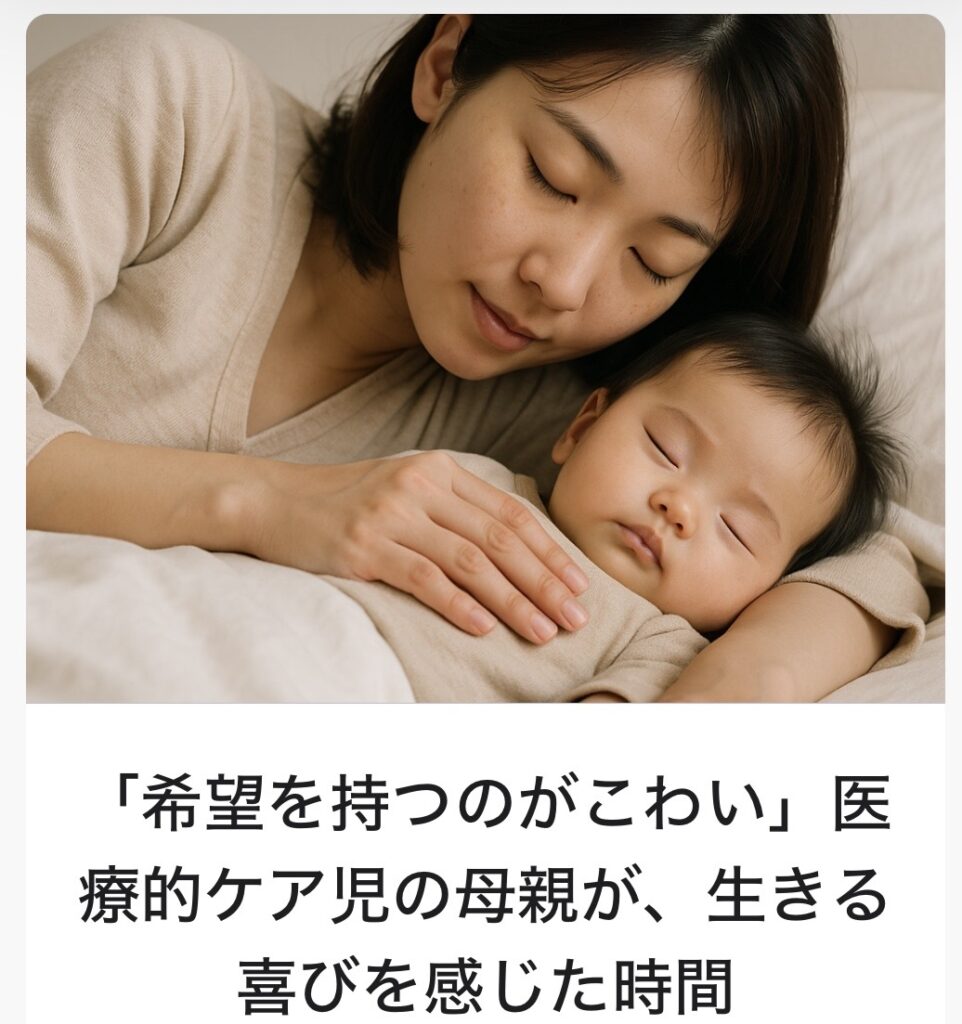
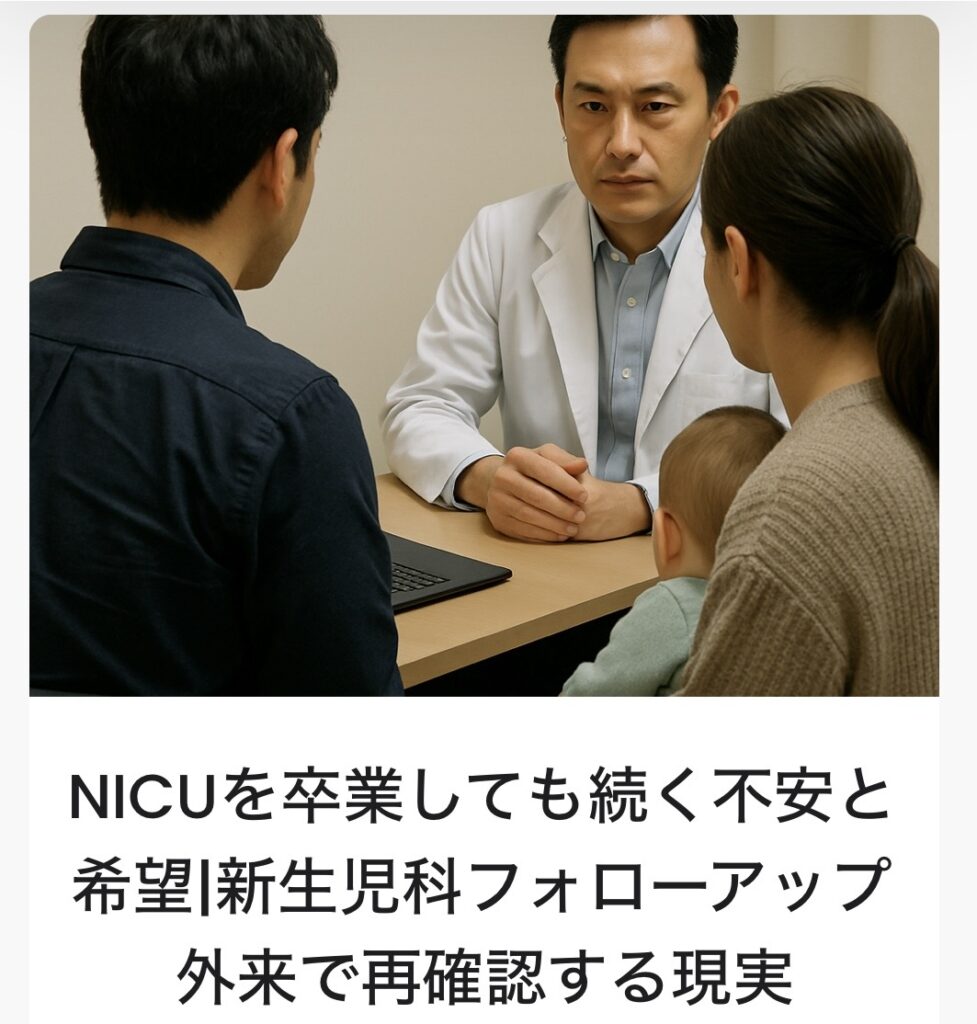

No responses yet